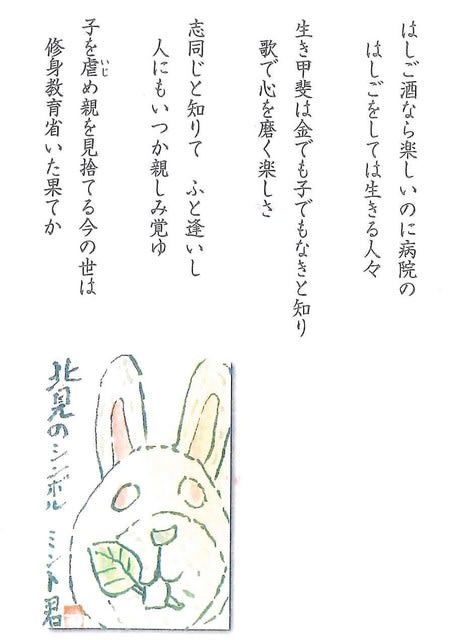文は人なりという諺があるが、言葉は人なりという諺はない。諺にない理由は、当たりまえのことだからだと思う。最近、言ってはいけない言葉を口に出したために、辞職した政治家をたびたび目にしたが、思っているから口に出たのであり、まさに「言葉は人なり」だと思う。
ところで、川端康成の文でも、司馬遼太郎の文でも、村上春樹の文でも感じるが、文は人なりと思う。身から出た錆という諺もあるが、辞職も自業自得で止むを得ないと思っている。
ただ、国会で歯舞・色丹を読めない沖縄北方大臣がいたが、道産子としては笑うに笑えないことでもある。いま国会議員の資質が問われているが、普通の国会議員ならまだしも、いみじくも大臣である。大臣になってかで良いから、北方四島のことをもっと知ってほしいと思う。
「十勝の活性化を考える会」会員
注)北方四島
北方領土、北方四島は、北方地域 - 日本の各種の法令において使用される用語で、1959年の「内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令」(昭和34年政令第33号)では、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島、その他日本国首相が指定する「北方の地域」を指す。1982年の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第87号)では、北方領土を意味する「北方地域」として、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島が示されている。なお、郵政民営化まで、国際郵便料金の分野(郵政省の官報告示など)で、「北方諸島」との用語が使用されていた。ロシアでは、南クリル諸島と呼ぶ。
【北方領土問題】
上記「北方地域」を巡る領土問題であり、終戦前後まで生活の基盤を北方四島に有していた者、並びにその子孫の本拠に関係する問題。
(『ウィキペディア(Wikipedia)』)
注)川端康成
川端 康成(明治32年―昭和47年)は、日本の小説家、文芸評論家。大正から昭和の戦前・戦後にかけて活躍した近現代日本文学の頂点に立つ作家の一人である。1968年、ノーベル文学賞受賞。
大阪府出身。東京帝国大学国文学科卒業。大学時代に菊池寛に認められ文芸時評などで頭角を現した後、横光利一らと共に同人誌『文藝時代』を創刊。西欧の前衛文学を取り入れた新しい感覚の文学を志し「新感覚派」の作家として注目され、詩的、抒情的作品、浅草物、心霊・神秘的作品、少女小説など様々な手法や作風の変遷を見せて「奇術師」の異名を持った。その後は、死や流転のうちに「日本の美」を表現した作品、連歌と前衛が融合した作品など、伝統美、魔界、幽玄、妖美な世界観を確立させ、人間の醜や悪も、非情や孤独も絶望も知り尽くした上で、美や愛への転換を探求した数々の日本文学史に燦然とかがやく名作を遺し、日本文学の最高峰として不動の地位を築いた。日本人として初のノーベル文学賞も受賞し、受賞講演で日本人の死生観や美意識を世界に紹介した。
注)司馬遼太郎
司馬 遼󠄁太郎(1923年(大正12年)―1996年(平成8年)は、日本の小説家、ノンフィクション作家、評論家。本名、福田 定一(ふくだ ていいち)。筆名の由来は「司馬遷に遼(はるか)に及ばざる日本の者(故に太郎)」から来ている。
大阪府大阪市生まれ。産経新聞社記者として在職中に、『梟の城』で直木賞を受賞。歴史小説に新風を送る。代表作に『竜馬がゆく』『燃えよ剣』『国盗り物語』『坂の上の雲』などがある。『街道をゆく』をはじめとする多数のエッセイなどでも活発な文明批評を行った。
(出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』)