標高百数十米の男山と言う名前の山頂に八幡宮が勧請されている。京阪電車の駅前からケーブルで2分もあれば終点である。ここからまだ5分は坂道を登る。
「歩こう」という事になって、表参道から石段を登ることにした。


左:一の鳥居では走井餅を買って、表参道に行く。ここは二の鳥居である。正面に黒い碑で下馬と標記してある。平安時代に宇佐八幡から勧請されてきて以来、多くの貴族・武士・庶民が足を踏み入れた石段である。
右:つづら折れになって登っていきます。傾斜が緩やかなので歩きやすい。


左:この坂は通行止めになっているが、この上には国の史跡の松花堂跡がある。茶人松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)が居を構えたところに向う道である。
右:表参道の最後の石段の横に甘酒の旗をあげる茶店がある。

石段の頂上に道標がある。「右 なら かうやみち」とある。草鞋を履いた旅人が、奈良へ、高野山へと向ったのである。

三の鳥居までやって来た。ここから直線で八幡宮の本殿まで石畳が続く。今日8日はまだお正月気分の人で混雑している。

参道に並ぶ石燈籠はすべて崩壊の恐れがあると書いてある。春日大社などの事を思えば参道がはるかに短いのだが、燈籠が2重3重に並んでいる。約400基という。

京の都を守護したいと九州の宇佐八幡のご宣託で、淀川を上って来て山崎離宮まで来た時に、目前の男山に祀るようにとの神様の意志で鎮座したと言う。
山崎離宮については(06.5.7blog)
以来都の北西、鬼門の比叡山、そして裏鬼門に石清水八幡宮があり、平安の都を守護してきた。人々の信仰はどれほど大きかった事でしょう。それが、この燈籠の寄進であったろう。

南総門は華麗な門である。
「歩こう」という事になって、表参道から石段を登ることにした。


左:一の鳥居では走井餅を買って、表参道に行く。ここは二の鳥居である。正面に黒い碑で下馬と標記してある。平安時代に宇佐八幡から勧請されてきて以来、多くの貴族・武士・庶民が足を踏み入れた石段である。
右:つづら折れになって登っていきます。傾斜が緩やかなので歩きやすい。


左:この坂は通行止めになっているが、この上には国の史跡の松花堂跡がある。茶人松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)が居を構えたところに向う道である。
右:表参道の最後の石段の横に甘酒の旗をあげる茶店がある。

石段の頂上に道標がある。「右 なら かうやみち」とある。草鞋を履いた旅人が、奈良へ、高野山へと向ったのである。

三の鳥居までやって来た。ここから直線で八幡宮の本殿まで石畳が続く。今日8日はまだお正月気分の人で混雑している。

参道に並ぶ石燈籠はすべて崩壊の恐れがあると書いてある。春日大社などの事を思えば参道がはるかに短いのだが、燈籠が2重3重に並んでいる。約400基という。

京の都を守護したいと九州の宇佐八幡のご宣託で、淀川を上って来て山崎離宮まで来た時に、目前の男山に祀るようにとの神様の意志で鎮座したと言う。
山崎離宮については(06.5.7blog)
以来都の北西、鬼門の比叡山、そして裏鬼門に石清水八幡宮があり、平安の都を守護してきた。人々の信仰はどれほど大きかった事でしょう。それが、この燈籠の寄進であったろう。

南総門は華麗な門である。
















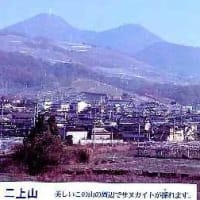
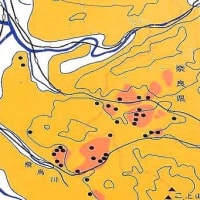


アコードさんのblogを拝見しましたが、どれも素晴らしい影像ですね。良い勉強になりそうで、「お気に入り」に入れて、また訪問します。
産経新聞の紹介を心待ちにしています。
写欲をそそられる情景ばかりですね!
羨ましいです。
アコードさんのブログ活動が産経新聞に
掲載されたので近日中にアップしますご
覧くださいネ。
山上に上がれば結構上ってきた充実感があると思います。見るところが多い。車で山上まで来る道があるのですが、公開していなくて知る人ぞ知るという道で、住宅街とか脇道とかを利用します。
身体のためには、歩くのも良いかも・・。
江戸時代なら駕篭があったかも知れませんね。殿上人のように。
足腰が丈夫でなければ、お参りもタイヘンですネ~。