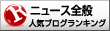しかし、翌日になると武男は体調が回復したのか、朝食の時に春恵にあやまった。
「昨日はごめんね、不機嫌な様子をして」
春恵は特に返事をしなかったが、気を取り直したようだった。太郎と次郎はそれぞれ友だちの家へ遊びに行ったりしたので、2人はしばらく応接間でくつろぐことになった。
武男の問いに春恵が答えるには、彼女はアメリカ・ウィスコンシン州のミルウォーキーの近くの高校に留学することになり、ある篤志家の住まいに寄宿するという。日本からは今回、59人もの高校生がAFSの留学生として渡米するそうだ。
「ずいぶん大勢の生徒が行くんだね」
「日本だけでなく、ヨーロッパなどからも留学生が来るのよ」
春恵はそう言って、AFSについて知っていることをいろいろ話してくれた。武男はもっぱら聞き役だったが、やがて彼女にこう言った。
「天気も良いし、ローリーと一緒に散歩しないか」
「ええ、いいわ」
2人は立ち上がると、庭の犬小屋に向かった。ここには雌のコリー犬がいるが、名前を“ローリー”と言う。これは春恵が名付けたもので、ローズ(ばら)とリリー(ゆり)の一部を組み合わせたものなのだ。
「あら、散歩なの? 昼までには帰っていらっしゃい」
美代子が声をかけたので2人はうなずき、犬を連れて外に出た。
「ローリーは“名犬ラッシー”にそっくりだね」
「コリー犬だもの。どの犬もラッシーにそっくりよ」
そう言って春恵は笑った。ラッシーとはアメリカの映画で有名になった犬だ。
真夏の太陽が照りつける中、武男が犬の鎖を持って歩いていく。2人は日よけ帽をかぶっていたが、すぐに額に汗がにじんできた。
「ずいぶん暑いな、あの木陰で休んでいこう」
前方の小さな公園の木陰を見つけ、武男が歩いていった。春恵がついてくる。2人は公園の片隅のベンチに腰を下ろした。
「太郎君や次郎君は将来、何になりたいのかな」
武男が春恵の弟たちの話を持ち出した。
「次郎はまだ小学生だから分からないけど、太郎は絵が好きだから美術関係の方へ行くでしょう」
家族の話になって、2人はくつろいだ雰囲気になった。互いの兄弟や両親のことに触れるうちに、春恵は自分のことも遠慮なく語り出した。
「わたし、もう少し背が高かったらいいな。あと2センチ、そう、160センチなら良かったのに」
春恵の率直な話に、武男がすぐに受け答えた。
「僕だってそうだよ。165センチじゃ嫌だ、せめて170センチあったらいいのに」
背格好の話になると17歳の少年少女は敏感になるのか、そう言って2人は顔を見合わせて笑った。 他愛のない話が続いて気分がほぐれ、どちらともなく立ち上がると2人は散歩の帰路についた。
今度は春恵がローリーの鎖を持って先に歩き、昼前に帰宅した。すると、美代子が待ち構えたように武男に声をかけた。
「先ほど、久乃さんからあなたに電話があったのよ。もうそろそろ“おいとま”して帰るようにと言われたけど、こちらは一向に構いません、春恵たちも喜んでいるので、どうぞご心配なくと言っておいたわ。
もし気になるなら、あとでお母さんに電話をかけたら」
まるで“家出”をしたように姫路に来たので、武男は気まずい気持ちになっていた。一度は母に電話をしなければならない。父の武義も気にしているだろう。
「分かりました、あとで電話をかけます」
武男はそう答え、昼食を済ますと春恵の部屋に移った。
「僕、そろそろ家に帰らないと駄目だな。お袋から電話があったからね」
すると、春恵が珍しく厳しい顔付きになって言った。
「まだいいでしょ! せっかく来たのに・・・父も母も弟たちも武男ちゃんを歓迎しているのよ」
“武男ちゃん”と幼なじみの呼び名を言われて、彼は親しみを覚えた。しかし、一度は家に電話をかけなければならない。 そう考えると、どうも憂うつになってくるのだ。
武男は応接間で春恵と雑談を交わしていたが、だんだん言葉が少なくなった。
「僕、ちょっと散歩してくるよ」
彼はそう言って立ち上がると、玄関の方へゆっくりと向かった。すると、春恵が急にピアノの前に座って鍵盤に手を置いた。何をするのかと思っていると、彼女はバダジェフスカの『乙女の祈り』を弾き出した。
武男は少し唖然として、立ったままその曲に聴き入る・・・ 春恵の演奏はあまり上手くなかった。何カ所かで“つっかえる”。それでも、彼女は弾くのを止めずに最後まで続けた。
「最近、弾いてないから駄目ね」
吐き捨てるようにそう言うと、春恵はさっさと2階の自分の部屋へ立ち去った。武男はなにか済まないような気持ちになったが、玄関を出ると、午前中に行った公園の方へ歩き出した。
セミの鳴き声がやけにうるさく聞こえる。耳に“こびりつく”ようだ。真夏の太陽もじりじりと照りつける・・・ 汗をかきながら、彼は公園を通り過ぎて、今度は小高い丘を登っていった。なにか無性に歩きたくなっていた。
丘の頂上付近に来ると、木陰を見つけそこでくつろいだ。眼下に広がる景色を眺めていると、わりと先の方に新庄家の屋根が見える。
春恵は今あそこにいるのだなと思うと、武男はその遠景がなにか“尊い”もののように見えた。春恵は今、2階の自分の部屋で何をしているのだろうか・・・ そんな想いに耽りながら、彼はそこでしばらく休んでいた。
散歩の帰りに、武男は少し遠回りをしながら家に戻った。そして、浦和の自宅に電話をかけ、久乃に一両日中には帰宅すると伝えたのである。
その晩は太郎の部屋に集まって、武男は春恵姉弟と遅くまで語り合った。
翌日、朝食を済ますと武男は自転車を借りて、姫路市内の繁華街へ行った。市内を見て回りたいというだけで、大した用事があるわけではない。彼はある書店を見つけて中に入った。
小型の時刻表を買ったあとは“立ち読み”をしていたが、文庫本のところでアメリカの劇作家のユージン・オニールの作品を見つけた。秋には高校の演劇部発表会で、オニールの作品のどれかを“出し物”にすることが決まっていたから、武男はついでにその文庫本も買った。帰りの汽車の中で、ゆっくり読むつもりなのだ。
そして、新庄家に戻ると、美代子が「春恵は2階の部屋にいるわよ、行ってあげて」と言う。
武男が2階の部屋に入ると、春恵の姿を見て一瞬 立ちすくんだ。彼女はベッドに横たわりながらじっとこちらを見つめ、悩ましげな笑みを浮かべている。
「どうしても今日帰るの?」
春恵の問いに武男は少し動揺したが、ベッドの側の椅子に無言で腰を下ろした。
「もっといたらどうなの・・・」
彼女が重ねて言ってくるが、武男はしばらく返事をしなかった。もっといたいのは“やまやま”だが、母には一両日中に帰ると昨日 伝えたばかりだ。約束は守らなければならない。彼はやっと答えた。
「母に今日か明日、帰ると言ったんだもの」
「あなたは一度言ったら聞かないのね」
春恵はそう言って、ベッドの上でゆっくりと寝返りを打った。その動作が妙に悩ましく、武男は体の芯から熱くなるのを覚えた。
どうしようもない時間を過ごしていると、やがて美代子が現われ声をかけてきた。
「武男さん、やっぱり帰るの?」
「ええ、今夜の夜行で帰ります。どうもお邪魔しました」
武男はようやく立ち上がり、階下に降りて帰り支度を始めた。
そして夕方、彼は春恵とともに姫路駅へ行き、彼女と駆けつけた一郎が見送る中を夜行列車に乗って東京へ向かった。車窓から手を振る武男に対し、春恵もずっと手を振り続けていた。
5)浦和にて
姫路から遠ざかるにつれて、武男はしだいに“悔恨”の思いが湧いてくるのを感じた。それはだんだん強まり、やがて心に重くのしかかってきた。
自分は春恵に対し、極めてわがままに勝手気ままに振る舞ったのではないか。六甲山へ行った時も新庄家にいる時も、彼女に無礼で不機嫌な態度をしばしば見せたように思う。
自分は春恵に対し、なぜ優しくしてあげられなかったのか・・・ 反省の感情だけが込み上げてくる。この“償い”をぜひしなければならない・・・ 償いって何をすれば良いのか? どうすれば償えるのか。
そう考えていると、武男はほかに何もする気が起きなかった。せっかく買ったユージン・オニールの作品も読む気がしなくなり、彼はただ呆然として汽車のシートに身を寄せていた。 脳裏に迫りくるのは春恵の“幻影”だけで、夜行列車の一晩はあっという間に過ぎたのだ。
武男は浦和の自宅に戻ると、すぐに春恵宛てに手紙を書いた。それは悔恨と償いの感情に満ちており、最後に彼女がアメリカへ旅立つ前に、ぜひ会いたいとの願いを吐露したものだった。
「春恵さんや皆さんは、元気だったの?」
久乃が当たり前のことを聞いてくるが、武男は「うん」と返事をしただけで黙ってしまった。彼は母に多くを語りたくなかったのだ。
しかし、帰宅して少し落ち着いたのか、武男はオニールの作品に目を通した。そして、高校の演劇部発表会には彼の戯曲『交戦海域』が良いと思い、9月になったら同僚の部員に勧めたいなどと考えていた。
そうするうちに、春恵からも手紙が届いた。武男の手紙とは“行き違い”のようなものだったが、彼女は手みじかに、アメリカへ行く前に青木家に挨拶に訪れたいと書いていた。
やがて、8月の中旬になって、美代子が春恵を伴なって浦和の青木家にやって来たのである。
その日の夕方近く、母と娘が現われた。春恵は水色の半袖ブラウスとスカートを着ており、その清々しさに武男は思わず見とれてしまった。
彼は両親や美代子親子と夕食を共にしたが、両親と美代子は名古屋時代の昔話などですっかり話がはずんでいた。このあと、国義は春恵に向かって、昔、自分が満州や朝鮮へ一人で旅立った話をして、彼女のアメリカ留学を励ましたりした。
自分だけ“仲間はずれ”にされた感じになり、武男は「僕、部屋に戻るよ」と言って、席を外した。そうすれば、春恵がじきに部屋に来てくれるだろうと思ったからだ。
ところが、国義は酒が入ったせいだろうか、上機嫌で春恵に満州などの一人旅の話を続けているようだ。彼女はなかなかやって来ない。
「畜生、オヤジは春恵を“独り占め”にしやがって!」
怒った武男はぷいと部屋を出ると、そのまま外出した。別に行くあてもなく、30分ぐらい散歩をして家に戻ると、国義たちはまだ雑談をしているようだ。
武男はもう絶望的になって、ベッドの上に寝ころがった。春恵も春恵だ、くだらない話に付き合っているなんて、勝手にしろと言いたい。さっき家を出たのも、彼女に早く自分の部屋に来てほしいからそうしたのだ。
なんて馬鹿々々しい、これが春恵との最後の晩だなんて・・・ 武男がじりじりしながら待っていると、食堂の方から国義の声が聞こえた。
「それでは元気に行っておいで」
ようやく団らんが終わったのか、父が自分の部屋に引っ込んでしまったので武男はほっとした。 すると、しばらくして春恵が薄暗い部屋に入ってきた。
「ごめんなさい、待たせてしまって」
「ああ、待ったよ、ずいぶん待った!」
彼女が謝ったのに、武男はまだ憮然としている。
「あなたがさっき、家を出て行ったのも知っていたわ」
「貴重な時間を台無しにしてしまうなんて、オヤジもオヤジだ!」
「でも、お父さまのことを悪く言っては駄目よ。先ほど、とても励ましてもらったもの」
2人のたわいない会話が続いたあと、春恵がベッドの端にそっと腰を下ろした。
彼女が座っているだけで、アジサイかスミレのような雰囲気が伝わってくる。清々しい香りも漂ってくるようだ。
春恵はかすかな微笑みをたたえ、床に目を落としている。武男はもう何も言葉を発することができなかった。彼女の横顔に時おり視線を向けるだけで、感無量で胸が一杯になった。
どうすれば良いのか呆然としていると、春恵がふと立ち上がり、部屋から庭に面した廊下へ出ていった。しばらくして、武男がその後についていくと、彼女は隅の方でうずくまっている。
「どうしたの、お腹(なか)が痛いの?」
武男が声をかけたが、返事がない。やがて、春恵は立ち上がると部屋の方へ戻ってきた。どうしていいか分からず、彼は思わず、左手を彼女の背に当てた。その途端、彼女は頬を朱色に染め、両眼が星のように輝いた。
驚いた武男は、思わず春恵を前方へ突き放した。彼女の体はベッドの上に転がり落ちたのである。 不器用な17歳の少年は、少女の扱い方を知らなかったのだ。
自分の突拍子もない行動に、武男は慙愧の念に堪えられなくなった。彼はしばらく“木偶(でく)の坊”のように立ち尽くしていた。春恵はベッドの上で座り直していたが、その横顔は叱られた少女のように青ざめている。 枕元の電気スタンドの淡い光が、彼女を浮き立たせているようだ。
自分はなんて馬鹿なんだ、申し訳ない! 悔恨の情にさいなまれ、武男は崩れ落ちるように春恵の側に身を投げた。
「ごめんね」と謝ればいいのに、彼はそれが言えず、おずおずと右手を彼女の左手の上に重ねた。すると、彼女の手の温かみが伝わってくる。彼は力を入れてその手を握り締めた。
下からうかがうと、春恵がかすかにほほ笑んだ感じがする。やがて、彼女の優しい視線を受けて、武男は“許された”と感じた。彼はゆっくりと身を起こし、今度こそ「ごめんね」とささやいた。
そして、春恵の身体をそっと抱くと、炎のように熱い! 彼は一瞬たじろいだが、そのままの姿勢で耐えたのである。
枕元の扇風機が回転しながら、2人の熱した身体を心地よく冷やしてくれているようだ。やがて、武男が声をかけた。
「僕の写真と詩集をアメリカへ持っていってくれる?」「ええ、いいわ」
春恵が承諾したので、彼は机の引出しから写真などが入った封筒を取り出し、彼女に手渡した。そして、またベッドに横になると、今度は思いつくままにあれこれとしゃべり出した。
春恵は黙って聞いていたが、いつの間にか床に腰を下ろしてベッドに寄りかかり、両腕をその上にながながと伸ばしていた。武男はすっかり上機嫌になり、彼女の両手を握ってはもてあそび、軽口をたたいた。
「春ちゃん、もうお別れだね。アメリカへ行ったら手紙をちょうだいよ、待ってるからね。君の写真も送って欲しいな・・・」
彼の饒舌(じょうぜつ)は続いたが、美代子親子が帰る予定の夜9時が迫ってきた。 武男が「あと10分」「あと7分」「あと5分」などと気ぜわしく言うので、春恵がほほ笑んだ。しかし、彼女は両手を武男に預けたまま、最後の“一時”を満喫しているようであった。
すると、部屋の外から急に美代子の声が聞こえた。
「春恵、そろそろお暇(いとま)しますよ」
薄暗い部屋に入ってきた彼女は、2人の様子を見て一瞬 驚いたように立ちすくんだ。美代子の声を聞いて、武男が我(われ)に返ったようにベッドから起き上がると、春恵もゆっくりと身を起こした。
美代子親子はその夜、東京の親戚の家に泊まる予定なのだ。2人はそのまま玄関に出ると、久乃と武男に別れの挨拶をした。
「それでは明後日(あさって)、横浜でお会いしましょう」
久乃がそう言うと美代子がにっこりとほほ笑み、春恵は右手で武男の左手首を握り締めた。彼女の温かい血流が伝わってくるようだ。
やがて、美代子親子は門外に待たせてあったタクシーに乗り込んだ。春恵が窓を開けて手を振ると、武男も手を振る・・・ タクシーは闇の中へと去っていった。
6)横浜港の別れ
2日後、久乃と武男は春恵を見送るため横浜港に出かけた。昼過ぎに港に着くと、春恵はすでに乗船しており、一郎・美代子夫妻が出迎えてくれた。
「遠い所を、わざわざお見送りに来ていただいて恐縮です」と、一郎が丁寧に挨拶する。
「いえいえ、今日は春恵さんの門出の晴れ姿を、ぜひ拝見したくて参ったのですよ」と、久乃が答えた。
4人は雑談を交わしていたが、そのうち、一郎が「私は船内を少し見てみたいのですが、武男君、一緒に行かないか」と誘ってきた。
武男はもちろん異存がないので、2人は客船の中へ入っていった。船内は入り組んでいて昇り降りもある・・・ やがて、AFS留学生が寝泊まりする2等船室にたどり着いた。
「だいぶ、狭苦しいな」
一郎がそうつぶやいたが、2段ベッドが窮屈そうに並んでいる室内を見ると、たしかに狭苦しい感じがする。
「でも、デッキへ出たりお茶を飲んだりしていれば、気が晴れますよ」
「そうだな、高校生だから贅沢はできないさ」
そんなことを言い合って、2人は船のデッキへ出てみた。すると、AFSの留学生たちに、見送りに来た人たちが盛んにエールを送っていた。
「〇〇君、元気でやれよ!」
「アメリカへ行く○○さん、万歳!」
声援や叫び声があちこちから湧き上がっている。1年間、遠いアメリカで過ごす高校生たちに、父兄はもとより恩師、友人たちのエールが“こだま”していた。
「あっ、春恵さんがいた」
彼女の後ろ姿を見つけた武男が一郎に呼びかけたが、彼はじっと黙っている。万感 胸に迫って言葉が出ないようだ。 武男は春恵に声をかけようかと思った。
しかし、彼女も見送りに来た恩師や友人らのエールに応えて、手を振ったりしている。 しばらく迷っていると、地元の新聞社の記者だろうか(腕章を巻いていた)、春恵に声をかけて何やらインタビューを始めた。
春恵は頬を紅潮させながら、なんとか答えていた。インタビューはけっこう長く続く・・・ そのうち、出航の時刻が近づき、武男たちは下船することになった。
2人が埠頭に戻ると、そこは見送りに来た人たちでごった返していた。真夏の強い日差しが照りつけ熱気でむんむんしていたが、五色のテープが飛び交い、港の活気に満ちていた。
美代子たちが買ったテープを、武男も船に向かって投げ、投げ返されたテープを受け取ったりして船の出航を待った。波止場から音楽隊の『蛍の光』などが鳴り響く・・・
一郎や美代子の話によると、客船は横浜を出ると、2週間をかけてカナダのバンクーバーに着くそうだ。そこから留学生たちはそれぞれの場所へ行くのだが、春恵は飛行機でミルウォーキーへ向かうという。けっこうな“長旅”である。
しかし、長旅だからこそ、一緒に行く人たちと知り合い、仲良くなれるかもしれない。船旅の良い点はそこにあるのだろうと、武男は思った。
「それにしても、賑やかな見送りですね」
武男が美代子に話しかけると、彼女は待ってましたと言わんばかりに答える。
「さっき、見送りに来た人と話したら、宝塚歌劇団が客船に乗ってるんですって」
「えっ、宝塚が?」
「そうよ、なんでもカナダとアメリカで11月まで公演するんですって。だから、見送りも華やかで賑やかになったのかしら」
宝塚歌劇団が大好きな美代子が、得意そうに答えた。そうか・・・賑やかなのは、それもあるかもしれない。武男がそう思っていると、美代子がさらに付け加えた。
「この船にはフルブライトの奨学生さんや、日本に留学していたアメリカの高校生も乗っているそうよ。ずいぶん国際的だわ」
それは素晴らしいではないか。春恵たちAFSの留学生はそういう人たちに混じって、ますます“やる気”を起こすだろう。
「隣の送迎フロアーに行きませんか」
ここで武男が誘いを入れた。隣の送迎フロアーとはビルの“高台”のことで、船客の姿がすぐ近くから見える所なのだ。ところが、一郎夫妻は春恵の恩師やクラスメートと話し合っているため、武男は久乃と一緒にそこへ行くことにした。
高台に着くと、春恵の姿はすぐに分かった。彼女は時々 会釈したり手を振ったりして、見送りに来た人たちに挨拶している。
それは良いが、武男はふと、彼女が遠い存在になりつつあるように思えた。一昨日(おととい)まであんなに親しくしていた春恵が、今や自分の“独占物”ではなく、大勢の人の“共有物”になった感じがしたのである。
そう思うと、武男はだんだん妬ましくなってきた。それは単なる“わがまま”でしかないが、彼は陰うつな気分になってきた。そうするうちに、春恵の視線が武男の姿を捉えた。彼女は武男のふて腐れた表情を見て、おかしいと思ったようだ。
次の瞬間、彼女は天を向いて笑ったのである。これには武男がカッとなった。
「お母さん、僕もう帰るよ」
そう言って立ち去ろうとすると、久乃があわてて制止した。
「駄目よ、なにを言うの、きちんと見送りなさい」
母の説得で、彼はしばらくそこにいたが、無性に独りになりたくなる・・・ やがて、汽笛が鳴って出航の時がきた。演奏の音楽がさらに強く鳴り響き、客船はゆっくりと埠頭から離れていく。
武男はもうその場にいることができず、「ごめん」とだけ母に言うと、逃げるようにして送迎フロアーから離れた。彼は去っていく客船に時おり目をやりながら、港のバスターミナルへと急ぎ足で向かった。
言いようもない寂しさと諦めの気持ちが湧いてくる。春恵はいま、太平洋に出てカナダ、アメリカへ向かっているのだ。 彼女は自分の手から離れた。彼女は天使のような、いやヴィーナス(女神)のような存在になりつつある。
もう手の届かない存在、17歳の乙女・・・そう思うと悲しい気持ちになる。
しかし、武男がバスに乗って着席すると、やがて、春恵に送った詩や写真のことを思い出した。
『あなたの胸に抱かれて 僕の心は太平洋を越える あなたの胸のときめきに 僕は生きる希望を感じる 長き別れの時の中に 二つの命はさらに燃える・・・』
その詩を思い出すと、武男の悲しい気持ちは、しだいに甘美な慕情へと変わっていった。(完)