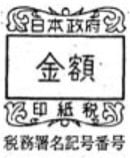1.事業承継税制の趣旨
事業承継税制とは、中小企業の経営者から後継者(子、孫など)へ事業を円滑に承継させるための支援の制度をいう〈さしあたり、石村耕治編『税金のすべてがわかる現代税法入門塾』〔第11版〕(2022年、清文社)383頁[浅野洋、木村幹雄担当]、金子宏『租税法』〔第二十四版〕(2021年、弘文堂)752頁、小池正明『知っておきたい相続税の常識』〔第23版〕(2022年、税務経理協会)261頁を参照。とくに実務家向けの書籍や雑誌掲載記事(「税経通信」、「税務弘報」、「税理」などの)を読むとよい〉。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、中小企業経営承継円滑化法)の附則第2条は「政府は、平成20年度中に、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする」と定めていた。これを受ける形で、2009(平成21)年度税制改正により、事業承継税制が導入され、2008(平成20)年10月1日に遡って適用された〔租税特別措置法第70条の7以下、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成21年3月31日法律第13号)附則第63条〕。
その後、2018(平成30)年度税制改正により、事業承継税制の適用要件が大幅に軽減される特例措置が追加された。この特例措置は、2018年1月1日から2027(令和9)年12月31日までの間に相続または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用される)。続いて、2019(平成31=令和元)年度税制改正により、個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度、および個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度が創設された。この納税猶予制度は、2019年1月1日から2028(令和10)年12月31日までの間に相続または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用される。
さらに、2021(令和3)年度税制改正により、個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が拡充された(特定事業用資産に、一定の要件を備えた自動車が加えられる)。また、非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度の適用対象が拡充された。この特例制度は、後継者が相続開始直前において特定認定承継会社の役員でない場合であっても、被相続人が70歳未満であるとき(改正前は60歳未満)、または後継者が中小企業経営承継円滑化法施行規則に定められた確認を受けた特例承継計画に特例後継者として記載されているときには、特例制度の適用を受けることができる、というものである。
2021年度税制改正については、自由民主党・公明党「令和3年度税制改正大綱」(2020年12月10日)45頁を参照されたい。
2.相続税に係る事業承継税制 一般措置
まず、認定承継会社とは、中小企業経営承継円滑化法第12条第1項に定められる認定(円滑化法認定。租税特別措置法第70条の7の2第2項第4号、同第70条の7第2項第4号)を受けた中小企業(同第1号)。その株式は非上場株式である。なお、常時使用従業員が1名以上であること、政令で定める資産保有型会社または資産運用型会社に該当しないこと、風俗営業会社に該当しないこと、などの要件がある。
ここで、認定承継会社に該当しない資産保有型会社は、総資産の帳簿価額に占める特定資産の帳簿価額の合計額の割合が70%以上である会社をいう。また、認定承継会社に該当しない資産運用型会社は、総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が75%以上である会社である。
次に、特定資産とは、有価証券、当該会社が自ら使用していない不動産、ゴルフ会員権、現金預金などをいう。
事業承継税制の適用を受けるためには、次のような要件がある。
まず、被相続人については、相続開始前において認定承継会社の代表権を有していた者であり、経営承継相続人等となる者を除く同族関係者と合わせて過半数の議決権を有するとともに筆頭株主であったことなどの要件がある。
次に、経営承継相続人等については、被相続人から相続または遺贈により、当該認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限定される)を取得した相続人等(同第3号)。相続開始日の翌日から5か月を経過する日において当該認定承継会社の代表権を有し、同族関係者と合わせて過半数の議決権を有し、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き当該認定承継会社の株式等の全てを有する、などの要件がある。
ここで、非上場株式等とは「当該株式に係る会社の株式の全てが金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式」(同第70条の2第2項第2号イ)または「合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの」(同ロ)である。
納税猶予分の相続税額は、当該認定承継会社の非上場株式等の発行済み株式または出資の3分の2までの部分に係る相続税額の80%(同第70条の7の2第2項第5号イに掲げる金額から同ロに掲げる金額を控除することによる)である〈80%とされたのは、個人事業者の場合には事業用宅地等の価額の80%に相当する額が相続税の課税価格から除外されていることと平仄を合わせるためである。金子・前掲書756頁〉。結局、発行済株式または出資の総数または総額の約53%が猶予されるということになる。
経営承継相続人等が被相続人から非上場株式等を相続または遺贈により取得した場合で、相続税法第27条第1項の規定による申告書に租税特別措置法第70条の7の2第1項の適用を受けようとする旨の記載をしたときには、納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、当該承継相続人等の死亡の日まで、納税猶予分の相続税額について納税が猶予される(租税特別措置法第70条の7の2第1項。用語の定義については同第2項も参照)。担保は、国税通則法第50条に定められる担保(公債、社債、土地、建物など。手続は国税通則法施行令第16条による)の他、認定承継会社の非上場株式等も認められる(手続は租税特別措置法施行令第40条の8の2第5項以下に定められる)。非上場株式等の全てが担保として提供された場合には、当該非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないとしても、租税特別措置法第70条の7の2第1項の適用については当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなされる(同第6項本文)。
租税特別措置法第70条の7の2第1項の適用を受けた経営承継相続人等が非上場株式等を所有したまま死亡した場合には、納税猶予分の相続税額が免除される(同第16項第1号)。
また、経営承継期間〈租税特別措置法第70条の7の2第2項第6号により、同第1項の適用を受ける旨の申告書の提出期限の翌日から5年を経過した日、または経営承継相続人等の死亡の日の、いずれか早い日までの期間と定義される〉の末日の翌日以後に、経営承継相続人等が第70条の7第1項の適用に係る贈与をした場合には「猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る特例非上場株式等で同項の規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税」が免除される(同第2号。同第17項以下、租税特別措置法施行令第40条の8の2第44項も参照)。
なお、経営承継期間内に経営承継相続人が認定承継会社の代表権を有しなくなった場合など、納税猶予期間が打ち切られる場合がある(租税特別措置法第70条の7の2第3項〜第6項、第9項、第10項、第12項、第13項)。
3.相続税に係る事業承継税制 特例措置〈石村編・前掲書384頁において説明されているのは特例措置である。〉
2018年度税制改正により追加された特例であり、適用期間は2018年1月1日から2027年12月31日までとされる。
まず、特例認定承継会社は、中小企業経営承継円滑化法第12条第1項の認定(特例円滑化法認定。租税特別措置法第70条の7の5第2項第2号)を受けた中小企業である(同第70条の7の6第2項第2号)。その株式は非上場株式である。
次に、特例被相続人は、特例認定承継会社の代表権を有していた者である。また、特例経営承継相続人等とは、特例被相続人から相続または遺贈により、当該特例認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限定される)を取得した相続人等である(同第7号。当該特例認定承継会社が定めた2人または3人まで)。さらに、特例非上場株式等とは、租税特別措置法第70条の2第2項第2号に定められる株式または出資である(同第70条の7の6第2項第5号)。
納税猶予分の相続税額は、当該特例認定承継会社の非上場株式等の発行済み株式または出資に係る相続税額の全額である(同第1項)。結局、発行済株式または出資の総数または総額の100%が猶予される。
特例経営承継相続人等が特例被相続人から非上場株式等を相続または遺贈により取得した場合で、相続税法第27条第1項の規定による申告書に租税特別措置法第70条の7の6第1項の適用を受けようとする旨の記載をしたときには、納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、当該承継相続人等の死亡の日まで、納税猶予分の相続税額について納税が猶予される(租税特別措置法第70条の7の6第1項。用語の定義については同第2項も参照)。担保については、租税特別措置法第70条の7の6第4項により、同第70条の7の2第6項が準用される。
租税特別措置法第70条の7の6第1項の適用を受けた特例経営承継相続人等が非上場株式等を所有したまま死亡した場合には、納税猶予分の相続税額が免除される(同第12項により、同第70条の7の2第16項から第21項までが準用される)。
特例経営承継期間〈租税特別措置法第70条の7の6第2項第6号により、同第1項の適用を受ける旨の申告書の提出期限の翌日から5年を経過した日、または経営承継相続人等の死亡の日の、いずれか早い日までの期間と定義される〉の末日の翌日以後に、特例経営承継相続人等が第70条の7第1項の適用に係る贈与をした場合には「猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る特例非上場株式等で同項の規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税」が免除される(同第70条の7の6第12項)。
特例措置の適用を受けるためには、2018年4月1日から2024年3月31日までの期間内に「特例承継計画」を作成し、中小企業経営承継円滑化法第12条第1項に規定される認定を受けなければならない。
特例経営承継期間内に特例経営承継相続人が特例認定承継会社の代表権を有しなくなった場合など、納税猶予期間が打ち切られる場合がある(租税特別措置法第70条の7の6第3項〜第9項による同第70条の7の2第3項〜第13項の準用)。
特例認定承継会社の事業の継続が困難になったとして政令で定められる一定の場合において、特例経営承継期間の経過後に当該特例認定承継会社の非上場株式の全部または一部の譲渡をするとき、当該特例認定承継会社が合併により消滅するとき、当該特例認定承継会社が株式交換または株式移転により他の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号、同第773条第1項第5号を参照)となったとき、または当該特例認定承継会社が解散をしたときには、税額を再計算のうえ、差額の減免などが行われる(租税特別措置法第70条の7の6第13項〜第20項)。
4.贈与税に係る事業承継税制 一般措置
まず、認定贈与承継会社は、中小企業経営承継円滑化法第12条第1項の認定を受けた会社のうち、当該会社の常時使用従業員が1人以上であることなど、租税特別措置法第70条の7第2項第1号に掲げられる要件をみたすものである。
次に、贈与者は、当該認定贈与承継会社の代表権を有していた個人で、租税特別措置法施行令第40条の8第1項に掲げられる要件を全て満たす者である。これに対し、経営承継受贈者は、贈与者から贈与により当該認定贈与承継会社の非上場株式等を取得した個人で、租税特別措置法第70条の7第2項第3号に掲げられる要件(贈与の日において満20歳以上である、贈与の時において認定贈与承継会社の代表権を有している、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり認定贈与承継会社の役員などの地位に就いている、など)の全てを満たす者である。
また、特例受贈非上場株式等は、当該認定承継会社の発行済株式または出資の総数または総額の3分の2に達するまでの部分(政令で定められた部分)である。納税猶予分の贈与税額は、当該認定承継会社の非上場株式等の価額である(同第2項第5号)。
経営承継受贈者が贈与人から特例非上場株式等を生前贈与により取得した場合で、相続税法第28条第1項の規定による申告書に租税特別措置法第70条の7第1項の適用を受けようとする旨の記載をしたときには、納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、当該承継相続人等の死亡の日まで、納税猶予分の贈与税額について納税が猶予される(租税特別措置法第70条の7第1項。用語の定義については同第2項も参照)。ここで、担保は、国税通則法第50条に定められる担保(公債、社債、土地、建物など。手続は国税通則法施行令第16条による)の他、認定承継会社の特例非上場株式等も認められる(手続は租税特別措置法施行令第40条の8第3項以下に定められる)。特例非上場株式等の全てが担保として提供された場合には、当該特例非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないとしても、租税特別措置法第70条の7第1項の適用については当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなされる(同第6項本文)。
贈与者の死亡の時以前に経営承継受贈者が死亡した場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税が免除される(同第15項第1号)。
贈与者が死亡した場合には、猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与した特例受贈非上場株式等に対応する部分の額として政令で定められた金額に相当する贈与税が免除される(同第2号。租税特別措置法施行令第40条の8第37項も参照)。
経営贈与承継期間〈租税特別措置法第70条の7の2第2項第6号により、同第1項の適用を受ける旨の申告書の提出期限の翌日から5年を経過した日、または経営承継相続人等の死亡の日の、いずれか早い日までの期間と定義される〉の末日の翌日以後に、経営承継相続人等が第70条の7第1項の適用に係る贈与をした場合には「猶予中贈与税額のうち、当該贈与に係る特例受贈非上場株式等で同項の規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税」が免除される(租税特別措置法第70条の7第15項第3号。同第16項以下、租税特別措置法施行令第40条の8第38項も参照)。
経営贈与承継期間内に経営承継相続人が認定承継会社の代表権を有しなくなった場合など、納税猶予期間が打ち切られる場合がある(租税特別措置法第70条の7第3項〜第6項、第11項、第12項)。
5.贈与税に係る事業承継税制 特例措置
2018年度税制改正により追加された特例であり、適用期間は2018年1月1日から2027年12月31日までとされる。
まず、特例認定贈与承継会社は、中小企業経営承継円滑化法第12条第1項の認定(特例円滑化法認定)を受けた会社のうち、当該会社の常時使用従業員が1人以上であることなど、租税特別措置法第70条の5第2項第1号に掲げられる要件をみたすものである。
次に、特例贈与者は、当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していた個人で、租税特別措置法施行令第40条の8の5第1項に掲げられる要件を全て満たす者である。これに対し、特例経営承継受贈者は、特例贈与者から贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等を取得した個人で、租税特別措置法第70条の7の5第2項第6号に掲げられる要件(贈与の日において満20歳以上である、贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有している、贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の議決権の過半数を有する、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特例認定贈与承継会社の役員などの地位に就いている、など)の全てを満たす者(当該特例認定承継会社が定めた2人または3人まで)である。また、特例受贈非上場株式等は、租税特別措置法第70条の2第2項第2号に定められる株式または出資である(同第70条の7の5第2項第5号)。
納税猶予分の贈与税額は、当該特例認定承継会社の非上場株式等の発行済み株式または出資に係る相続税額の全額である(同第1項)。結局、発行済株式または出資の総数または総額の100%が猶予される。
特例経営承継受贈者が特例受贈者から特例非上場株式等を生前贈与により取得した場合で、相続税法第27条第1項の規定による申告書に租税特別措置法第70条の7の5第1項の適用を受けようとする旨の記載をしたときには、納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、当該特例受贈者の死亡の日まで、納税猶予分の贈与税額について納税が猶予される(租税特別措置法第70条の7の5第1項。用語の定義については同第2項も参照)。
その上で、当該特例贈与者が死亡した場合には、贈与税が免除され、特例経営承継受贈者が当該特例受贈者から特例非上場株式等を相続または遺贈により取得したものとみなされる(相続税に移行することとなる。同第70条の7の7第1項)。さらに、当該特例経営承継受贈者が死亡するまで相続税の納税が猶予され、当該特例経営承継受贈者が死亡することにより、相続税も免除される(同第70条の7の8)。
なお、担保については、租税特別措置法第70条の7の5第4項により、同第70条の7の2第6項が準用される。
▲第3版における履歴:2022年11月23日掲載。
▲第2版における履歴:「28 事業承継税制」として、2017年12月4日掲載。