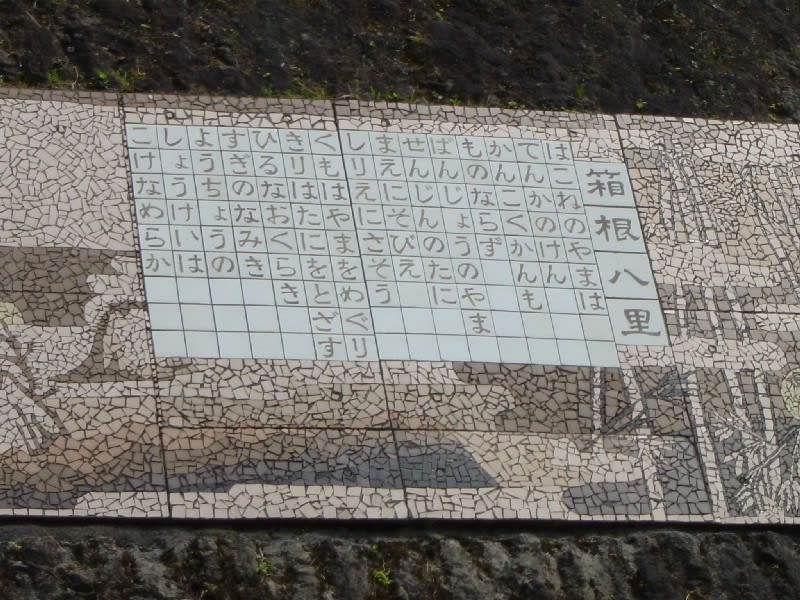今回も、「日本国憲法ノート」〔第5版〕からの復活掲載です。第16回の「経済的自由権その1—序論と憲法第22条—」ですが、ここに掲載するにあたって改題しました。なお、一部を修正しています。
★★★★★★
1.経済的自由権序論
歴史的に見れば、経済的自由権こそが、近代市民革命の原動力となったものである。このことは、とくに財産権の保障に、そして裏返しの形で、しかも濃厚な意味合いを帯びて納税の義務に現われている。そして、精神的自由権の優越性を承認するにせよ、経済的自由権が保障されない限り、人間が人間としての生活を(十分に)営めないことは、近年においては東欧諸国における体制変換(ドイツ民主共和国の消滅)から理解しうる。
フランス人権宣言第17条は、財産権を「神聖かつ不可侵」の人権と位置づけていた。これを文字通りに理解することには注意が必要であるが、少なくとも、経済的自由権の絶対性は基本的に支持されていたと考えてよい。とくに、19世紀のイギリスではベンサム(Jeremy Bentham, 1748-1832)やJ.S.ミル(John Stuart Mill, 1806-1873)の功利主義が勃興し、急速な展開を見せるようになる。これは、他の国にも強い影響を与えた。
しかし、経済的自由権は、或る意味において市民の利己心を正当化することになるし、競争を正当化することになる。これを放任した場合、結局、経済的強者と弱者を拡大再生産することになり、平等規定の空洞化を生じることになるし、多くの社会問題を生ずることになる。さらに、いわゆる市場の失敗という現象がある。そのため、経済的自由権については、とくに内在的制約のみならず、外在的な政策的制約がなされることになった。
このことを憲法において示した最初の例が、ドイツのヴァイマール憲法第153条である。この規定は、次のようなものである。
「所有権は、憲法により保障される。その内容とその限界は、法律によって定める。
公用収用は、公共の福祉のため、かつ法律上の根拠に基づいてのみ行うことができる。公用収用は、ライヒ法律に別段の定めがないかぎり、正当な補償の下にこれを行う。補償の金額について争いのあるときは、ライヒ法律に別段の定めがないかぎり、通常裁判所に出訴することができるようにしなければならない。ラント、公共団体および公益上の団体に対してライヒが公用収用を行う場合には、必ず補償しなければならない。
所有権は義務を伴う。その行使は、同時に公共の福祉に役立たなければならない。」
〔訳は、カール・シュミット(阿部照哉=村上義弘訳)『憲法論』(1974年、みすず書房)468頁による。〕
もっとも、1990年代より「政府の失敗」が叫ばれるように、経済的自由権に対する規制の結果として、かえって既存の業者などが保護され、国民に不利益を与える現象が多く見られることは否定できない( 規制緩和やビッグバンの問題である)。従って、外在的な政策的制約の是非については、個別的に再検討をする必要がある( おそらく、数多くの規制が、その正当性を失うことになるであろう)。
但し、そのことは、新保守主義が説くように、社会福祉などを含めた政府の役割を全て否定し、または、そこまで行かなくとも大幅に削減することを、直ちに正当化するものではない。環境問題などを考えれば明らかである。
また、最近では、たとえばタクシー業界における労働条件などの悪化、およびそれが原因の一つと考えられる交通事故の増加、ネットカフェ難民など、規制緩和の行き過ぎによると考えられる弊害が顕著になっている。いかに「政府の失敗」が強調されようとも、「市場の失敗」が完全に克服される訳ではない。
経済的自由権を考察する場合、以上の点に留意しなければならない。
日本国憲法においては、経済的自由権として、職業の自由(憲法第22条第1項)、居住・移転の自由(同第22条第1項)および財産権(同第29条)が規定される。このうち、居住・移転の自由は、歴史的な経緯によって、便宜的に経済的自由権に含められているのであり、純粋な経済的自由権ではない。むしろ、憲法学は、精神的自由権あるいは人身の自由として扱う。第22条第1項は明文で「公共の福祉」を定めるが、居住・移転の自由については安易に「公共の福祉」による制約を認めるべきでないとするのが、憲法学において述べられるところである。
これに対し、職業の自由と財産権については、明文により、「公共の福祉」による制約が認められる。
なお、経済的自由権の解釈(とくに第29条)に際しては、憲法第25条ないし第28条(とくに第25条)に留意する必要がある。歴史的な経緯という理由もあるが、原理的にも、第29条第1項と第25条とが対抗関係にあり、両者の均衡を保つような解釈が求められる。少なくとも、第29条第1項に示された原理は、第25条に示された原理によって制約を受けると理解するのが妥当であろう。
2.職業の自由(憲法第22条第1項)
憲法における「職業選択の自由」は、職業を決定する自由(狭義の選択の自由)と職業活動の自由とを含み、職業活動の自由は、憲法第29条第1項をも根拠とする。職業の自由は経済的自由として位置づけられるが、そればかりでなく、「人格的価値」としての意味をも有することに注意しなければならない(判例においても、薬事法事件最高裁判所判決が、職業の自由における人格権的性格に着目する)。
職業を決定する自由には、開業の自由、継続の自由、廃業の自由が含まれる。また、公務に就くことも、職業決定の自由に含まれる。なお、外国人については、合理的な理由が存在する限りにおいて制約することが可能であるとされており、現在、弁理士、公証人などについて禁止されている。
また、職業活動の自由に関連して、営業の自由が説かれている。しかし、営業の自由は、論者によって内容を異にする傾向が見られ、内容も複雑になるので、ここでは解説を省略する 。
(1)職業の自由の限界
憲法第22条第1項により、明文において「公共の福祉」による制約が認められている。その内容は、財政上の理由によるもの(例、酒類製造・販売の免許制)、事業の公共性を理由とするもの(例、電気、ガス、交通、郵便)、警察的規制(例、旅館、風俗営業、古物商、食品販売業)、一定の資格を要求するもの(例、医師、弁護士、公認会計士、建築士)、経済の健全な発展を目的とするもの(例、大規模小売店舗に対する規制)があり、形式としては、届出制、登録制、許可制、特許制がある。
職業の自由を制約する立法に関する審査基準は、いかなるものであろうか。最高裁判所判例をはじめとして、多くの説が、経済的自由権に対する規制を積極的目的による規制(政策的規制ともいう)と消極的目的による規制(警察的規制ともいう)とに分類し、積極的目的による規制については合理性の基準を、消極的目的による規制については厳格な合理性の基準を用いる。
消極的目的による規制とは、国民の生命、健康、公安、風俗、公衆衛生、安全などを保護するための規制を指す。これについては、職業の自由の内在的限界を超えるか否かが問題とされる。この問題をクリアすると、次に、その目的達成のための手段との関連において判断される。具体的には、導入されようとしている(あるいは、された)規制がなければ目的を達成できず、あるいは著しく困難であるという程度の客観的な合理性(必要性)が問われる。
●最大判昭和35年1月27日刑集14巻1号33頁
無資格者が業として医業類似行為(この事件の場合は、あんま、はり、きゅう、柔道整復)を行うことを禁止するあん摩師等法第12条の規定を合憲とした。しかし、理由は「公共の福祉」があげられる程度で、それほど説得性はない。
消極的目的による規制については、次の判決が最も重要である。
●薬事法事件最高裁判所判決(最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁)
原告は、広島県内で薬局を開設するため、県知事に営業許可の申請をした。しかし、県知事は、薬局解説の距離制限を規定する薬事法第6条第2項(および第4項)および広島県薬局等の配置基準を定める条例第3条(いずれも当時)の基準に適合しないとして不許可処分をした。原告は、これらの規定が憲法第22条第1項に違反すると主張して、不許可処分の取消しを求めて出訴した。広島地判昭和42年4月17日行裁例集18巻4号501頁は、憲法判断を避けたものの、不許可処分を取り消した。これに対し、広島高判昭和43年7月30日判時531号17頁は、これらの規定が憲法に違反しないと判断した。原告が上告した。
最高裁判所は、これらの規定を違憲無効と判断している。
理由として、まず、「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由自体に制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定するためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、(中略)自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成できないと認められることを要する」という前提があげられ、薬局の「適正配置規制は、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的のための規制措置であり」、「これらの目的のために必要かつ合理的であり、薬局等の業務執行に対する規制によるだけでは右の目的を達することができない」か否かが問題であり、「薬局の偏在」や「一部薬局等の経営の不安」という事由は、規制のために必要かつ合理的とは言えない、と述べている。
これまでは、消極的目的による規制について述べたので、次は、積極的目的による規制について述べておく。
積極的目的による規制とは、福祉国家的理念から導かれるものであり、私的自治の原則や契約自由の原則が社会的正義をもたらさないことに鑑み、構造的弱者を保護することを目的とする規制である。このため、取引の一方当事者を保護し、他方に対して規制を加えることになる。この場合は、規制について、原則として合憲の推定が働くことになる。すなわち、立法府の裁量を尊重することになる訳である。従って、その裁量に逸脱または濫用が見られ、規制が著しく不合理である場合に、はじめて違憲と判断されることになる。
小売市場距離制限事件最高裁判所判決(最大判昭和47年11月22日刑集26巻9号586頁)は、小売市場の開設を許可する条件として適正配置、すなわち距離制限を要求する小売商業調整特別措置法第3条第1項を合憲と判断した。理由として、経済的基盤の弱い小売商による事業活動の機会を適正に確保することが必要であり、その一つとして、小売市場の乱設に伴う小売商相互間の過当競争による共倒れから小売商を保護するという目的があげられている。
〔他に、製造たばこ販売業の許可制と適正配置規制(たばこ事業法第22条・第23条第3号による)を合憲と判断した最判平成5年6月25日判時1475号59頁などがある。〕
消極的目的と積極的目的との区別については、近年、批判がある。その趣旨は、規制目的のみで全てを判断することは不可能ではないか、両者の区別は不可能ではないか、あるいは全く不可能ではないとしても両者の区別は相対的であり、できない場合もあるのではないか、消極的目的の規制について、より厳格な審査を必要とする理由が不明確ではないか、というものである。
私も、このような批判を正当と考える。
まず、消極的目的と積極的目的との区別自体、常に貫徹しうるものではない。或る規制が両者のいずれにも妥当する場合、いずれにも妥当しない場合が存在する。そして、仮に消極的目的と積極的目的との区別をなしうるとしても、規制の意味は時代によって変わりうる。また、規制の性質が変わらなくとも、もはや時代に合わないということもある。法律を解釈する際、立法者の意思に基づくことは誤りではないが、法律自体は立法者の意思から離れて存在しうる(法律意思説)。そればかりでなく、解釈者によって、規制の意味が異なることもありうる。
消極的規制および積極的規制の双方に該当するもの、または規制の意味が時代によって変わりうるものの代表例として、公衆浴場の距離制限がある。
●最大判昭和30年1月26日刑集9巻1号89頁
被告人は、昭和27年、福岡県知事の許可を受けずに公衆浴場を開業した。そのため、公衆浴場法第2条第1項違反に問われ、福岡地吉井支判昭和28年6月1日刑集9巻1号104頁および福岡高判昭和28年9月29日高刑特26号36頁によって罰金刑を受けた。そこで、被告人は、公衆浴場法第2条第1項および福岡県条例に定められた公衆浴場設置の距離制限規定が憲法第22条および第94条に違反するとして上告した。
最高裁判所は、これらの規定を合憲と判断した。その理由として、距離制限が公衆浴場の偏在や濫立を防ぐためのものであること、そして公衆衛生の確保のためでもあることがあげられている。
判決は、国民保健や環境衛生の保持という点を強調する。しかし、公衆衛生の確保という点に着目すれば消極的規制と考えられるのであるが、公衆浴場の偏在や濫立を防ぐという点は、積極的規制を正当化する根拠ともなりうる。そのため、距離制限を消極的目的による規制と考えるには根拠が薄弱であると言われており、行政法の学説などからは積極的目的による規制と捉える見解も現れていた。また、消極的目的と積極的目的との相対性などを指摘する見解もある〈芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法』〔第五版〕(2011年、岩波書店)220頁。なお、長尾一紘『日本国憲法』〔第3版〕(1997年、世界思想社)263頁を参照〉。
●最判平成元年1月20日刑集43巻1号1頁
やはり公衆浴場の距離制限に関する判決である。この判決においては、積極的目的による規制と理解されている。
●最三小判平成元年3月7日判時1308号111頁
これも公衆浴場の距離制限に関する判決である。この判決においては、消極的目的による規制と積極的目的による規制の双方と考えられている。
次に、消極的規制および積極的規制のいずれにも該当しないと考えられるものとして、酒類製造および販売の免許制がある。酒税法第10条第10号の事由に該当するとして酒類販売業の免許申請に対して行われた拒否処分の是非が争われた最三小判平成4年12月15日民集46巻9号2829頁がある。酒類製造および販売の免許制は、昭和13年の酒税法改正によって導入されたものであり、当時は酒税徴収の確保を目的としていた。判決においても、この点が理由の根幹をなしている(酒税は、国税収入全体から見れば相対的に割合を落としているが、重要性は失われていない)。また、酒税は消費者に負担が転嫁されるべき間接税の一種であること、酒類が販売秩序維持のために販売を規制されてもやむをえないことも述べられている。
また、規制目的が正当であるとしても、それだけで規制を正当なものとしないことは当然である。
さらに、私は、積極的目的に関して、単純に合憲性を推定することに疑問を抱いている。このような態度を採れば、様々な理由をつけることにより、全ての規制が合憲となってしまうであろう。政策的な理由によるとされる規制こそ、必要性および合理性が厳しく審査されるべきであろう。このような理由によるとされる規制が、官民癒着、不透明な行政などの悪弊を生み出す原因の一つでもある。
3.居住・移転の自由(憲法第22条第1項)
日本国憲法第22条第1項においては、居住・移転の自由も保障される。これは、経済的自由権としての意味を有するのであるが、それはむしろ歴史的な経緯によるものである(封建時代において、居住・移転に対する制約は職業選択への制約に結びついていた)。しかし、居住・移転の自由は、個人の人格発展の自由でもあり、その意味において その意味において精神的自由と捉えられるべきものであるとともに、人身の自由でもある。現在は、この意味のほうが重要である。従って、居住・移転の自由に対し、政策的理由による制限を簡単に許容するものではない。「公共の福祉」という制約原理は、少なくとも国内における居住・移転の自由に対する制約の原理とはなりえない。
この自由は、住所(または居所。国内・国外を問わない)を決定または変更する自由であり、「何人」に対しても保障される。また、第22条第2項において外国への移住の自由が定められている。
出入国管理及び難民認定法(旧出入国管理令)、旅券法の合憲性については、以前から争いのあるところである。
●帆足計事件最高裁判所判決(最大判昭和33年9月10日民集12巻13号1969頁)
前参議院議員(当時)の帆足計氏が、モスクワで開催される国際経済会議への出席を招請されたため、外務大臣に旅券発給を申請した。しかし、外務大臣は、旅券法第13条第1項第5号によって拒否処分をした。そこで、帆足氏は損害賠償請求訴訟を提起したが、東京地判昭和28年7月15日下民集4巻7号1000頁、東京高判昭和29年9月15日下民集5巻9号1517頁は、ともに請求を棄却した。帆足氏は上告したが、最高裁判所大法廷は上告を棄却した。
判決理由において、憲法第22条第2項にいう「外国に移住する自由」に外国へ一時的な旅行をする自由も含まれるとされており、その上で、外国へ一時的な旅行をする自由も「公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきである」とされた。そして、旅券法第13条第1項第5号はこの種の制限を規定したものであり、「漠然たる基準を示す無効のものであるということはできない」と述べられている。
この判決には、田中裁判官および下飯坂裁判官による補足意見が付せられている。それによると、憲法第22条は旅行の自由を保障しているとは言えず、この自由は「一般的な自由または幸福追求の権利の一部分をなしている」。
まず、この判決については、外国へ一時的な旅行をする自由は精神的自由の一つでもあることを指摘しうる。そのため、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」に対して旅券の発給を拒否できるとする規定は、不明確なものであり、憲法違反の疑いも濃いと思われる。
次に、外国への一時的な旅行の自由について、検討を加えておく。
第一説は、第22条第2項を根拠とする。前掲最大判昭和33年9月10日の多数意見の他、最三小判昭和60年1月22日民集39巻1号1頁の多数意見がこの立場を採っており、学説にも支持が多い(通説であろう)。この説は、第22条第1項を国内に関連する規定、第2項を外国に関連する規定と捉えた上で、永住のための出国が保障されるのに旅行のための出国を認めないというのは不合理であると述べる。
第二説は、第22条第1項を根拠とする。最二小判昭和44年7月11日民集23巻8号1470頁の色川裁判官補足意見、前掲最三小判昭和60年1月22日の伊藤裁判官補足意見の他、有力な学説が採用する。この説は、第1項の「移転の自由」を、居住所の変更のみならず、旅行の自由を含めて解釈する。そして、旅行を第2項の「移住」に含めることには無理があるし、移住は日本国の支配を脱することを意味することになると考える。
第三説は、第13条を根拠とする。前掲最大判昭和33年9月10日の田中裁判官および下飯坂裁判官の補足意見がこの立場を採る。この説は、旅行について「移転」とも「移住」とも異なると考える。
まず、第三説については、文言解釈に最も忠実であるという点において評価しうるものの、妥当とは言い難い。この考え方によると、まず、国内旅行の自由の根拠をどの条文に求めるのかが問題となるであろう。仮に、根拠を第13条に求めるとすると、第22条第1項の「移転」は転居のみを意味することになるが、「居住」と「転居」を第22条第1項の問題とし、旅行を第13条の問題とすることは、バランスを欠いた解釈であると言わざるをえなくなる。また、国内旅行の自由の根拠を第22条第1項に求めるとすると、外国旅行の自由だけが第13条に根拠を求めるべきことになり、これもバランスを欠くこととなる。
次に、第一説と第二説については、どちらが妥当であるか、にわかに判断し難い。一時的な外国旅行は、日本から外国に住所を移すことを意味しないから、「移住」に含めることには無理が伴う。しかし、それでは「移転」に含めうるのであろうか。これもかなり苦しいのではないか。他方、第一説が指摘するように、永住であれ旅行であれ、出国をしなければ話が始まらない。また、或る国民が外国に永住すると言っても、帰国の可能性が全く存在しないという訳ではない。そのように考えると、永住のための出国が自由であるのに旅行のための出国については一切自由が認められないというのも不合理である。ここでは、第一説を妥当としておきたい。