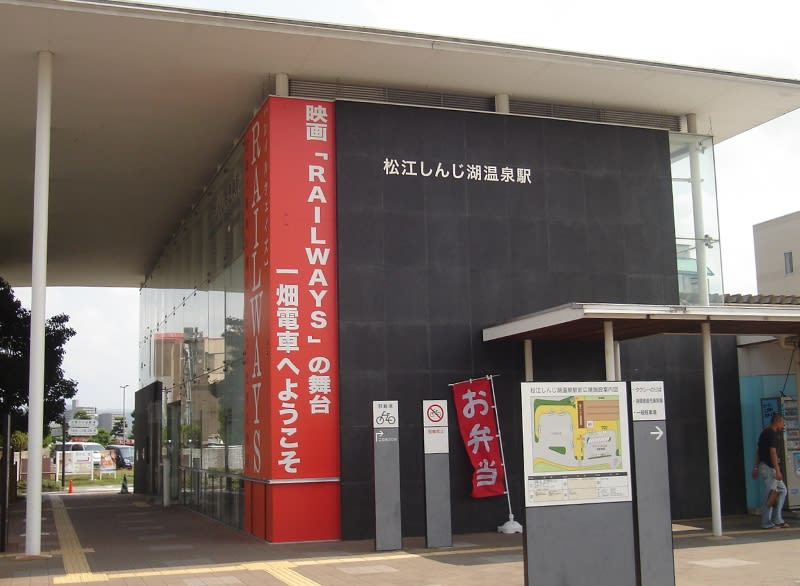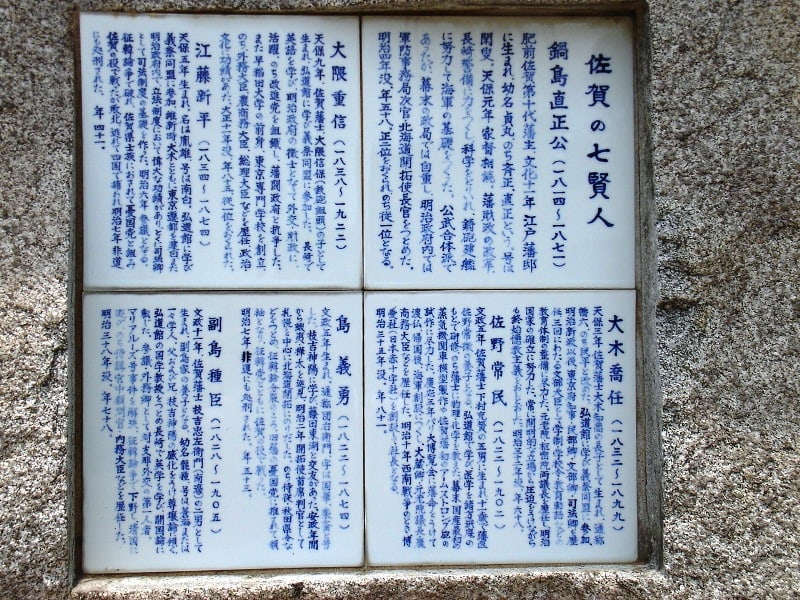先々週から中日新聞などで報じられていましたが、取り上げるのが遅くなりました。
近鉄内部線・八王子線について、近鉄のBRT化の意思は変わらず、四日市市議会でもその意思が表明されました。四日市市は、今後、どのように対応するのでしょうか。
まず、読売新聞社の4月19日付記事(おそらく三重版)「近鉄内部八王子線 存続策8月末までに」(http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/mie/news/20130419-OYT8T00135.htm)によると、18日に四日市市議会総合交通製作調査特別委員会が開かれ、そこで近鉄の鉄道事業本部の担当者が参考人として出席した上で、次のように述べました(要点)。
(1)内部線・八王子線を鉄道として残すなら、今年8月末までに交渉の結論を出さなければならない。
(2)鉄道として存続させるならば、公有民営方式しかない。
(3)内部線・八王子線は、鉄道として残すのではなく、BRT化し、バス路線とするのが最善である。
このうち、(1)の理由は、車両にあるようです。現在、内部線・八王子線では14両の車両があるそうですが、このうちの1両が2015年8月28日に予定されている定期検査の際に廃車となる、ということが理由としてあげられています。「予備車がないのか?」とも思うのですが、市議会で突っ込まれたりしなかったのでしょうか。仮に新しい車両を製造するとなれば、設計から完成まで2年くらいかかるということも述べられています。このように主張されているということは、近鉄の廃線の意思が固いということです。近鉄自身が特殊狭軌線と言っているように、内部線・八王子線の場合はどこかから中古の車両を購入するという訳にいきませんし、存続を前提としているならば、既に新型車両の設計などに取り掛かっているはずです(少なくとも、わざわざ定期検査と廃車の話など出さないでしょう)。
次に(2)ですが、この公有民営方式を採用するのであれば安泰かというと、そうではありません。まず、四日市市(場合によっては三重県も)の財政負担が大きくなります。鉄道施設を四日市市が保有するのですから、固定資産税などの収入もなくなります。
しかも、近鉄の主張によると、近鉄自身が有償で借り受けるということにならないのです。まずは別会社を作り(これも具体的にどのような形態になるのかは不明です)、その会社が無償で四日市市から施設の貸与を受け、しかも補助金が四日市市からその会社に支払われます。人によっては「随分と虫がいい話じゃないか?」と思われることでしょう。さらに、ここまでしても1年間で1億円を超える赤字が見込まれるというのです。「何のために残すのかわからない」という話にまでなります。これなら、いっそうのこと、富山県の万葉線のような形態とし、四日市市が中心となって第三セクターを作るほうがよいでしょう。一民間企業のために公有財産を無償で貸与し、その上に赤字を補助金で補うというのは、多くの人の納得を得られるのか、疑問とせざるをえないからです。
こうなると、近鉄も主張するようにBRT化するほうがよいということになります。ただ、BRT化するとしても、土地などの施設は必要です。これをどこが保有するのでしょうか。おそらく四日市市か三重県か、ということになるでしょう。ただ、車両などの保有まで市や県が行う必要もありませんので、運賃収入がさしあたっての問題ということになるでしょうか。
4月24日には、朝日新聞社が「公有民営も選択肢」(三重版)として報じています(http://www.asahi.com/area/mie/articles/MTW1304242500002.html)。それによれば、四日市市長が記者会見(23日)で公有民営方式の案に難色を示したようですし、翌日の中日新聞社の「近鉄2線公有民営に疑問の声 四日市市議会」という報道(http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20130425/CK2013042502000006.html)によれば、24日に開催された四日市市議会総合交通政策調査特別委員会において近鉄の方針に対して多くの疑問が出されたようです。今後、四日市市がアンケートなり住民投票なりを行わざるをえない事態となるかもしれません。
四日市市は、現在のところ、近鉄内部線・八王子線を鉄道路線として存続させる方向をとることを表明しています。しかし、近鉄の路線として存続することが難しく、かつ、四日市市がBRT化に低い順位しか与えていないことからすると、(鉄道として残すのであれば)富山県の例、まずは先にあげた万葉線、および、JR西日本から移管されてLRT化された富山港線(富山ライトレール)の例にならうくらいしか手がないと思われます。勿論、その際には完全に近鉄の手から離すしかありません。基本的には近鉄の資本参加を要請しない、ということになるでしょう。第三セクターという形式に問題があることは承知していますが、現実の問題として純粋な民営私鉄の形をとることはできないでしょう。
ちなみに、同じく近鉄の路線であった北勢線が三岐鉄道の路線となって10年が経ちます。これについては中日新聞社の4月22日付の記事(三重版)「【三重】自治体支援も厳しい経営 三岐鉄道北勢線10周年」(http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20130422/CK2013042202000020.html?ref=lcrk)に興味深い内容が記されています。三岐鉄道にとって、北勢線の受け入れにメリットなどなかったはずで、実際にその通りだったのですが、三岐鉄道の路線になってから乗客も増え、およそ7億円もあったという赤字の額も半分ほどにまで減ったそうです。しかし、経営状態が苦しいことに変わりはなく、三岐線の乗客も減少していることからすると、今後、また問題がぶり返される可能性もあります。
過去の記事をあげておきます。
「近鉄内部線・八王子線が廃止される可能性」(2012年8月22日付)
「別に目新しくも何ともないBRT(バス高速輸送システム)」(2012年8月25日付)
「近鉄内部線・八王子線に乗ってみました」(2012年11月1日付)
「存廃問題に揺れる近鉄内部線・八王子線に乗る(その1)」(2013年1月7日付)
「存廃問題に揺れる近鉄内部線・八王子線に乗る(その2)」(2013年1月8日付)
「存廃問題に揺れる近鉄内部線・八王子線に乗る(その3)」(2013年1月9日付)
「近鉄内部線・八王子線の存廃問題について住民アンケートが行われるようです」(2013年2月28日付)