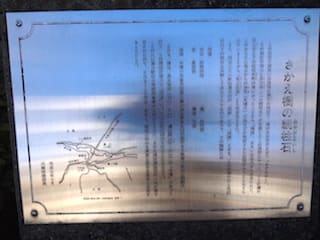栄橋交差点から溝の口駅に行くには、素直に南武沿線道路を通るのが最もわかりやすいのですが、今も昭和の面影を残す西口商店街を歩いてみます。溝口二丁目です。

光線の加減を見誤りましたが、こちらが栄橋交差点から最も近い入口となります。旧大山街道踏切のそばにも入口があり、商店街はYの変形のようなものになっています。
戦後の闇市がそのままアーケード商店街になったような構造で、高津区では唯一の、そして川崎市でも数少ないアーケード商店街です。ただ、私が市内のアーケード商店街として知る新城駅南口と川崎駅東口は、いずれも本式のアーケード商店街ですので、ここ西口商店街とは全く趣が異なります。

こちらには商店街であることを示す看板の類がありません。飲食店の多い所ではありますが、再開発以前と以後とではかなり姿を変えているように思えます。

さすがに正月三箇日の午前中では人通りも少なく、多くの店が閉まっています。ここはやはり、平日の夕方以降に歩くのが最も面白いのです。大学院生時代にはよく歩いていましたが、まだここで飲んだことがないので、一度は飲んでみたいところです。最近は女性の客も多く、時の流れを感じさせてくれます。
左側には、今、溝の口駅周辺にある書店(古書店を除く)では唯一、文教堂でない書店があります。しかし、ここでは右側のほうに注目したいところです。

少し進み、注目したいところを遠目に撮影しました。一見するとただの店です。しかし、ここは、昼は八百屋、夕方から焼き鳥屋なのです。まるで性格の異なる商売を一つの店がやっている訳で、私は溝口以外にこのような例を知りません。焼き鳥屋として営業をしているところを何度も見ていますが、立ち飲み屋と考えていただいてよいでしょう。
ちなみに、左側の壁の向こうは南武線です。

左側に進むと旧大山街道踏切、右側に進むと栄橋交差点です。ここでは屋根に御注目下さい。川崎市で、このような商店街は他にあるのでしょうか。

古本屋の明誠書房は、もう営業していました。ここにも時々寄ります。古書店ですが、所々におもちゃが置かれており、何故か記念切符などもたくさん置かれたり貼られたりしています。ちなみに、南武線の上り電車に乗ると次である武蔵新城駅の南口にも支店があります。
溝の口駅周辺には、現在も何軒かの古書店があります。いずれもメインの商店街にないのですが、昔ながらの、味のある店ばかりですので、まわってみるのも面白いでしょう。

アーケードを抜け、田園都市線溝の口駅の近くに出ました。再開発事業完成以前には、アーケードがさらに先まで伸びており、右側にはクリーニング店と菓子屋を兼ねた店がありました(現在は奥のほうへ移転しています)。少し手前のほうには帽子屋もあったはずです。

溝口が大きく変わったのは1990年代後半、ノクティの営業開始などによる再開発事業竣工後です。それまで、西口商店街は、田園都市線のガード下付近、亀屋呉服店の辺りまで伸びていました。再開発により、西口商店街は短くなった上に店舗も少なくなりました。
ここから奥のほうへはあまり歩いたことがない私は、どのような店があったのかを覚えていません。ただ、カレーハウスデリーがあることは知っています。1980年代には駅の反対側にあったのですが、いつの間にか西口に移転していました。今ではほとんど見かけなくなった魚屋もありました。
また、右側にハセガワという洋食屋がありました。大衆食堂のようなものですが、安い上に美味く、しかも店主がニュースを見ては突然客に話しかけてきたりするという店でした。
しかし、2007年2月、放火による火災が起こります。この事件について触れているサイトやブログも多いようで、写真も掲載されていますが、季節と建物の構造により、甚大な被害となりました。これにより、ハセガワなどが閉店してしまいます。昭和の光景が多く失われた訳です。
もっとも、川崎市としては、火災に遭ったからと言って再建を認める訳にもいかなかったようです。理由は、この西口商店街の一部(よくわからないので、一部としておきます)が川崎市の市有地(など)を不法占拠するような形となっていたからです(戦後の闇市から始まったのですから)。市は立ち退きを要請するしかなかったのでしょう。古い建物が残っているのも、同じ理由によるもののようです。

火災はこの辺りまで広がりました。そのためか、屋根型アーケードも津久波商店の奥のほうにしか残っていません。手前左側、自転車が置かれている場所にも何軒かの店舗があったのですが、移転したり廃業したりしています。

田園都市線溝の口駅の西口です。いつからこのような構造になったのか、私もよく覚えていません。私が大学院生としてこの駅を利用していた頃には、西口がなかったと記憶しています。改札口は地上1階にあり、南武線の武蔵溝ノ口駅側を向いていました。改札口が2階に移ってから、西口ができたのです。いや、復活した、と記すべきかもしれません。
今回は西口商店街を取り上げました。この名称は、1966年の高架化より前、地上駅であった頃の構造に由来するのでしょう。宮田道一『東急の駅 今昔・昭和の面影』(2008年、JTBパブリッシング)165頁には、1961年11月5日の写真(荻原二郎氏撮影)が掲載されています(当時は「溝ノ口」と表記されていました)。それを見ると、駅を経由して西口から武蔵溝ノ口駅まで通り抜けられるような構造になっています。
高架化以降、溝の口駅には西口がなく、中央口と南口だけがありました。また、おそらくは再開発事業竣工時まで、武蔵溝ノ口駅には南口がなく、現在の北口だけしかなかったのです。すぐ前が狭いバスターミナルで、何故か駅前公衆便所のそばに屋台のラーメン屋が出ていたことを覚えています。
現在の溝の口駅の1階には24時間営業の東急ストアが入っています。私が小学生であった1970年代には、長崎屋(現在のドン・キホーテ)の地下1階(楽園というパチンコ屋が入っています)に東急ストアがあったのですが、いつの間にか駅の構内に移転しました。長崎屋と東急ストアが同居していたのも不思議な話ですが、理由はよくわかりません。
また、文教堂書店の本店が駅構内にあった時代もあります。考えてみると、文教堂書店本店は何度も移転しており、1970年代後半には溝口中央商店街とポレポレ通りとの交差点のそばにあるフジモトビルの1階にありました(ちなみに、現在も4階にカワイ音楽教室があります)。1980年代に、溝の口駅構内に移転したのですが、1990年代には再び溝口中央商店街とポレポレ通りとの交差点のそばに移転しました。但し、今度はマルエツ溝ノ口店のB館、現在のQiz溝の口です。ノクティがオープンした頃に、現在の本店ができたと記憶しています。
あれこれと思い出したりしましたが、ここから駅の中に入って用事を済ませ、ペデストリアンデッキを利用してノクティに入ることとしましょう。