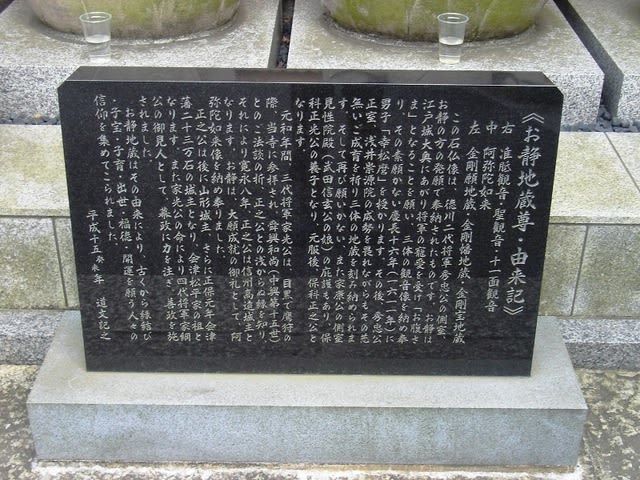1.法治主義(Rechtsstaatsprinzip)と法律による行政の原理(Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung)
今回の題目に掲げられている「法律による行政の原理」(法治行政の原理ともいう)は、ドイツ公法学、とくにオットー・マイヤー(Otto Mayer. 1846-1924)によって確立された法治主義理論に由来するものである。そこで、まず、法治主義の内容をみることとしよう。
法治主義は、法治国家ともいうことがある。ドイツ語ではRechtsstaatという。この言葉自体に、法治主義の本来の意味が隠れている。Rechtは、法を意味すると同時に権利をも意味し〈最近では「主観的権利」という言葉が氾濫しているが、権利そのものが主観的なものであるし、客観的権利というものは想定されていないから、誤訳、もっと言えば悪訳である〉、正義をも意味する。権利という場合にはSubjektives Recht、法という場合にはObjektives Rechtと区別することもある〈権利が主観的な正義であるとするならば、法は客観的な正義ということになるのであろう〉。また、Staatは国家を意味する。このことから、Rechtsstaatは、やろうと思えば権利国家とも訳せるのである。
日本国憲法の下における法治主義は、基本的に二つの内容を前提としている。
第一に、公権力によって国民の権利・自由を制約する場合には、必ず、立法府たる国会(議会)の制定した法律の根拠が必要である。
第二に、法律の根拠があるからといって国民の権利・自由をどのように制約してもよいという訳ではない。立法府(国民の代表からなる)による法律であっても制約できない権利・自由が存在する。すなわち、基本的人権が尊重されなければならないのである。
このうち、本来の法治主義の内容は第一のものであるが、これはイギリス法の「法の支配」(Rule of Law)と土台を同じくする。しかし、法の支配と異なる点は、法治主義の場合、立法作用などが行われるための手続を示すものであり、形式的な概念であるということである。法の支配の場合は、元々が王権に対する封建貴族の権利を擁護するためのものであったが、それが一般的に発展し、国民(とくに市民階級)が立法過程に関与し、自らの権利や自由を可能な限り防衛しようとすることに資する原理である。これに対し、法治主義の場合は、ドイツにおいて市民階級の発達が十分でなかったという社会的背景が存在したため、法の支配にみられるような契機は皆無でなかったものの、弱かったのである。また、法の支配の場合は、市民階級の権利や自由の防衛という目的のために法の実質的内容と合理性を問うものであったのに対し、法治主義の場合は、法の実質的内容と合理性はそれほど強く問われなかったのである〈もっとも、法規(Rechtssatz)の概念には注意しなければならない。「行政法学(など)にいう『法規』の意味」において説明したので、参照されたい〉。
しかし、第一の内容のみでは、結局、法律さえあれば如何様にも権利や自由を制約しうるということになる。これでは国家による不法な行為を防ぐことが十分にできなくなる。そこで、第二次世界大戦後のドイツ公法学においては、法治主義に第二の内容が加わり、憲法裁判所制度の設置および発達によって法治主義の概念が豊かなものになっている。これを日本において高く評価するのが長尾一紘教授であり、現在のドイツ公法学における法治主義の内容を「①権力分立原則、②憲法の優位、③基本権の保障、④法律適合性の原則、⑤法的安全性の原則、⑥比例の原則、⑦裁判による権利保護」とまとめている〈長尾一紘『日本国憲法』〔第3版〕(1997年、世界思想社)25頁〉。いずれも、行政法との関連において重要なものである。
以上のような法治主義を行政法に当てはめる際に、法律による行政の原理が導き出されることとなる。オットー・マイヤー以来、この原理は次の三点を主な内容とするものである。
第一に、前述の狭義の法規を作りうるのは法律のみであるという原則を生み出す。これは「法律の法規創造力の原則」とも言われる。ここでは法治主義の元来の内容がそのまま導入され、国民の権利や自由を直接的に制限し、あるいは国民に義務を課する法規範(法規)は、国民の代表機関である議会によって定立される法律によらなければならないとされる。日本国憲法第41条における立法とはこの意味であり、行政機関が単独で実質的な意味における立法の権限を行使することは許されないのである。
もっとも、実際には例外もある。行政立法がそれに該当するが、この場合であっても、日本国憲法においては、法律の委任なくして法規を定めることはできないとされている。詳細は「第6回 行政立法その1:行政立法の定義、法規命令」において扱う。
第二に、行政の様々な活動が法律に反してはならないという原則を生む。これは「法律の優位の原則」(Der Grundsatz des Vorrangs des Gesetzes)とも言われる。従って、行政決定や行政慣例が法律の内容と矛盾する場合には、その範囲において行政決定や行政慣例が違法となる。なお、憲法に違反してはならないことは当然のことである。
第三に、行政が何らかの活動を行う際に、その活動を行う権限が法律によって行政機関に授権されていなければならない(すなわち、与えられていなければならない)という原則を生む。これは「法律の留保の原則」(Der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes)と言われている。第一の内容から導き出されるものであり、少なくとも、国民の権利や自由を制約し、または新たな義務を課するような活動を、法律の根拠なくして行政権が単独でなすことは許されないということになる。
2.法治主義の射程距離―侵害留保説、全部留保説など―
但し、法律の留保の原則については、適用される範囲という問題がある。
まず、既に述べたように、少なくとも国民の権利や自由を制約し、または新たな義務を課する行政活動については、法律の根拠を必要とする。この考え方については一致がみられる。自由主義を前提とする限り、当然のことである。
問題は、その他の行政活動にも法律の根拠が必要であるのかということである。上述の考え方に留まる考え方が侵害留保説であり、日本国憲法の下においても支持されてきた。通説であり、判例も、この考え方を前提としているものと思われる。ちなみに、侵害留保説を採りつつも、法律の根拠を必要とする範囲を拡大することは可能であるし、望ましい。
しかし、民主主義の原則は、国民主権を前提とするから、行政権の発動も国民の意思に従うべきである、という考え方も、当然成り立ちうる。そこで、(少なくとも国民に対する)全ての行政活動に法律の根拠を必要とするという考え方がある。これを全部留保説という。しかし、この考え方に対しては、現実的でない、行政が硬直化して臨機応変に需要の変化に対応できないなどの問題がある。
侵害留保説と全部留保説との間に、様々な説が展開されている。そのうちの代表的なもののみを取り上げておく。
まず、権力留保説は、侵害留保説を拡張し、行政がおよそ権力的な行為形式によって活動をなす際には法律の根拠を必要とするという考え方である。国民に権利を与えたり義務を免ずるものであっても、法律の根拠が必要とされることになる。
次に、社会留保説がある。これは福祉国家理念から発生したもので、国民の社会権を確保するために行われる生活配慮行政についても法律の根拠を必要とするという考え方である。給付行政にも法律の根拠が必要であるということになる。
また、ドイツにおいて「本質性理論」(Wesentlichkeitstheorie. 以下、本質留保説とする)が有力になり、連邦行政裁判所の判例において形成・採用された。この内容は必ずしも明確でないが、基本権(基本的人権)に関する憲法上の条項を基準として、「基本権実現にとって本質的」である領域については、必ず法律の根拠を必要とする、ということである。問題は、本質的か本質的でないかの判断に関する基準であろう。
本質留保説に関する日本語の文献として、大橋洋一『行政規則の法理と実態』(1989年、有斐閣)93頁、同「法律の留保学説の現代的課題―本質性理論(Wesentlichkeitstheorie)を中心として―」『現代行政の行為形式論』(1993年、弘文堂)1頁が参考になる。
現在のところ、この他にも様々な説があるが、なお侵害留保説の妥当性が大きい。
なお、以上は行政作用法の根拠に関する議論である。行政組織法の根拠は全行政領域に要求される。また、権力的手段に関しては行政作用法・行政組織法・行政手続法の根拠を必要とするのであり、非権力的手段に関しては行政組織法・行政手続法の根拠を必要とすると考えるべきであろう。
行政手続法の根拠については、以前ならば不要と考えられていた。新井隆一編『行政法』(1992年、青林書院)20頁。
3.法律による行政の原理、とくに「法律の留保」との関係が問題になる事例
日本において、行政活動は法律による行政の原理に服すべきであり、少なくとも侵害留保説が妥当すべきである。しかし、実際には法律の留保の要請を充たしていないのではないかと考えられる事例が存在する。ここで若干の裁判例を概観する。
〔1〕自動車の一斉検問
交通取締の一環として行われる自動車の一斉検問であるが、実のところ、そもそも、法的根拠は何かという問題がある。
判例は警察法第2条第1項説に立つ。行政実務も同じであり、学説においても多数説ではないかと思われる。しかし、警察法は行政作用法ではなく、行政組織法に属する。しかも、同第2条第1項は「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする」と定めている。「交通の取締」が明示されているからであろうが、このような規定が自動車の一斉検問の法的根拠になりうるのであれば、犯罪の捜査についても法的根拠となりうるから、刑事訴訟法の第2編第1章にある規定の一部が不要になるはずである。しかし、そのような説を述べる者は存在しない。警察法第2条第1項説は論旨が一貫せず、妥当性を欠く。
判例の立場を採りえず、しかも行政作用法に根拠を求めるとすれば、警察官職務執行法第2条説が浮かび上がる。かつて、私はこの説を採っていた。しかし、同条は職務質問、すなわち特定の者に対する質問に関する規定であるから、犯罪の嫌疑の有無を問わない一斉検問を文言解釈によって導きうるはずもなく、類推解釈の許容範囲を超えていることも否定できない。そうなると残るのは、法的根拠がないので違法であるとする説である。
●最三小決昭和55年9月22日刑集34巻5号272頁(Ⅰ―107)
事案:警察官が、飲酒運転の多発地帯である場所で交通違反取締りを目的とする自動車検問を行った。X運転の車は、外観からは不審な点が存在しなかったが、警察官の合図に従い停車した。警察官はXに運転免許証の提示を求めた際、酒の臭いを感じたので降車を求め、派出所で飲酒検知を行ったところ、酒気帯び運転の事実が確認された。Xは自動車検問が何の法的根拠もなく行われたなどとして争ったが、一審判決(宮崎地判昭和53年3月17日判時903号107頁)および二審判決(福岡高宮崎支判昭和53年9月12日判時928号127頁)は、自動車検問の法的根拠を警察法第2条第1項とした上でXの主張を退けた。最高裁第三小法廷も、次のように述べてXの上告を棄却した。
判旨:「警察法2条1項が『交通の取締』を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといつて無制限に許されるべきものでないことも同条二項及び警察官職務執行法一条などの趣旨にかんがみ明らかである。しかしながら、自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、その他現時における交通違反、交通事故の状況などをも考慮すると、警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである」。
〔2〕緊急措置と法律による行政の原理との関係
既に述べたように、法律による行政の原理は、最低限度として、国民の権利や自由を制約し、または新たな義務を課する行政活動について妥当すべきものである。しかし、現実には、目前に公共の安全や秩序に対する危害が存在し、これに緊急に対処しなければならない場合が存在する。このような事態が発生しているのに、対処方法を規定する法律の規定が存在しないならば、行政は何らの予防策などをとることもできず、危害を放置して安全や秩序が崩れるまで待たなければならないのであろうか。これでは、行政が国民の安全を確保することができず、ひいては生命、身体、財産などを保護することができないということになる。緊急措置として、例外的ではあれ、法律の根拠がなくとも何らかの措置をとることができると考えなければならない場合があるのではなかろうか。
●最二小判平成3年3月8日民集45巻3号164頁(Ⅰ-101)
事案:千葉県浦安町(現在は浦安市)を流れる某河川に、河川法および漁港法による占用許可を受けずにヨット係留施設が設置された。そのため、船舶の航行にとって危険な状態が続いた。Y(浦安町長)は千葉県葛南土木事務所長に撤去を要請したが、撤去はなされなかった。そこで、Yは、本来の河川の管理者である千葉県知事の措置を待たず、この施設の鉄杭を独自に撤去することとし、A社と撤去工事請負契約を締結した。某日、浦安町職員とA社従業員が鉄杭の撤去作業を行った。
本来、撤去作業を進めるためには漁港法に基づいて漁港管理規程(条例)が制定されるべきであったが、浦安町は漁港管理規程を制定していなかった。そのため、千葉県知事は河川法に違反する施設の撤去命令を発する権限を有するが、浦安町長はその権限を有していなかった。
この撤去作業のために浦安町長が公金を支出したところ、X(浦安町住民)は、同町の職員に対する時間外勤務命令およびA社と締結した請負契約のいずれも違法であるとして、時間外勤務手当および請負代金につき、Yが浦安長に対して損害賠償を行うよう請求する住民訴訟を提起した。一審判決(千葉地判昭和62年3月25日民集45巻3号180頁)はXの請求を認容した。Yが控訴し、二審判決(東京高判平成元年5月30日民集45巻3号189頁)は、損害賠償の額を減額したものの、Xの請求を認容した(判決としては一部棄却となる)。Yが上告。
判旨:最高裁判所第三小法廷は、次のように述べてY(引用文中では上告人)の主張を認め、Xの請求を棄却した。
①「本件鉄杭は、本件設置場所、その規模等に照らし、浦安漁港の区域内の境川水域の利用を著しく阻害するものと認められ、同法39条1項の規定による設置許可の到底あり得ない、したがってその存置の許されないことの明白なものであるから、同条六項の規定の適用をまつまでもなく、漁港管理者の右管理権限に基づき漁港管理規程によって撤去することができるものと解すべきである」が「当時、浦安町においては漁港管理規程が制定されていなかったのであるから、上告人が浦安漁港の管理者たる同町の町長として本件鉄杭撤去を強行したことは、漁港法の規定に違反しており、これにつき行政代執行法に基づく代執行としての適法性を肯定する余地はない」。
②しかし、「浦安町は、浦安漁港の区域内の水域における障害を除去してその利用を確保し、さらに地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全を保持する(地方自治法2条3項1号参照)という任務を負っているところ、同町の町長として右事務を処理すべき責任を有する上告人は、右のような状況下において、船舶航行の安全を図り、住民の危難を防止するため、その存置の許されないことが明白であって、撤去の強行によってもその財産的価値がほとんど損なわれないものと解される本件鉄杭をその責任において強行的に撤去したものであり、本件鉄杭撤去が強行されなかったとすれば、千葉県知事による除却が同月9日以降になされたとしても、それまでの間に本件鉄杭による航行船舶の事故及びそれによる住民の危難が生じないとは必ずしも保障し難い状況にあったこと、その事故及び危難が生じた場合の不都合、損失を考慮すれば、むしろ上告人の本件鉄杭撤去の強行はやむを得ない適切な措置であったと評価すべきである」。従って、「上告人が浦安町の町長として本件鉄杭撤去を強行したことは、漁港法及び行政代執行法上適法と認めることのできないものであるが、右の緊急の事態に対処するためにとられたやむを得ない措置であり、民法720条の法意に照らしても、浦安町としては、上告人が右撤去に直接要した費用を同町の経費として支出したことを容認すべきものであって、本件請負契約に基づく公金支出については、その違法性を肯認することはでき」ない。
この判決に対する評価は分かれており、法律による行政の原理に対する例外を認容した判決とする評価と、町(長)とヨットクラブ代表者との関係について撤去を適法としたものではないとする評価が存在する。この訴訟の原告はヨットクラブ代表者でなく住民であったため、直接、法律による行政の原理が争われていたと言い難い部分もある。また、ヨット係留施設の存在による危害と撤去措置とが比例関係にあるか否かも問われうるであろう。
その点を承知した上で、一般論として述べるならば、本来、私人の意思に反して私人の財産たる工作物を撤去するには、撤去命令を定めた法律の根拠が必要である。その根拠が欠けているならば、民事執行によらざるをえない。これが原則であることを認めない訳にはいかない。しかし、国民・住民(私人)の生命や身体を保護しなければならないような場合など、緊急を要するような場合にまで、法律の根拠がなければ活動をなしえないのか。緊急措置(緊急避難措置)が必要ではないのか。極めて限定的に解さざるをえないとはいえ、民法第720条に定められた正当防衛および緊急避難のいずれかが、行政法においても適用される余地はあるものと解される。
4.行政法の一般原則(条理)
行政法の一般原則というのであれば、先の法律による行政の原理が例であるが、ここでは、不文法の一種としての条理をあげておく。
条理とは、社会生活において相当多数の人が一般的に承認する道理である。但し、実際には、条理は、裁判官が具体的な事件に即して適切な裁判規準を形成するための手がかりであり、または心構えである。その意味において、慣習法のように、一般的規準として存在するものではない。
なお、少数説ではあるが、条理の法源性を否定する見解もある。
刑事裁判においては罪刑法定主義が支配するため、不文法たる条理が援用されてはならない。これに対し、民事裁判の場合、成文法にも慣習法にも判例法の中にも適切な裁判規準がない場合には、条理に従うものとされる。
〔1〕比例原則
比例原則とは、国民の権利や自由を制約する際に、その制約の程度に見合うように公権力の行使がなされなければならない、という原則である。換言すれば、国民の権利や自由を制約する際には、必要かつ最小限の手段が用いられなければならない、ということである(必要性の原則、過剰禁止の原則)。警察官職務執行法第1条第2項は、この原則を確認した規定であると言われる。「警察は、大砲を使って雀を撃ってはならない」という名言がある〈Fritz Fleiner, Institutionen des Deutschen Verwaltungsrecht, 8. Auflage, 1928, S. 412〉。
〔2〕平等原則
平等原則は、憲法第14条に根拠を求めることができる。法律による行政の原理に適合しているとしても、平等原則に違反する場合には行政活動などが違法となることもありうる〈スコッチライト事件として有名な大阪高判昭和44年9月30日判時606号19頁を参照〉。
〔3〕信義誠実の原則
民法第1条第2項に規定されている信義誠実の原則は、元々、ドイツの債権法に由来する考え方である。これが民法全体の原則に、さらに法の一般原則にもなり、行政法の分野にも妥当するようになった。行政庁(行政機関)の活動の継続に対する私人の信頼を保護するという意味で、信頼保護の原則ということもある。
なお、日本の判例は「禁反言の原則」という、英米法に由来する語も用いる。ほぼ同義であるが、信義誠実の原則のほうが若干広範囲であるといわれる。
しかし、行政法において、信義誠実の原則をそのまま援用すると問題が生ずる場合がある。それは、この原則が法律による行政の原理と抵触し、違法な行政活動を確定的に有効としてしまう場合があるためである。信義誠実の原則は、行政活動によって何らかの損害を受けた私人を救済するための手段であるが、これを無条件かつ安直に用いるとすると、他者にとって不公平な結果を招く危険性もある。従って、具体的な事案への適用の妥当性が問題となる。以下、判例の状況を概観しつつ、検討する。
▲租税法律主義と信義誠実の原則との抵触
憲法第30条および第84条(とくに後者)は、租税法律主義を規定する。これが妥当すべき租税関係(さらに言えば租税法)に信義誠実の原則をそのまま援用すれば、当然、租税法律主義との抵触が生じることとなる。具体的な事件に関し、法律に定められた課税要件を行政が勝手に変更することになるからである。一方、結果的には法律が定める課税要件に適合するとしても、手続の面において何らかの問題があった場合には私人の権利や利益が侵害され、納得のできないものとなる可能性もあるから、可能な限りこれを避けなければならない。法律に従った課税を選択するか、私人の権利や利益の擁護を選択するか、難しい判断を迫られるのである。
なお、信義誠実の原則については、「租税法講義ノート」〔第3版〕の「第1部:租税法の基礎理論 第09回:租税法と信義誠実の原則」も参照していただきたい。
租税法において信義誠実の原則の適用があるか否かという問題が、初めて本格的に扱われたのが、次に示す判決である。
●東京高判昭和41年6月6日行裁例集17巻6号607頁(文化学院非課税通知事件)
事案:原告X(文化学院)は当時、民法上の財団法人であった〈学校法人となったのは1972(昭和47)年になってからである。なお、文化学院は2018(平成30)年3月に閉校した〉。Xは、自らが保有し、直接教育の用に供している土地および建物について固定資産税を非課税とするように求める文書を東京都千代田税務事務所長に提出した。同事務所長は、本件土地および建物が地方税法第348条第2項第9号に該当するものと誤認し、本件土地および建物については1953(昭和28)年度から非課税とする趣旨の決定を行い、同年9月17日付で通知した。しかし、それから8年ほど経った1961(昭和36)年6月に同事務所が調査したところ、Xの土地および建物は非課税物件ではなく、課税物件であることが判明した。そこで、同事務所長は本件土地および建物について固定資産税を賦課徴収するという趣旨の決定を行い、Xに送付した。Xは固定資産税を納めなかったので、Y(東京都知事)が土地について差押処分を行った。Xは、この差押処分の取消を求める訴訟を提起し、固定資産税賦課処分の無効も主張した。一審判決(東京地判昭和40年5月26日行集16巻6号1033頁)は、本件について信義誠実の原則(同判決では禁反言の原則)の適用を認め、差押処分を取り消したが、Yが控訴した。東京高等裁判所は、次のような趣旨を述べてXの請求を棄却した。
判旨:税務事務所長の通知が何らの法的効果を生ずるものでもなく、単に所長の関係や部内の方針を知らせた事実上の通知にすぎず、他方でXが学校法人でもないのに本件土地建物が非課税物件であると誤解しており、通知が誤解を深めたという程度にすぎない。このような「誤解に基づく違法な取扱いは少しでも早く是正されるべきであ」る。
この事件において、Xは、かつてなされたYの決定内容を信頼していた訳である。この場合、Xの信頼を保護する必要性があったのであろうか。Xは学校法人でないため、地方税法第348条第2項第9号の適用を受けないという前提事実を基にして考えてみていただきたい。
そして、次の判決において、最高裁判所が租税法の領域に関する信義誠実の原則の適用に関する原則らしきものを提示している。
●最三小判昭和62年10月30日判時1262号91頁(Ⅰ—24)
事案:Xは、Aが経営する酒屋に勤めており、しばらくしてからは実質的に経営をなすようになった。Aは青色申告について所轄税務署長Yの承認を受けており、昭和29年分から昭和45年分まで、事業所得に関する青色申告はAの名義で行われていた。しかし、昭和47年3月に行われた昭和46年分の青色申告はAの名義ではなく、Xの名義で行われている。Xは青色申告についてYの承認を受けていなかったが、何故かYはX名義の青色申告書を受理し、その後、昭和47年分から昭和49年分についても青色申告用紙をXに送付し、Xの青色申告を受理していた(なお、Aは昭和47年秋に死亡している)。或る日、YがAの相続人について相続税の調査を行った際に、Xが青色申告の承認を受けていないことが判明した。そこで、Yは昭和48年分および昭和49年分の青色申告の効力を否認し、白色申告とみなして更正処分を行った。Xは、この更正処分が信義誠実の原則に違反するとして処分の取消訴訟を提起した。一審判決(福岡地判昭和56年7月20日訟月27巻12号2351頁)および二審判決(福岡高判昭和60年3月29日訟月31巻11号2906頁)はXの主張を認めた。
判旨:最高裁判所第三小法廷は、次のように述べて破棄差戻判決を下した。
「租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。そして、右特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、のちに右表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか 、また、納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるといわなければならない」。
黄色のマーカー部分をまとめると、信義誠実の原則が適用されるためには、次の3点が必要である。
①信頼の対象適格性:行政庁が、納税者(例.青色申告者)に対して信頼の対象となる公の見解を、通達の公表など一般に対し、あるいは申告指導のように個別に示したこと。
②信頼保護の正当性。行政庁の表示を納税者が信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて、納税者に帰責事由があるか否か(帰責事由があれば保護されないこととなる)。
③信頼保護の必要性。②で納税者に帰責事由がなく、後に行政庁の表示と異なる行為(処分)が行われたために、納税者が経済的不利益を被ったか否か。
原文をお読みいただければおわかりのように、判決文においては上記要件を一つの文章で表現しており、とくに「第一に」、「第二に」というように記している訳ではない。そのため、 論者・教科書によってまとめ方が異なる。私は、この講義ノートでは、判決文において使われている接続詞などから判断して3つに分けたが、石村耕治編『税金のすべてがわかる現代税法入門塾』〔第10版〕(2020年、清文社)163頁においては4点にまとめた。
上の例からわかるように、信義誠実の原則は、多くの場合、相手方の信頼保護と関わる。厳密に言うならば、信義誠実の原則と相手方の信頼保護(の原則)は等号で結ばれない場合があるが、基本的には同じものと考えてよいであろう。
さて、上記最高裁判所第三小法廷判決は、どの要件に照らして信義誠実の原則の適用を否定したのであろうか。これを試験やレポートの問題として出すと、②、あるいは③の要件を満たさないものと考えられる、という答案が少なくない。
既に述べたように、判決文では上のようには書かれておらず、ただ一つの文章で表現しているだけであるから、どの要件に該当するかを答えることは難しいかもしれない。しかし、事案をよく読み、さらに、判決文を丁寧に読み返してみると、次に示す文章が続いていることがわかる。
「納税申告は、納税者が所轄税務署長に納税申告書を提出することによって完了する行為であり(国税通則法17条ないし22条参照)、税務署長による申告書の受理及び申告税額の収納は、当該申告書の申告内容を是認することを何ら意味するものではない(同法24条参照)。また、納税者が青色申告書により納税申告したからといって、これをもって青色申告の承認申請をしたものと解しうるものでないことはいうまでもなく、税務署長が納税者の青色申告書による確定申告につきその承認があるかどうかの確認を怠り、翌年分以降青色申告の用紙を当該納税者に送付したとしても、それをもって当該納税者が税務署長により青色申告書の提出を承認されたものと受け取りうべきものでないことも明らかである。そうすると、原審の確定した前記事実関係をもってしては、本件更正処分が上告人の被上告人に対して与えた公的見解の表示に反する処分であるということはできないものというべく、本件更正処分について信義則の法理の適用を考える余地はないものといわなければならない。」
すなわち、①の段階で適用がないものと判断されていることが理解されるであろう。①の要件に適合してこそ、②ないし③を論じる意味がある。従って、①の要件は他の要件の前提となっている訳である。
所轄税務署長の承認を受けずに青色納税申告書を提出したからといって、これが青色申告をなすことと言えないことは当然であろう。また、このように提出された申告書を税務署長が受理し、申告納税額を収納したからといって、これが直ちに青色申告納税の承諾を意味するものではなければ、納税者が青色申告者であることを公的な見解として表示したことにもならない。しかし、本件の場合、誤った扱いであるとはいえ、受理ないし収納という手続を税務署長が行い、しかも数年続いていたということになれば、これはもはや、黙示的であるとはいえ、公的見解を示したと理解してもよいのではないか、という意見も成り立ちうる。納税義務者の立場からすれば、たとえ税務署長の誤りによるとはいえ、一度は青色申告を受けつけ、その申告書に示された税額を収納しているのであるから、自らの誤りを棚に上げて青色申告を否認して更正処分をなすというのは背信的行為であると言わざるをえない。
▲行政庁(などの行政機関)の活動に対する相手方の信頼と信義誠実の原則
信義誠実の原則については、行政行為の撤回などについても問題となる場合が存在する。判例などで問題となったのは、計画や政策の変更に伴う損害である。このような場合には信義誠実の原則が適用されやすいとも言える。下級審判決において、信義誠実の原則の適用を認めた例として、次のものがある。
●熊本地玉名支判昭和44年4月30日判時574号60頁
熊本県荒尾市は、昭和30年代に住宅難を解消するため、公営住宅団地の建設計画を立てた。この計画による公営住宅には浴室設備の計画がなかったので、荒尾市は公衆浴場の建設設置者を募集し、甲を選んだ。荒尾市と甲は協議の末、公営住宅の建設、およびその公営住宅の所在地における公衆浴場の建設を内容とする契約を結んだ。この契約を履行するため、甲は公衆浴場の建設に着手し、翌年に99パーセントほどを完成させ、営業許可も得た。ところが、荒尾市長が死亡したことによって交代し、新市長は突然この建設計画を縮小したため、公衆浴場は経営が不可能な状態に陥った。そこで甲は荒尾市に対して損害賠償を請求した。判決は、荒尾市の行為が不法行為を構成するとして、甲の請求を一部認めた。
逆に、信義誠実の原則の適用を認めなかったものとしては、札幌高判昭和44年4月17日行集20巻4号486頁、仙台高判平成6年10月17日判時1521号53頁などがある。
最高裁判所の判例のうち、信義誠実の原則または信頼保護の原則の適用を認めたものの代表例として、次の判決がある。
●最三小判昭和56年1月27日民集35巻1号35頁(Ⅰ−25)
事案:Xは、沖縄県のY村に製紙工場を建設する計画を立てた。Y村の当時の村長であったAは、Xからの陳情を受け、工場を誘致してY村所有の土地をXに譲渡する旨の議案を村議会に提出した。これが可決されてから、AはXの工場建設に全面的に協力する旨を言明し、さらに手続を進めた。Xも、村有地の耕作者に対する補償料の支払い、機械設備の発注の準備などを進め、工場敷地の整地工事も完了させた。ところが、ちょうどその頃に村長選挙が行われて工場誘致反対派のBが村長に当選し、就任した。BはXに対し、工場の建設確認申請に同意しない旨を伝えた。Xは、工場の建設や操業ができなくなったとして、Y村を相手取って損害賠償を請求する訴訟を起こした。一審判決(那覇地判昭和50年10月1日判時815号79頁)および二審判決(福岡高那覇支判昭和51年10月8日金判618号36頁)はXの請求を棄却したが、最高裁判所第三小法廷は破棄差戻判決を下した。
判旨:「地方公共団体の施策を住民の意思に基づいて行うべきものとするいわゆる住民自治の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則であり、また、地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたつて継続すべき施策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴つて変更されることがあることはもとより当然であつて、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。しかし、右決定が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、右特定の者は、右施策が右活動の基盤として維持されるものと信頼し、これを前提として右の活動ないしその準備活動に入るのが通常である。このような状況のもとでは、たとえ右勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との間に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であつても、右のように密接な交渉を持つに至つた当事者間の関係を規律すべき信義衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたつてはかかる信頼に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入つた者がその信頼に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない。そして、前記住民自治の原則も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではないから、地方公共団体の施策決定の基盤をなす政治情勢の変化をもつてただちに前記のやむをえない客観的事情にあたるものとし、前記のような相手方の信頼を保護しないことが許されるものと解すべきではない」。
〔4〕権利濫用禁止の原則
民法第1条第3項に規定される権利濫用禁止の原則も、民法に限らず、あらゆる法領域に適用されるべき法の一般原則である。
そもそも、民法が明治時代に制定されてから長らくの間、信義誠実の原則および権利濫用禁止の原則に関する明文の規定は民法に存在しなかった。信義誠実の原則が日本の学説や判例において肯定されるようになったのは大正期である。また、権利濫用禁止の原則は明治期から判例において登場していたが、本格的に定着したのは宇奈月温泉事件として有名な大判昭和10年10月5日民集14-1965によると言われる。両原則が民法第1条として明文化されたのは第二次世界大戦後の1947(昭和22)年であり、親族編・相続編の大改正と同時に第1条が追加されたのである。
形式的には法律による行政の原理に適合する活動としても、その活動の目的が不当なものであれば、違法と判断されざるをえない。行政法学においては、とくに行政裁量論において裁量権の逸脱・濫用の例として取り上げられることが多かった。
●最二小判昭和53年5月26日民集32巻3号689頁(Ⅰ―29。国家賠償請求訴訟)および最二小判昭和53年6月16日刑集32巻4号605頁(Ⅰ―68。刑事訴訟)
事案:X社は、個室付公衆浴場の設置を計画し、山形県公安委員会に営業許可を申請した。しかし、この計画を知った余目町(現在は庄内町の一部)は、個室付公衆浴場の予定地である場所から200mも離れていない場所にA児童遊園を設置するために県知事に認可を申請し、X社への営業許可よりも早い日に認可を得た。X社は個室付公衆浴場を開業したため、同県公安委員会から営業停止処分を受け、また、風俗営業等取締法違反に問われて起訴された。そこで、X社は、営業停止処分の取消を求めて出訴するとともに(途中で山形県に対する国家賠償請求訴訟に変更した)、刑事訴訟においては無罪を主張した。
国家賠償請求訴訟については、一審判決(山形地判昭和47年2月29日判時661号25頁)がXの請求を棄却したのに対し、二審判決(仙台高判昭和49年7月8日判時756号62頁)はXの請求を認容した。山形県が上告したが、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却した。
また、刑事訴訟については、一審判決(酒田簡判昭和47年10月23日刑集32巻4号623頁)がX社に対して罰金刑を言い渡し、二審判決(仙台高秋田支判昭和49年12月10日判タ323号279頁)はX社の控訴を棄却した。X社が上告し、最高裁判所第二小法廷は二審判決を破棄し、X社を無罪とする判決を言い渡した。
国家賠償請求訴訟の判旨:「所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし是認することができ、原判決に所論の違法はない。そして、原審の認定した右事実関係のもとにおいては、本件児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法であり、かつ、右認可処分とこれを前提としてされた本件営業停止処分によつてX社が被つた損害との間には相当因果関係があると解するのが相当であるから、X社の本訴損害賠償請求はこれを認容すべきである」。
刑事訴訟の判旨:「本来、児童遊園は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする施設(児童福祉法40条参照)なのであるから、児童遊園設置の認可申請、同認可処分もその趣旨に沿つてなされるべきものであつて、前記のような、X社のトルコぶろ営業の規制を主たる動機、目的とする余目町のA児童遊園設置の認可申請を容れた本件認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、X社のトルコぶろ営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざるをえない」。
▲第7版における履歴:2020年4月23日掲載。
2020年4月27日修正。
▲第6版における履歴:2015年9月22日掲載。
2017年10月19日修正。
2017年10月26日修正。
2017年12月20日修正。