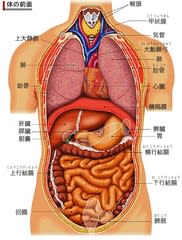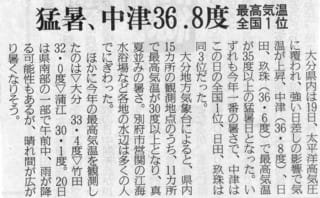トップアスリートから学ぶことができるというのは、本当に貴重な体験です。技術習得とともに、夢や目標を持つことができます。先日学校にトリニータの選手がやってきました
トップアスリートから学ぶことができるというのは、本当に貴重な体験です。技術習得とともに、夢や目標を持つことができます。先日学校にトリニータの選手がやってきました

大分県では、プロなどで活躍するチームの選手たちを中学校の部活動に派遣して、生徒に夢や希望を与えるとともに指導者の育成を図るため、今年度から「プロチームを活用した地域スポーツ普及事業を実施して学校を応援してくれています。
サッカー部が書面で応募したところ、学校に来てくれるようになりました。
生徒たちも日頃新聞やテレビなどでしかトリニータのことを知る機会はありませんが、直接学校に来て選手が指導してくれることで、楽しみにしていました。以前、今の学校に勤務する前に、一年間一緒に大学の講義を受けていた方も来てくれていました。
その人は、昨年度までトリニータの強化部長をしていました。トリニータがJ2に降格してからは、地域に出向いていって、このような広報活動をおこなっています。久しぶりに会う機会を持つことができました。
トリニータのコーチや選手たちは、暑い中、2時間たっぷり生徒たちに教えてくれました。話す言葉、一つひとつが素人の自分でもわかりやすく思えました。プロの方たちだけにやはり、教え方もすばらしかったです。短時間ですが、効率のよい練習を繰り広げていました。
また練習後の質問コーナーの内容を、帰ってから、すべてパソコンでQ&Aを作ってくださって、その日に、FAXで送ってくれました。ていねいな心配りでした。

今日の朝刊にこの日の様子が掲載されています。
サッカー部のみんなは、さらにサッカーが好きになって、これからの練習に臨んでいくことでしょう。8月の後半には大会もあります。それに向けてまたグランドを駆け回ってほしいと思います。これからの活躍が楽しみです。
トリニータは、今は、J2です。このところ、なかなか勝てない試合が多く続いていますが、ここは、ふんばって、また子どもたちにそして大分に住んでいる人たちに夢を与えてもらいたいと思います。
















 何気ない言葉がうれしいときもあり、気持ちを下げるときもあります。言葉の使い方を自分自身もしっかりと使いこなさなければと思うのですが、まだまだです
何気ない言葉がうれしいときもあり、気持ちを下げるときもあります。言葉の使い方を自分自身もしっかりと使いこなさなければと思うのですが、まだまだです