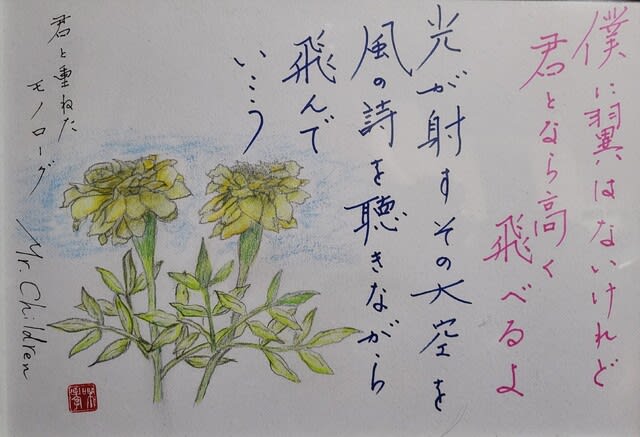なんとなく梅雨の匂いがします。
庭のあじさいがとてもきれいに咲いています。
これから雨の季節となっていきます。

昨日の夕方は、水神祭が地区の神社で開催されました。
水の恵みを乞う、水の災いが地区を守るということの祭典です。

神事を行い、そのあとは直会があります。
昔からの「祈る」の行事です。
田んぼの神様を迎えて豊作を願い、その際、田んぼで取れる米から造った日本酒を神様にお供えしていたことから祭事やお祭りでは日本酒がお供物として扱われ、そのお下がりをいただくということだそうです。

座元だったので、直会では、社務所で、お弁当・お酒のふるまいがあります。

ひと昔までは、夜遅くまで飲み明かしたことでしょう。
今は、既定のお酒を飲み終えてから終わりです。

今年は座元。
最後は、来年の座元に引き継ぐ「らいつ(どんな字を書くのでしょう。)」があります。

お酒をコップにつがれて、飲みほしてから、
「まだまだそれでは、来年に引き渡されん。」
と周りから言われ、また飲んで・・・。
来年の方に当番を渡します。

今日は、近所の方が用事でやってきたときに、
「昨日は、大丈夫やった?」と
言われました。
大丈夫ではありません。
こんな祭典をくり返しながら、地区の絆も深めていったのでしょう。

気分が悪くなった分だけ、今年は、水の恵みを受け、水の災難がない地区であって欲しいと願っています。