 先日の日曜日からふるさとを離れている子どもが帰ってきました。近くに住んでいる子どもたちと一緒に食事もしながら何日間を楽しく過ごしました
先日の日曜日からふるさとを離れている子どもが帰ってきました。近くに住んでいる子どもたちと一緒に食事もしながら何日間を楽しく過ごしました
久しぶりにゆっくりとふるさとを離れて暮らしている子どもが今日まで帰省をしていました。
近くに住んでいる子どもたちも帰ってきて、姉がプレゼントしてくれたフライヤーを使ってみんなで楽しく食事などをすることができました。
なかなかゆっくり帰省することのない子どもでしたが、今回は、時間を取ることができ、みんなで会話を弾ませました。今日、また戻っていきましたが、なんとなく家がぽっかりと空いたような雰囲気になりました。
家族の中で見送り役っているような気がします。
主観的ですが、幼い時から、ふと一番下の自分や親があてはまるのかなあと思います。自分には姉が二人いて、3人兄弟の末っ子になります。
まだ姉たちが学生だった頃、当時交通事情もよくなかったせいもあり、家の近くから中津の高校に通う場合は、下宿する学生がほとんどでした。上の姉が高校に通い出し、家を出ていきます。
下の姉が高校に行くために、また一人家を離れていきます。
さらに上の姉は、今度は大学にいくために、もっと遠いところで暮らし始めます。大学ともなると、めったに帰ることがないので、姉たちが車に乗って、それぞれの生活にもどっていくときに、父や母が手を振りながらも涙を流していたことが今でも心に残っています。
見送ったあとは、何となく家がひっそりとしていました。大学のあとは、今度は、結婚で家を巣立っていきました。自分以上に父や母にはいろんな思いが交錯していたことでしょう。
今日、子どもが生活しているところに戻っていきました。寂しくは感じますが、それはそれで、自立していっているんだなあと思うようにしています。今度は親の立場です。
無事に着いたという電話があったのは、何よりでした。






















 なんとなく天候が不順なこの頃です。夏日があったかと思えば、今日の朝の冷え込みは厳しかったです。先日の土曜日の朝は、雨が激しく、川は濁流となりました。そんな最近の気候です
なんとなく天候が不順なこの頃です。夏日があったかと思えば、今日の朝の冷え込みは厳しかったです。先日の土曜日の朝は、雨が激しく、川は濁流となりました。そんな最近の気候です






 毎日、学年練習や全校練習で合唱祭の向けての練習が始まっています。来月の日曜日に三光中学校の合唱祭が開催されます。目標をもって取り組みの強化をしてもらいたいと思います
毎日、学年練習や全校練習で合唱祭の向けての練習が始まっています。来月の日曜日に三光中学校の合唱祭が開催されます。目標をもって取り組みの強化をしてもらいたいと思います



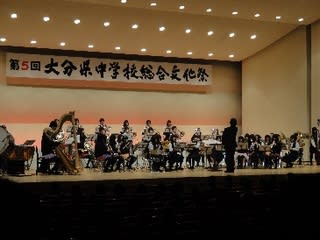



 生徒総会が今日の午前中に行われました。いよいよ生徒会も3年生から2年生に移り変わります。学校の中のいろんな組織が2年生中心となっていっています。もうそんな時期となってきています
生徒総会が今日の午前中に行われました。いよいよ生徒会も3年生から2年生に移り変わります。学校の中のいろんな組織が2年生中心となっていっています。もうそんな時期となってきています



 知り合いの方に誘われて、ヨットに乗る機会がありました。今まで、釣舟などには乗ったことがあるのですがヨットから見える海の風景は初めてでした
知り合いの方に誘われて、ヨットに乗る機会がありました。今まで、釣舟などには乗ったことがあるのですがヨットから見える海の風景は初めてでした

 大分県駅伝競技大会が行われました。この大会をもって今年度の三光中学校の中体連関係の行事は終わります。7月から4ヶ月間、生徒たちは、一週間に1.2度の練習に頑張ってきました
大分県駅伝競技大会が行われました。この大会をもって今年度の三光中学校の中体連関係の行事は終わります。7月から4ヶ月間、生徒たちは、一週間に1.2度の練習に頑張ってきました



 秋が深まっていく中、いろんな行事が各地で行われています。お誘いがあって、昨日、日田の「千年あかり」に行ってきました。ろうそくが天領の街を淡く灯していきました
秋が深まっていく中、いろんな行事が各地で行われています。お誘いがあって、昨日、日田の「千年あかり」に行ってきました。ろうそくが天領の街を淡く灯していきました











