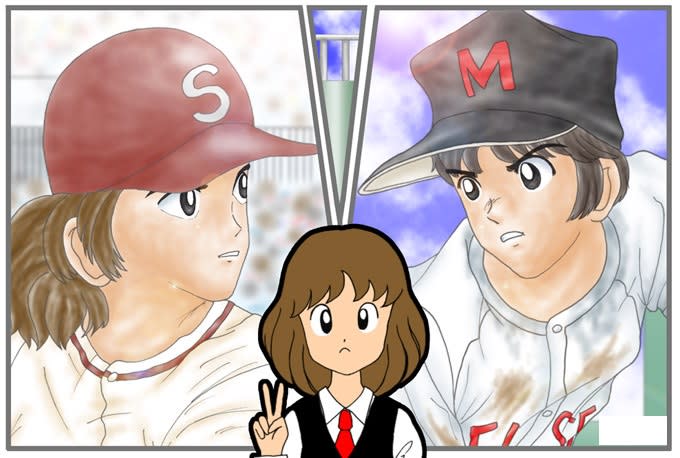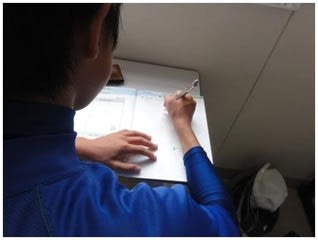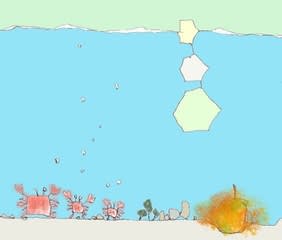「子どもらを幸せにできる学舎に」
「子どもらを幸せにできる学舎に」心がけ過ごす2学期もすぐそこ

おとといの午後、大分大学付属教育実践総合センターで福島県の短期大学の先生が来県。その先生の講演を聞きに行きました。
「STEP勇気づけを活用した中学校の生徒指導の実践」というテーマで話をされました。
以前、先生の本を読んだことがあります。福島という遠い地に住んでいる先生の話を直接聞けることは、最初で最後かも知れないので、いろんな行事に断りを入れて、出かけました。
小さな研修室で20人くらいの中で一番前で、目の前で聞くことができました。
ちょっと感動。斬新な考え方で生徒たちに接しています。本を書いた頃は、中学校の数学の先生でした。「勇気づけ」という手法を用いて、学級崩壊をしたクラスを立て直していったことを書き表しています。
先生の境地にはまだまだ至ることはできませんが、多くのことを学びました。勇気づけの姿勢は次のようにとらえています。
①あるがままの子どもを受け入れる。
②子どものよい点や長所に目を向け、建設的な見方をする。
③子どもを信頼して、先走りをしない。
④結果よりもプロセスを認める。
⑤長所や能力に注目し、人の役に立っていることを感じさせる。
その姿勢の中で、目標は、
①子どもの言動の目標を理解し、それを建設的な方向に導き、そして子どもを勇気づける。
②子どもの話をよく聴き、子どもも親や教師の言葉に耳を傾ける効果的なコミュニケーションを創る。
③子どものしつけに関しては、日常生活の中で子どもたちに『自然の結末』などを体験させることを通して、責任感を育てる。
中学校教師、武道家をめざす空手家、半そでから出ている腕は筋肉もりもり。そして何より若い。
そんな先生が管理型から「子どもを幸せにできる教師」をめざした実践家に変貌して子どもとのあたたかな関わりを持ち続けて活動しています。
残りの教師生活。少しでも「子どもを幸せにできる」先生に近づくことができることをめざしたいです。