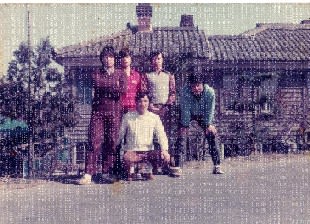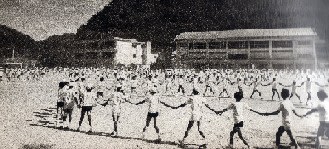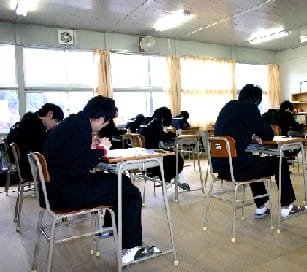卒業式シーズンがやってきました。今週の木曜日が中学校の卒業式です。しかし、その前に、高校の卒業式が行われます。明日が卒業式となっています。
卒業式シーズンがやってきました。今週の木曜日が中学校の卒業式です。しかし、その前に、高校の卒業式が行われます。明日が卒業式となっています。



いよいよ明日が高校の卒業式です。それぞれの胸の中には、いろんな夢や目標が立てられ、それに向けて出発をしていきます。
今日は、ある生徒が進学した高校の部活の「3年生を送る会」に出席をしました。
生徒から、「送る会に来て下さい。」と電話がありました。高校を卒業してから、東京の大学に進学をしていきます。その前に会いたかったこともあったので、月曜日でしたが、すぐにOKの言葉を言いました。
生徒は、3年間、全国でも強豪の部活動に所属をしていました。中学校時代とは違う部活なので、経験は少なかったのですが、将来性を見込まれて、その部に入りました。親元を離れての高校生活です。
故障、けが・・・いろんなことに悩まされましたが、3年間、粘り強くやり通しました。
「先生、確かに1年生の時は、きつかったけれど、それを乗り越えてから、楽しくなりました。」
生徒の学年は、3年生の時に、惜しくも全国大会には出場できませんでした。今日の送る会の中では、その悔しさが先生やいろんな選手の言葉から出てきました。3年生の全員が関東の大学に進学していきます。
「この悔しさを大学で、生かしていきたいと思います。」
と生徒は、語っていましたが、いつか晴れの姿を応援に行きたいと思います。
お父さんやお母さんたちが来ていました。部活動に明け暮れた高校生活。でもその中で、故郷を離れて頑張る中で、走る技術とともに、親を思う気持ち、礼儀、苦しさを乗り越える精神力・・・勝つこと以上に学んだことも多いと思います。
親が生徒へ語る言葉、生徒が3年間の思いを話す内容・・・心を打つものがたくさんありました。
「この3年間、厳しいトレーニングを積み、それをしっかりと受け止め、努力してきたことは、これから生きていく中で大きな自信や行動力につながるだろうね。」とお家の方と話をしました。
これからもみんなに夢を与えて下さいね。卒業おめでとう。