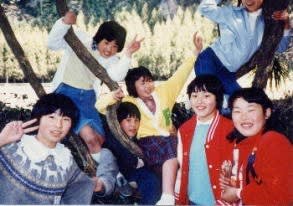昨日から雪が降っています。朝の積雪は、耶馬渓は、10センチ近くありました。久しぶりにこのような雪が積もった風景を見ることができました。銀世界の中で、新しい年を迎えようとしています
昨日から雪が降っています。朝の積雪は、耶馬渓は、10センチ近くありました。久しぶりにこのような雪が積もった風景を見ることができました。銀世界の中で、新しい年を迎えようとしています



大晦日から正月にかけて、雪が降るという天気予報が出ていました。まさに予報通りになりました。
昨晩からものすごい雪が降りました。朝は、見事に銀世界。正月に雪が降るというのが、3年連続です。今年は別ですが、あったかい冬でも正月になってから、雪が降ります。
昨晩は、中津市内に泊まったのですが、朝、耶馬渓に戻るとき、家族と車で耶馬渓の方に車を走らせました。
街部は、ほとんど雪がなかったのですが、だんだん奥に入って、三光を過ぎるころから雪景色となってきました。道路は、まだ凍っているところがあって、どの車も減速をして運転をしていました。すれ違う車の屋根は雪が覆っています。
写真は、昨日からの雪景色です。玄関前の足跡・・・。夕方5時過ぎには、もうこのくらい雪が積もっていました。新雪を踏んだのは、誰でしょう。
そして、家の前の川の水面に朝日が当たった風景がきれいだったので、シャッターを押しました。冬の訪れをしっかりと感じました。

2010年の終わりを告げます。今年一年お世話になりました。