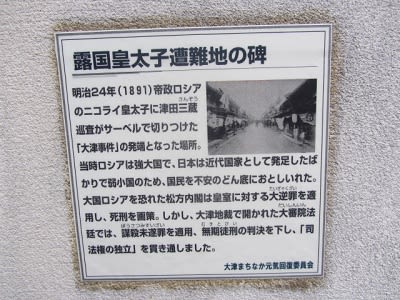北座跡
2015-07-22 | 石碑
京都南座向かいの北座ビルの前に北座跡の碑があります。

江戸時代中期、四条河原には、幕府公認の七つの芝居小屋がありました。
その後、火事で幾度も焼失し、また興行の中心が大坂に移ったため次第に数が減り、江戸時代中期には四条通りの南と北、大和大路の西の三座となります。
西の芝居は1794年(寛政6年)の大火後は再建されず、二座が残った。さらに南座の向かいにあった北座は
1892年(明治25年)四条通の拡張に伴い閉鎖され、南座のみになりました。

北座ビルは、その北座があった辺りに建てられ、一階は井筒八ッ橋本舗の本店となっています。


北座跡(この付近)
寛文10年(1670)以降、鴨川の両岸に新堤が築かれたことによって鴨河原の風景は一変した。
河原は「新地」(新造成地の意味)となりここに広大な芝居街と茶屋町が出現することになった。
延宝4年(1676)の絵図「祇園社並旅所之図」によれば、この時期すでに東岸の四条通をはさんで計6件の芝居小屋が描かれている。
17世紀末の元禄期になるとこの芝居小屋は7軒に増加する。
18世紀初頭の「京都御役所向大概覚書」によあると四条北側芝居は井筒屋助之丞、両替屋伝左衛門の所有とあり、さらに南側芝居は大和屋利兵衛、越後屋新四郎、伊勢屋喜兵衛の三者が所有者としてあげられていた。
しかし、たびたびの大火で19世紀末にはわずか北側に一軒南側に一軒となった。
その北側の一軒北座も明治26年(1894)に四条通拡幅によって消滅した。
ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

 にほんブログ村
にほんブログ村
 神社・仏閣 ブログランキングへ
神社・仏閣 ブログランキングへ

江戸時代中期、四条河原には、幕府公認の七つの芝居小屋がありました。
その後、火事で幾度も焼失し、また興行の中心が大坂に移ったため次第に数が減り、江戸時代中期には四条通りの南と北、大和大路の西の三座となります。
西の芝居は1794年(寛政6年)の大火後は再建されず、二座が残った。さらに南座の向かいにあった北座は
1892年(明治25年)四条通の拡張に伴い閉鎖され、南座のみになりました。

北座ビルは、その北座があった辺りに建てられ、一階は井筒八ッ橋本舗の本店となっています。


北座跡(この付近)
寛文10年(1670)以降、鴨川の両岸に新堤が築かれたことによって鴨河原の風景は一変した。
河原は「新地」(新造成地の意味)となりここに広大な芝居街と茶屋町が出現することになった。
延宝4年(1676)の絵図「祇園社並旅所之図」によれば、この時期すでに東岸の四条通をはさんで計6件の芝居小屋が描かれている。
17世紀末の元禄期になるとこの芝居小屋は7軒に増加する。
18世紀初頭の「京都御役所向大概覚書」によあると四条北側芝居は井筒屋助之丞、両替屋伝左衛門の所有とあり、さらに南側芝居は大和屋利兵衛、越後屋新四郎、伊勢屋喜兵衛の三者が所有者としてあげられていた。
しかし、たびたびの大火で19世紀末にはわずか北側に一軒南側に一軒となった。
その北側の一軒北座も明治26年(1894)に四条通拡幅によって消滅した。
ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m












 中山正美作「都の大殉教」より テクラ橋本(バチカン美術館蔵)
中山正美作「都の大殉教」より テクラ橋本(バチカン美術館蔵)