東京都目黒区にある五百羅漢寺を訪ねてみました。

当寺は、元々は本所五ツ目(現在の江東区大島)に創建され、五代将軍綱吉さらに八代将軍吉宗の援助を得て「本所のらかんさん」として人びとの人気を集めていましたが、度々洪水に見舞われて衰退し、明治時代に目黒の現在地に移転しました。
現在の五百羅漢寺は、近代的な鉄筋コンクリート3階建てのビルで、この中に寺務所、書院、聖宝殿(寺宝や歴史資料が展示されている)、目黒霊廟などがあります。


当寺の羅漢像は、元禄年間に松雲元慶禅師によって十数年の歳月をかけて造られたもので、江戸時代の羅漢ブームの火付け役となったそうです。
現在は305体が昭和56年に新築された本堂、羅漢堂に安置されています。
羅漢像の撮影は禁止なので、画像はありませんが、本堂に並ぶ等身大の羅漢像は迫力満点でした。
羅漢堂には146体の像が安置されています。
松雲元慶の五百羅漢像の特徴は、瞼に厚みがあることだとか。
そのせいか人間らしい表情をした像が多いと感じました。
葛飾北斎『冨嶽三十六景』の中でも「五百らかん寺さざゐ堂」が描かれているのですね。

私が羅漢像に興味を持ち始めたのは、この美術展がきっかけでした。
江戸東京博物館の「五百羅漢 幕末の絵師 狩野一信」展

狩野 一信は、江戸時代後期の絵師で、増上寺に全100幅にも及ぶ大作『五百羅漢図』を残した事で知られています。この100幅にも及ぶ羅漢図は、増上寺の寺宝でありながら、寺外で全作品が展示される機会がありませんでした。
2011年は、浄土宗の開祖・法然上人の800年を迎える節目の年にあたり、それに合わせて展覧会の開催となったそうです。
狩野派の筆法を身につけていたとはいえ、生前「狩野」という姓を名乗ったことはないといいますから、このような展覧会で人々を振り向かせる為に、「狩野」という姓を使用したのでしょう。
その羅漢図がどのようなものであるか・・・
地獄を描いた図

大蛇の口の中での座禅

少年が剃髪して出家得度する場面

とても幕末の絵とは思えないでしょう?
普通の羅漢図とは違い、まじめな絵ばかりではありません。
あくびをしたり、鼻をほったりする羅漢さまもいて、思わず笑ってしまいそうな絵もあります。
私は、予め「芸術新潮」で全100幅の縮小版を見ておいたのですが、実物の印象はまるで違い、色は鮮やか、髪の毛の一本一本まで、実に繊細に描かれていました。
五百羅漢寺以外にも、羅漢寺を訪ねましたので、また紹介していきます。
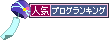


当寺は、元々は本所五ツ目(現在の江東区大島)に創建され、五代将軍綱吉さらに八代将軍吉宗の援助を得て「本所のらかんさん」として人びとの人気を集めていましたが、度々洪水に見舞われて衰退し、明治時代に目黒の現在地に移転しました。
現在の五百羅漢寺は、近代的な鉄筋コンクリート3階建てのビルで、この中に寺務所、書院、聖宝殿(寺宝や歴史資料が展示されている)、目黒霊廟などがあります。


当寺の羅漢像は、元禄年間に松雲元慶禅師によって十数年の歳月をかけて造られたもので、江戸時代の羅漢ブームの火付け役となったそうです。
現在は305体が昭和56年に新築された本堂、羅漢堂に安置されています。
羅漢像の撮影は禁止なので、画像はありませんが、本堂に並ぶ等身大の羅漢像は迫力満点でした。
羅漢堂には146体の像が安置されています。
松雲元慶の五百羅漢像の特徴は、瞼に厚みがあることだとか。
そのせいか人間らしい表情をした像が多いと感じました。
葛飾北斎『冨嶽三十六景』の中でも「五百らかん寺さざゐ堂」が描かれているのですね。

私が羅漢像に興味を持ち始めたのは、この美術展がきっかけでした。
江戸東京博物館の「五百羅漢 幕末の絵師 狩野一信」展

狩野 一信は、江戸時代後期の絵師で、増上寺に全100幅にも及ぶ大作『五百羅漢図』を残した事で知られています。この100幅にも及ぶ羅漢図は、増上寺の寺宝でありながら、寺外で全作品が展示される機会がありませんでした。
2011年は、浄土宗の開祖・法然上人の800年を迎える節目の年にあたり、それに合わせて展覧会の開催となったそうです。
狩野派の筆法を身につけていたとはいえ、生前「狩野」という姓を名乗ったことはないといいますから、このような展覧会で人々を振り向かせる為に、「狩野」という姓を使用したのでしょう。
その羅漢図がどのようなものであるか・・・
地獄を描いた図

大蛇の口の中での座禅

少年が剃髪して出家得度する場面

とても幕末の絵とは思えないでしょう?
普通の羅漢図とは違い、まじめな絵ばかりではありません。
あくびをしたり、鼻をほったりする羅漢さまもいて、思わず笑ってしまいそうな絵もあります。
私は、予め「芸術新潮」で全100幅の縮小版を見ておいたのですが、実物の印象はまるで違い、色は鮮やか、髪の毛の一本一本まで、実に繊細に描かれていました。
五百羅漢寺以外にも、羅漢寺を訪ねましたので、また紹介していきます。































