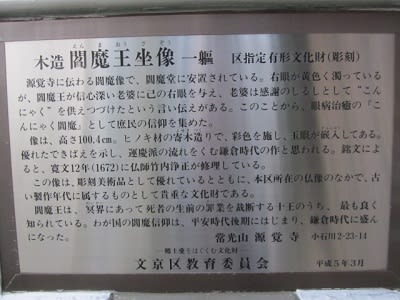塩地蔵尊


二体で一組のお地蔵さま。
お地蔵さまの体に塩をつけてお祈りすると、同じ部分の病気が治るといいます。
砂のように見えるのは塩です。
「塩」ということで、お相撲さんもお参りに見えるそうですよ・
毘沙門天

小石川七福神のひとつになっています。
ブログランキングに参加しています(*^_^*)
応援よろしくお願いしますm(__)m

 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ


二体で一組のお地蔵さま。
お地蔵さまの体に塩をつけてお祈りすると、同じ部分の病気が治るといいます。
砂のように見えるのは塩です。
「塩」ということで、お相撲さんもお参りに見えるそうですよ・
毘沙門天

小石川七福神のひとつになっています。
ブログランキングに参加しています(*^_^*)
応援よろしくお願いしますm(__)m

 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ