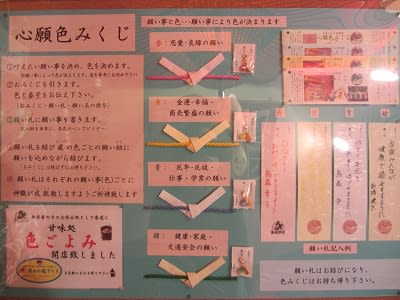浅草に神田山日輪寺という将門ゆかりの寺院があります。




日輪寺
台東区西浅草3丁目15番6号
神田山柴崎道場日輪寺という。創建は一説に9世紀、武蔵国豊島郡柴崎村(現千代田区大手町)に天台宗の了円法師が開基したと伝えられる。柴崎村には天慶の乱で天慶3年(940年)に戦死した平将門の墳墓が築かれたが、のちに荒廃して、将門の亡霊が村民を悩ますようになった。嘉元年中(1303~6)、時宗二祖他阿真教上人が村民の求めにより丁重に供養して亡霊を鎮め、その霊魂を神田明神に祀った。村には平和がたちまち戻り、上人は村民たちに請われて日輪寺を時宗の念仏道場に改めたという。江戸時代の神田明神祭礼では、日輪寺の僧侶が読経してから神輿を出す例となっていた。
日輪寺は天正18年(1590年)徳川家康の江戸入城以後、江戸の都市整備や災害復興などにともない、何度か所在地を変えている。現在地に移転した年代は二説あり、慶長8年(1603年)という説と明暦3年(1657年)江戸大火の後という説がある。
明治2年から昭和40年まで、この付近の町名を柴崎町といったが、その町名は日輪寺に由来している。
台東区教育委員会


真教上人直筆の将門鎮魂碑「南阿弥陀仏」

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m












 、将門公の史跡を巡っています。
、将門公の史跡を巡っています。