

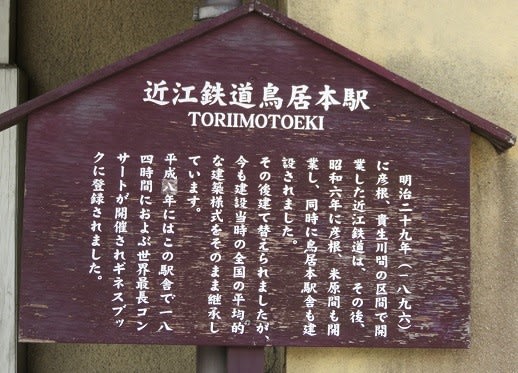
文政12年(1829年)から天保12年(1841年)までの『寺村家大福帳』によると、本陣宿泊客の状況は、13年間に161回3,594名が宿泊している。1年間の利用回数にばらつきがあるが、平均で年間利用回数12.4回、1回の平均利用者数22.3名であった。また1回の利用者数の最多は80名、最小は2名で、実際は50 - 60名がその収容限度であった。参勤交代の大名の供揃のように200 - 300名に達すると、全員を本陣に収容することはできず、多い時には156軒の下宿が必要になった。
また、天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、鳥居本宿の長さは小野村境から下矢倉村まで13町(約1.4 km)、宿高115石、鳥居本宿の宿内家数は293軒、うち本陣1軒、脇本陣2軒、問屋場1軒、旅籠35軒で宿内人口は1,448人であった。
鳥居本宿は、安芸廣島藩・筑前久留米藩・紀伊和歌山藩・阿波徳島藩・出雲松江藩・長門萩藩・美作津山藩・伊予松山藩などが利用しており、下宿を利用する大通行が年間数回ずつあった。 (Wikipediaより)


ちょうどこの日は「とりいもと宿場まつり」が開催されていました。


近江鉄道サイクルトレインについてはこちらをご覧ください。
http://www.ohmitetudo.co.jp/railway/cycle/index.html/

























