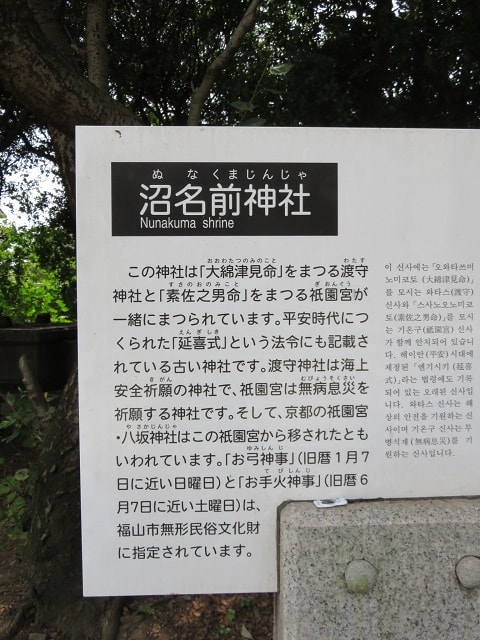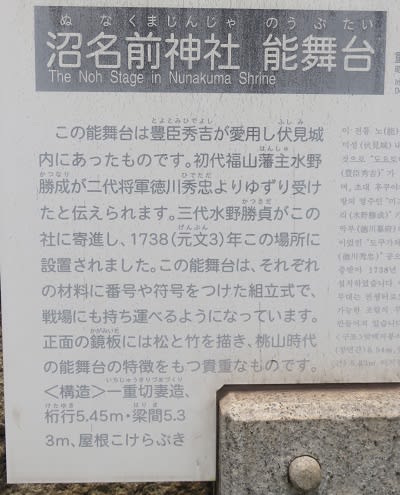安国寺は、南北朝動乱の戦死者を弔うために、足利尊氏・直義兄弟が国ごとに造ったお寺です。

この備後安国寺も、室町時代の建物と考えられていましたが、後の調査により、鎌倉時代、文永10年(1273年)無本覚心(法燈国師)を開山として金宝寺として創建されたものと判明しました。

南北朝時代、足利尊氏により寺号を「安国寺」と改めました。
安土桃山時代に、毛利輝元、安国寺恵瓊により再興され、江戸時代初期に、京都妙心寺の末寺となりました。
釈迦堂


室町時代中期建立。禅宗様建築で、鎌倉時代の典型的な唐様の技法がみられ、堂内の木造阿弥陀三尊像・木造法燈国師座像とともに国重文に指定されています。
子安観音堂

昭和期再建。
鞆の津塔

承応3年(1654)鞆の豪商が建立した鞆独特の石塔。
ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

 にほんブログ村
にほんブログ村
 神社・仏閣 ブログランキングへ
神社・仏閣 ブログランキングへ

この備後安国寺も、室町時代の建物と考えられていましたが、後の調査により、鎌倉時代、文永10年(1273年)無本覚心(法燈国師)を開山として金宝寺として創建されたものと判明しました。

南北朝時代、足利尊氏により寺号を「安国寺」と改めました。
安土桃山時代に、毛利輝元、安国寺恵瓊により再興され、江戸時代初期に、京都妙心寺の末寺となりました。
釈迦堂


室町時代中期建立。禅宗様建築で、鎌倉時代の典型的な唐様の技法がみられ、堂内の木造阿弥陀三尊像・木造法燈国師座像とともに国重文に指定されています。
子安観音堂

昭和期再建。
鞆の津塔

承応3年(1654)鞆の豪商が建立した鞆独特の石塔。
ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m