小松寺は、1175(安元元)年に、平清盛の長男・平重盛が、厳島神社へ参拝する途中、静観寺の境内に、旅の無事を祈る阿弥陀仏像とお堂を建立したのが、小松寺の始まりとされています。



境内には、重盛が植えたという巨大な松がありましたが、1954(昭和29)年の台風で倒壊し、
枯死してしまったそうです。
足利尊氏・直義兄弟、足利義昭、朝鮮通信使などともゆかりのあるお寺です。
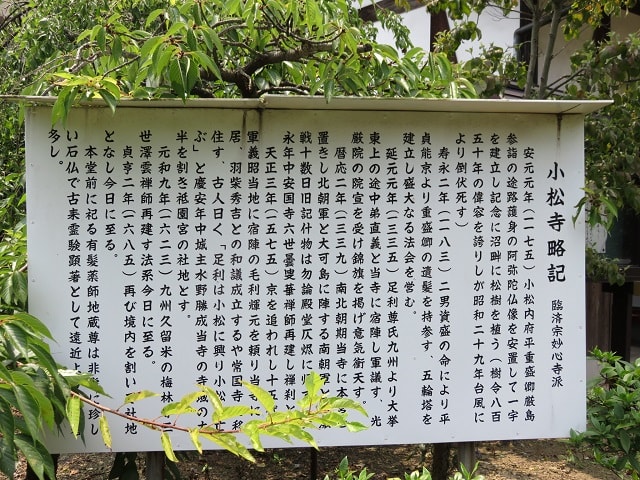
有髪薬師地蔵尊

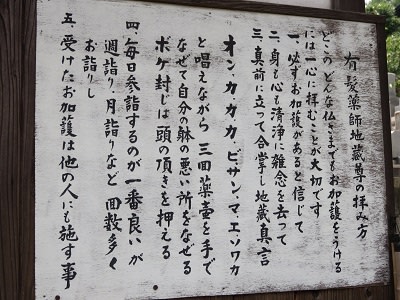
ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

 にほんブログ村
にほんブログ村
 神社・仏閣 ブログランキングへ
神社・仏閣 ブログランキングへ



境内には、重盛が植えたという巨大な松がありましたが、1954(昭和29)年の台風で倒壊し、
枯死してしまったそうです。
足利尊氏・直義兄弟、足利義昭、朝鮮通信使などともゆかりのあるお寺です。
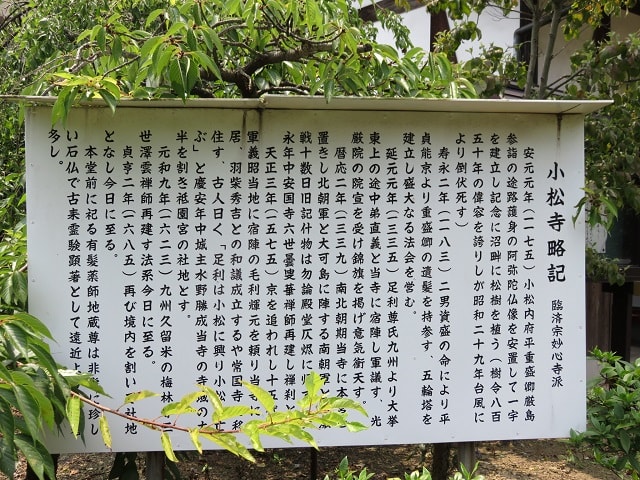
有髪薬師地蔵尊

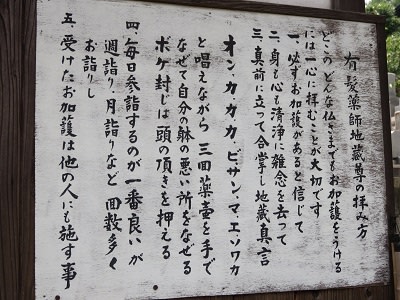
ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m




























 (Wikipediaより)
(Wikipediaより)





