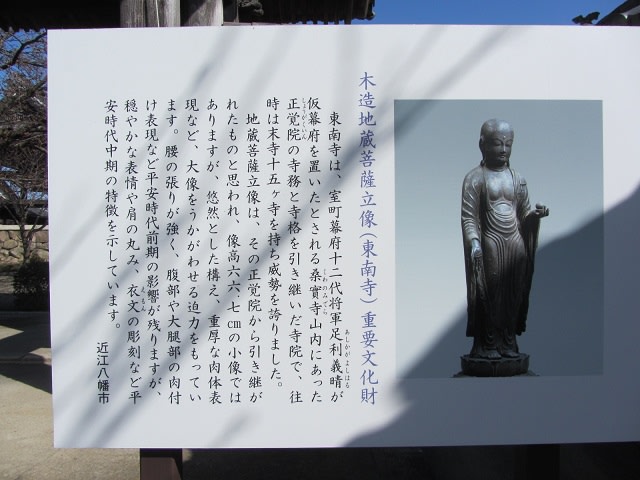焼津神社から教念寺へ。


こちらにも小泉八雲が散歩でよく訪れたそうで、「小泉八雲ゆかりの地」の案内板がありました。

母(二十八代忍晃の妻)が嫁にきて間もなくの頃、裏の畑で仕事をしている処へ乙吉が垣根越しに面を出して、「おばさん、八雲先生が来たので、泉水(池)の鯉を見せてくりよや」といった。
「ああええともサ」と返事すると、乙吉のほうがむしろ背の高い、目の大きい外人さんが入って来てニコニコ笑って頭を下げた。
そして、池の鯉を見たり、本堂の屋根から上に枝を覗かせている大松を眺めて「大変いい景色」と何度もほめていた。母が渋茶を汲んで出すと喜んですする様に飲んだ。茶碗を持つ手も型にはまっていて、この外人さんはきっと偉い人に違いないと思った。
(北山宏明著『小泉八雲と焼津』より)

江戸時代、徳川家康拝領の品が伝わっているそうです。



























 (中央が信長、右が信忠、左が信雄)
(中央が信長、右が信忠、左が信雄)