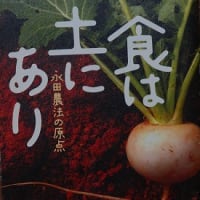民俗学の二人のパイオニアといえば、宮本常一・柳田国男があげられる。この二人を比較しながら宮本常一の先駆的で謙虚な人物像をシャープにあぶり出したのが、畑中章宏『今を生きる思想/宮本常一/歴史は庶民がつくる』(講談社現代新書、2023.5)の本だった。

柳田国男は民俗伝承・信仰を探求して日本の「心」を解明していった。宮本常一はフィールドワークを重視してそこに伝わる生産用具などの「もの」を手がかりに歴史の主体としての庶民像を探っていった。宮本は、農村・漁村・山里に生きる民衆の生産現場に行くことによって、従来の傍観的・客観的なデータや「民俗誌」ではなく、より民衆の生活点にねざした「生活誌」の視点が必要ではないかと提起していく。

彼の代表作の『忘れられた日本人』では、盲目の乞食から聞いた民話などを聞き取りしていくが、そうした人々の側に立って現在をあぶり出していく手法は従来にない視点だと畑中氏は評価する。したがって、現実のまち・むらづくりの方向性まで踏まえた聞き取りでもあった。佐渡の博物館設立、「鬼太鼓座」の設立、山古志村の錦鯉養殖、山口の猿回し復活などの支援にもかかわり、離島振興法の成立にも寄与してきた。

また、宮本は、戦後すぐに席捲していた搾取させられた民衆と支配者という構図・見方は一方的だとして、それではほんとうの民衆の姿はとらえられないとする。そのなかにはむしろ、「相互扶助による共同体と個人の持続的な営み」によって、互いにいたわりあい自分たちの世界を形づくってきたのではないかと提起し、「そういう民衆の生活はそのなかに入ってみなければわからない」とする。

そうした考え方の発想は、大杉栄が訳したクロポトキンの『相互扶助論』の影響があったという。その書のユートピア的な限界を踏まえながら、現状批判だけでなく生きる勇気を萌芽させるような発見が大切であることを学んだのではないかと著者は評価する。表紙の宮本常一の貌からもそんな息吹が感じられる。

宮本を支援してきた人物として、渋沢栄一の子・篤二の長男である渋沢敬三がいる。戦前は日銀や大蔵大臣などを歴任していたが、戦後は疲弊した経済の立て直しで活躍した財界人であり、KDDIの初代社長でもある。渋沢敬三は栄一の社会貢献を受け継いだのか、戦時下に「日本常民文化研究所」を創立して民俗学の発展に寄与していき、そこで働く宮本の調査研究の力量を高く評価していた。

そこで、渋沢が言った言葉を宮本は忘れなかったという。その内容は、「大事なことは主流にならぬこと、傍流でよく状況を見ていくこと」ということだった。主流に位置していると見落とすこともあり、その欠落を受け取ることで新たな世界が見えてくるというわけだ。これには説得力ある。

そこからか、宮本は「民具学」を提唱していく。つまり、その民具の即物的な説明だけでなく、そこから見えてくる民衆の生活周辺をくみ取るということでもある。その例として、狭山茶が発展していくルーツとして江戸にたまった空の茶壷をあげている。一つの民具に対してそこに庶民の精神的・生活的・技術的背景や思い入れを探求している。

そうした庶民への「まなざし」は、映画監督の木下恵介に通じるぬくもりを感じる。宮本常一の著作については断片的なものしか読んだことがない。したがって、この畑中章宏氏の入門書から読んだというわけだ。本書の後半に、宮本が上梓した著作の紹介をコメントしているのもきめ細かだ。宮本氏も畑中氏もわれわれ庶民にわかりやすく伝えようとしている心配りがありがたい。