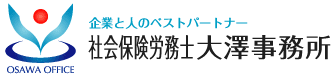低金利時代に突入した一時、退職金制度を廃止する動きが
盛んでしたが、近頃は、優秀な人材を確保するために、
退職金制度を新たに導入する企業も増えてきました。
企業が退職金制度を導入する際に重要な点は、
支給水準などの「制度設計」ですが、それと同じくらいに
重要なものに「資金をどのように準備するか」があります。
現在、企業が従業員のために「退職準備金」を社内で積み立てようと
しても(「退職引当金」)、損金算入は認められません。
従って、どのように退職金資金を準備するか(積み立てるか)を検討する
際には、できるだけ「損金算入」できる方法で準備するのが得策と
いえましょう。
この低金利時代に制度廃止が決まった厚生年金基金(優良基金除く)
や先年の「適格退職年金」廃止のように、「給付額をあらかじめ決める」ことの
「リスク」も、ある意味、肝に銘じるべきでしょう。
さて、退職金準備として、現在ある制度を挙げると、
① 確定給付企業年金(DB)
② 確定拠出企業年金(401k)
③ 特定退職金共済
④ 中小企業退職金共済
⑤ 厚生年金基金(廃止。優良基金は除く。)
⑥ 養老保険等
などとなります。
①と②はどちらかというと大企業向け、
③と④は、中小企業向け、
⑥は大企業でも中小企業でもどちらでもOK、といえます。
選択する際の判断基準について述べてみましょう。
最も重要なのは、「確定給付」か「確定拠出」かの選択です。
確定給付とは、あらかじめ給付額を確定するもの。
確定拠出とは、あらかじめ拠出金額を確定するものです。
あらかじめ給付額を確定するとは、運用結果により給付額(退職金額)
に不足金が出た場合は、企業が埋めなければならないということです。
反対に確定拠出の方は、確定するのは拠出金額だけですから、
企業は運用結果の給付額(退職金額)に責任が生じません。
資金に余裕のない中小企業は、確定拠出型が無難と申せましょう。
上記①~⑥を大雑把に分類すれば、
確定給付型は、①、⑤
確定拠出型は、②、③、④
などとなります。⑥は生命保険商品です。
ただし、①はキャッシュバランス・プランという確定給付型と
確定拠出型両方の機能を持った制度を選択することもできます。
「損金算入」の観点から見た場合、
①~⑤は、従業員のために掛けた拠出金は、全額損金算入できます。
しかし、⑥の養老保険の保険料は、2分の1が損金算入です。
従業員が退職金を受け取った場合の税制上の措置は、
①、②、⑤を年金として受け取る場合は公的年金等控除、一時金として
受け取る場合は退職所得。
③、④、⑥は退職所得(分割で受け取る場合は公的年金等控除)
の取り扱いになります。
 にほんブログ村
にほんブログ村
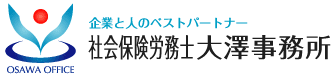
盛んでしたが、近頃は、優秀な人材を確保するために、
退職金制度を新たに導入する企業も増えてきました。
企業が退職金制度を導入する際に重要な点は、
支給水準などの「制度設計」ですが、それと同じくらいに
重要なものに「資金をどのように準備するか」があります。
現在、企業が従業員のために「退職準備金」を社内で積み立てようと
しても(「退職引当金」)、損金算入は認められません。
従って、どのように退職金資金を準備するか(積み立てるか)を検討する
際には、できるだけ「損金算入」できる方法で準備するのが得策と
いえましょう。
この低金利時代に制度廃止が決まった厚生年金基金(優良基金除く)
や先年の「適格退職年金」廃止のように、「給付額をあらかじめ決める」ことの
「リスク」も、ある意味、肝に銘じるべきでしょう。
さて、退職金準備として、現在ある制度を挙げると、
① 確定給付企業年金(DB)
② 確定拠出企業年金(401k)
③ 特定退職金共済
④ 中小企業退職金共済
⑤ 厚生年金基金(廃止。優良基金は除く。)
⑥ 養老保険等
などとなります。
①と②はどちらかというと大企業向け、
③と④は、中小企業向け、
⑥は大企業でも中小企業でもどちらでもOK、といえます。
選択する際の判断基準について述べてみましょう。
最も重要なのは、「確定給付」か「確定拠出」かの選択です。
確定給付とは、あらかじめ給付額を確定するもの。
確定拠出とは、あらかじめ拠出金額を確定するものです。
あらかじめ給付額を確定するとは、運用結果により給付額(退職金額)
に不足金が出た場合は、企業が埋めなければならないということです。
反対に確定拠出の方は、確定するのは拠出金額だけですから、
企業は運用結果の給付額(退職金額)に責任が生じません。
資金に余裕のない中小企業は、確定拠出型が無難と申せましょう。
上記①~⑥を大雑把に分類すれば、
確定給付型は、①、⑤
確定拠出型は、②、③、④
などとなります。⑥は生命保険商品です。
ただし、①はキャッシュバランス・プランという確定給付型と
確定拠出型両方の機能を持った制度を選択することもできます。
「損金算入」の観点から見た場合、
①~⑤は、従業員のために掛けた拠出金は、全額損金算入できます。
しかし、⑥の養老保険の保険料は、2分の1が損金算入です。
従業員が退職金を受け取った場合の税制上の措置は、
①、②、⑤を年金として受け取る場合は公的年金等控除、一時金として
受け取る場合は退職所得。
③、④、⑥は退職所得(分割で受け取る場合は公的年金等控除)
の取り扱いになります。