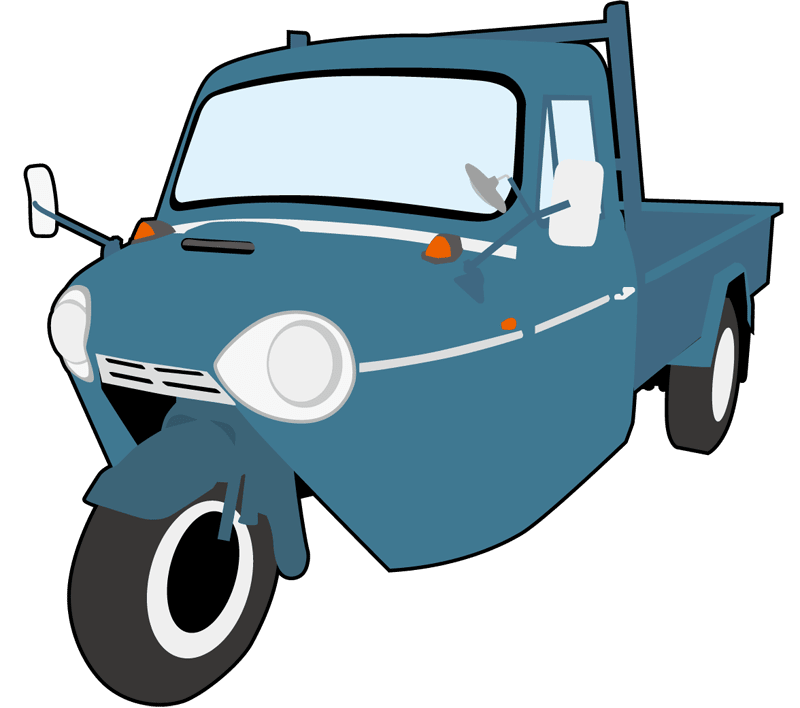テレビといえば当時は4本足。画面の前に拡大鏡のような物を下げて少しでも大きく見ようとしたものか。チャンネルはガチャガチャと回すもの。いまだにチャンネルを回すという言葉は残っています。見終われば画面の前には緞帳の様な幕が下ろされます。これもいつ頃まで続いたのでしょうか。幕をかけた事までは誰の記憶にもあるようですがかけなくなった時期については誰も記憶していない様です。

ご飯を炊くのは竈(へっつい)に羽釜ですね。洗濯は洗濯板。食事は卓袱台。星一徹が怒ってひっくり返すやつです。私が子供の頃味噌汁嫌いで知らぬふりして丸い卓袱台に味噌汁椀をひっくり返すので父親が卓袱台の縁を鉋で削り落そうとして木の節くれで手を切ったとは後年までよく聞かされたものです。

その後の近代的鉄筋コンクリートの住宅暮らし、煮炊きは初めはベランダに置いた石油コンロ。ガスコンロはそれから少ししてからです。調理台の下に10kgのプロパンガスボンベを置きます。どこの家も煮炊きのピークは夕方ですから途中でガスが無くなる。そうするとその頃電話は各家庭にありませんから近所の公衆電話まで走って行きガス屋さんにガスを注文します。

後年当時ガス販売店に勤めていた人から聞いたところ、その頃は日中は暇でゴロゴロしていて夕方になるとプロパンボンベを横倒しにして原付バイクの荷台に括り付けて走り回ったそうです。相当儲かったとのこと。ガスがメーター販売になったのは、このボンベ交換時残りのガスが入っているのに持っていかれた、不正行為だと主婦連に騒がれたのがきっかけだそうです。
生活を変えた家電品といえば洗濯機、冷蔵庫、電気掃除機でしょうか。もちろん洗濯機は脱水機なんてありません。手回しで絞るものです。冷蔵庫は冷凍庫なんてありません。せいぜい製氷室くらい。掃除機は、今も大して進化していないのではないでしょうか。サイクロン掃除機というものがあっても紙パックの方が良い所があるということですし。

ちなみにこれらの家電品の普及率は「カリスマ中内㓛とダイエーの戦後(佐野 眞一)」内の資料によれば下の表の通りです。
| 家電品 |
1957年普及率 |
1960年普及率 |
1965年普及率 |
1970年普及率 |
1975年普及率 |
| 電気洗濯機 |
20.2% |
45.5% |
78.1% |
92.1% |
97.7% |
| 電気冷蔵庫 |
2.8% |
15.7% |
68.7% |
92.5% |
97.3% |
| 電気掃除機 |
0% |
11.0% |
48.5% |
75.4% |
93.7% |
何れも70年代後半にはほとんどの家庭に普及しています。ただ電気掃除機だけは1965年時点でも50%以下。まだまだ箒とはたきの家庭がほとんどだったのでしょう。箒と塵取りの無いところはないでしょうけれどはたきは今では少なくなったかもしれません。前述のテレビと洗濯機、冷蔵庫が我が家にやってきた日の事は今でも覚えているのですが掃除機だけは全く記憶にありません。
家電品ではないですけれどもう一つはっきり覚えているのがイスとテーブル。昔のの観光地の食堂にあったような椅子もテーブルも脚が細いパイプでできたものです。それまでは畳の上で食事でしたから。近代的鉄筋コンクリートの住宅暮らしではキッチンらしきものがあり床はフローリングのようなもの。やはりここはイスとテーブルということである日家族で街中に一件だけあったデパートに出かけて注文してきました。届く当日は夕方テーブルが届くまで夕食は待ちます。待ちに待ったテーブルでの食事、そんな日の記憶がいまだに残っています。