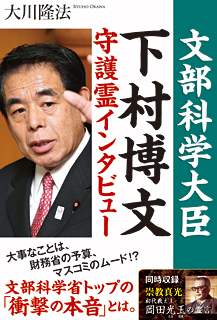理想国家日本の条件 さんより転載です。
ウイグルを弾圧する中国が、イスラム過激派の標的になる日

2014年5月3日土曜日 転載、させていただいた記事です
イスラム過激派は、火力でも兵力数でも劣るので、体制と戦うときは必ず息の長いゲリラ戦をする。
そして、不特定多数を巻き込んだテロを各地で引き起こして、当局の治安体制を嘲笑うような戦略を取る。
持久戦に持ち込むと、体制側は治安維持や兵士の駐屯のために多大なる出費を強いられる。
また長期に渡る厳しい締め付けは、市民を苛立たせる。
ゲリラ戦に巻き込まれると、体制側は経済面から気力を削られ、疲弊していく。
強化すれば何も起きないが兵士を駐屯させるので出費がかさむ。気を緩めばまたテロが起きる。
体制側は翻弄され、経済的に疲弊していく。1年や2年の話ではない。10年、20年の単位でそれが続く。
それほどの長期のテロ・ゲリラ戦で体制側を精神的に消耗させるのが、ゲリラ戦の戦法である。
アフガニスタンでは、旧ソ連やアメリカがそんな泥沼に引きずり込まれて、両大国ともそれで経済破綻に
見舞われている。最新鋭の軍は金がかかる。だから、持久戦が戦えない。
いつまでも終わらないテロが、大国を崩壊させる
アメリカのような強大な軍を持った国は、直接的な戦闘になれば負けることはない。
しかし、ベトナムや、アフガニスタンや、イラクのように、
いつまでも終わらないテロやゲリラ戦に足を取られると、
経済的な出費をまかない切れなくなって、アメリカ軍は撤退を余儀なくされる。
イスラム過激派は、すでに歴史の中で、大国の軍隊の弱点を見抜いているのだ。
「いつまでも終わらないテロが、大国を崩壊させる」と学んだ。
ロシアもアメリカも、そんな「終わらないテロ」で国力の弱体化を招いたが、中国はどうだろうか。
中国は今までイスラムとは接点がないように思われていたが、それも2009年までだ。
2009年7月、新疆ウイグル自治区では大規模な暴動が引き起こされたが、
これが中国当局とイスラムの初の大規模な衝突だった。
このときの衝突では1600人が負傷し、197人が死亡するという大惨事になったが、
重要なのは死者数ではない。
重要なのは、この暴動をきっかけに、世界のイスラム教徒は、中国政府がイスラムを
弾圧しているということを知ったことだった。
あまり知られていないが、ウイグル人たちは中東のイスラム国家に向けて、
自分たちが弾圧されていることを強く訴えていた。
イスラム教徒は、もともと国を超えたウンマ(イスラム共同体)で結びついており、
イスラム弾圧に対するニュースには敏感に反応する。
実際、2009年のウイグル人の訴えに対しても、アルカイダが呼応して、
「アフリカ北西部で働く中国人を対象にした報復を行う」と宣戦布告を出している。
イスラムのテロに巻き込まれる素地が生まれた
つまり、2009年から、中国はイスラム過激派を敵に回し、ウイグル人を通してイスラムのテロに
巻き込まれる素地が生まれたということだ。
その後、中国では激しい情報規制が行われているが、
それでもウイグル人の「テロ」が隠しきれなくなっている。
2010年にはアクス市で爆発物で7人が死亡するというテロが起きた。
2011年7月にはホータンで警察署が襲撃されている。
2012年にはカシュガルでテロが起きて13人が死亡した。
2013年には、武装集団と警察が銃撃戦を引き起こして警察官が15人死んだ。
このときに武装集団も殲滅したが、この報復として再び別の集団が警察署を襲いかかって
24人の警察官が死亡した。
2013年10月には、天安門にウイグル人の乗った車が暴走し、天安門前で炎上、
数十名の負傷者と死者5名が出ている。
そして、2014年3月1日には、雲南省昆明市で、新疆独立派が刃物を振り回して140人を
死傷させるというテロも起きている。
そして、2014年4月30日、ウルムチでウイグル人2名が駅構内で無差別に人々を
襲いかかって殺害し、最後に自爆するという事件を引き起こし、80名近くの死傷者を出している。
これは、習近平の新疆訪問に合わせたテロであるとされており、いよいよ中国政府はイスラムに
よる持久戦のテロに巻き込まれていることがはっきりしてきている。
まだまだ、ひとつひとつのテロの規模は小さく、それほど大したことではないように見えるかもしれない。
しかし、実は中国政府は、
こういったテロが連鎖的に広がっていくことを激しく恐れなければならない事情がある。
このままでは、中国内部が騒乱の嵐になっていく
中国政府が弾圧している少数民族は、ウイグル人だけではない。チベット人も、モンゴル人も弾圧している。
チベット人は非暴力で当局に対抗しており、各地で火だるまになって抵抗運動を引き起こしている。
(助けを求めるチベット人の炎の叫びを、私たちは拡散すべきだ)
自分たちが弾圧されていることを、自ら火をかぶって全世界に知らしめて中国政府を外圧から
崩壊させようとするのがチベット人の決死の戦略である。
欧米は人権問題を叫ぶ割には、中国が経済的に重要であるという理由で、チベット人の叫びを
無視する都合の良い国家だが、それでも中国政府の人権蹂躙は充分に伝わっている。
中国が経済的に重要な国ではなくなったとき、見捨てられた中国は少数民族によって崩壊させられる可能性がある。
これに合わせて国内のあちこちで格差や圧政に対抗する暴動が引き起こされている。
その数は年間20万件にも及ぶ。
少数民族の暴動やテロが押さえきれなくなると、中国内部が騒乱の嵐になっていく。
さらに中国は膨張政策を取っており、周辺国のすべてと激しい軋轢を引き起こしている。
日本も尖閣諸島問題で揺れているが、台湾も、ベトナムも、フィリピンも、
すべての国が中国の侵略に激しい不満を持っており、いったん中国が騒乱に見舞われたとしても、
同情する国はひとつもないだろう。
むしろ、中国共産党など消滅してしまうことを望むはずだ。
習近平は中国の抱える問題を解決できるような器ではない。
むしろ、ウイグル政策を見ても分かる通り、混乱を押さえようとして、
ますます混乱を生み出すような愚策を連発する。
そして、いつまでも終わらないテロによって疲弊していく。
経済も治安も環境も守れない習近平政権に対して、激しい不満が充満していき、
政権を揺るがすような大爆発が起きるのは時間の問題だ。


これ読んで、イスラム諸国の敵は、中国だと思っていたけど、・・・経済面からみると、わからない。。
中国の投資、中東紛争地域にも—西洋から覇権奪取へ
http://jp.ibtimes.com/articles/44061/20130513/511116.htm
中国、中東でより大きな役割を発揮
http://japanese.beijingreview.com.cn/yzds/txt/2014-02/18/content_597101.htm
長い間、中国の中東外交に対する外部の印象は「中庸」、「超脱」、「想像力に欠ける」というものであった。
しかし中東における中国の利益が増すに従って、中東外交において中国は最早あってもなくても
よい国ではなくなった。
積極的関与
2014年1月20日、中国外交部の王毅部長は北京で、シリア問題の政治的解決について5つの主張を示し、
シリアの各方面に、政治移行プロセスの具体的段取りと合理的スケジュールを早急に決め、相互承認をした
上で政治移行管理機関を設け、各方面の利益を配慮した「中間の道」を歩むよう呼びかけた。翌日、王毅部長は
スイス・モントルーに向かい、シリア問題第2回ジュネーブ会議に出席した。国連が主催したこの会議で、40余り
の国と地域組織の代表は、政治的解決の方向を支持する3点の共通認識に達した。
そこには中国の主張が十分に反映されていた。
2013年末以降、国連安全保障理事会と化学兵器禁止機関のシリア化学兵器廃棄に関する決議を実行するため、
中国、ロシア、デンマーク、ノルウェーの4カ国の軍艦が共同でシリア化学兵器海上輸送の護衛活動を展開している。
また中国はシリア及びヨルダン、トルコ、レバノン国内のシリア難民に、6回にわたって人道援助を行ってきた。
イラン核問題の外交解決プロセスでは、中国は「潤滑剤」の役割を果たし、「6+1」会談の建設的参加者である。
中国の代表は、「西側はイランに新たな制裁を行わない。イラン側は核計画の推進を停止する。双方は現状凍結を
ベースにまず相互信頼構築を目的とする段階的協定を締結し、全面協定締結に向けて地ならしをする」という
提案を真っ先に行った。
パレスチナ・イスラエル関係問題では、ずっと周りをうろうろするにとどまっていた中国は、より大きな役割を果たす
意欲を示している。2013年5月、中国はパレスチナ自治政府のアッバース大統領とイスラエルのネタニヤフ首相
の訪中をほとんど同時期に受け入れた。習近平主席はそれぞれと会見した際、パレスチナ・イスラエル関係問題
について4点の主張を行い、パレスチナ独立建国とパレスチナ・イスラエル両国の平和共存という正しい方向を
堅持すべきだと強調した。双方に「土地と平和の交換」原則を基礎として中東平和プロセスを全面的に推進するよう
呼びかけ、平和プロセス推進のために保障を提供するよう国際社会に求めた。
続き
http://japanese.beijingreview.com.cn/yzds/txt/2014-02/18/content_597101_2.htm
なぜイスラム過激派は中国でテロとか起こさないんですか?
中国政府はウイグル弾圧してますよね?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14115698669
アフガニスタンへの接近にも努力を惜しまない。
中国企業による石油、鉱物資源の採掘など同国重視の外交を進めている。
アフガニスタンにタリバン政権が復活すれば、新疆ウイグル自治区へ繋がる「アフガニスタン回廊」が
復活する。そうなれば夥しいイスラム戦士が山越えして、独立運動闘争を展開しかねないからだ。
「両国関係は極めて重要」とするカルザイ大統領は数回、北京を訪問している。