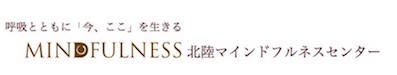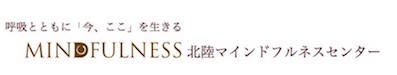私の仕事と絡んだ話です。
体制の整ったコールセンターでは、電話応対者の応対品質を向上し、顧客満足(CS)を高める為に、「トレーナー」や「クオリティ・アシュアランス」といった教育専任者が、お客様との通話録音テープを聴き、電話応対者の強みや弱みを抽出した後、個人面談をするという仕組みができています。
その時に、今後のお客様とのコミュニケーション上の課題を設定し、どんな風に課題を達成していくか、面談をして決め、その後、応対の品質を高める為の、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを継続的に回していきます。
そんな仕事をしてきた私は、面談後、数週間経った頃、
「○○さん、あの課題、今、何合目までキテる?」
山登りに例えて、課題を達成した状態を10合目として、全くできていない時を0合目とした時に、今の立ち位置はどのあたりなのかということを、立ち話的に聞いては、コミュニケーションを取っていました。
「○○さん、あの課題、今、どんな感じ?」
と聞いたところで「まあまあです」「全然ダメですぅ」「あんまり意識できてないです」「ぼちぼちです」なんて漠然とした抽象的な言葉を引き出しても、残念ながらあまり意味がないんですもん。
仕事なので課題達成に向けて、自分を客観的に振り返り、10合目に到達するには何がどう足りないのかを認識させ、努力を促します。しかし、私は、多少せっかちで、荒っぽいです。
「1番いいときの状態を10点として、最悪の状態を0点とした時、今、何点ですか?」
絶望のどん底にいたり、解決の糸口が見えない暗闇の中にいたクライエントへのカウンセリングにおいて、SFA:Solution-Focused Approachでも同じような質問をします。
先の質問も含めて、この手の質問を「スケーリング・クエスチョン」といいます。
どんなにつらい状態、やりきれない状態、パツパツな状態でも数値化してみて「6点ぐらいかなぁ」と応えることによって、「私って意外とOKじゃん」と気づくこともできます。
もし、「1点です」「2点です」と言われても、ここがSFAの素晴らしくポジティブなところなのですが、「0点」との差異に着目をするのですよ・・・。
「その1点分(2点分)って、いったい何なんですか?」
変化は日々起きているがゆえに、ここでも「差異」に気づくことが大事と考えるのです。
私の仕事の中でも、もう少しこの「差異」の部分への着目を丁寧にする必要があるのかもしれません。
例えば、「7合目にいます」に言われた時、これまでの私は10合目を目指して欲しいと望むがゆえに、「その3合目分を登り切るには何が必要なの?」といきなり「3つ分」の「問題」に着目してきましたが、
「7合目から8合目になっている時って、今とどんなふうに違ってるのかな?」
「7合目から8合目になった時ってどんな状態なの?」
「1つ分」の「解決に近づく具体的な行動」を問うことが、大事とかも・・・と気づきました。
私の仕事のドメインは「教育」です。
教育には「熱意」と「忍耐」が必要だと思っています。
今までは多少荒っぽく、ショートカット気味だった面談やフィードバックも、SFAのエッセンスでキメ細やかに行うことで、より効果的なものにしていきたいと思いました。
問題に焦点を当てるか、解決に焦点を当てるか、どちらでなければならないとは思いません。相手のエネルギーの状態を理解した上でベストの関わりを持ちたいと思います。
そんな創意工夫が自分のエネルギーの源泉です。
教育には熱意と忍耐が必要です・・・何か感じたら久しぶりによろしく。
↓

最近、生活者としてもうちょっとまじめに書いた方がいいのかと思っています。
→まあまあ「のほほん」なBlog「
Breathe&Stretchな暮らし」