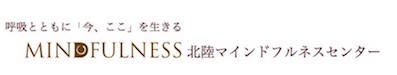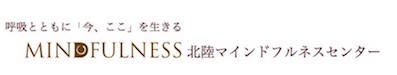新人研修が、ほぼ全開のエネルギーで進行しつつあります。
社外講師となり3年目の春です。
1年毎に、新人に教えることも変化してきているように思います。
私は、決して「厳し目の講師」に分類されている訳ではありませんが、新人の皆さんを叱る機会も増えています。
講師は接客業というスタンスの私は、新人研修以外の研修では、お客様を叱ることなどありません。
また、独立してからの自分には、部下・後輩もいませんし、子のいない自分にとっては、人を叱ったり注意をしたりする習慣もありません。
そして何よりも、常に「他人を喜ばせろ」という囚われを持っている自分にとって、叱るということは、特別な行為です。
しかしながら、まだ学生気分の抜けきらない新人に対して、社会人としてふさわしくない考え方や行動をしている時、それを放置し、無関心でいることは愛情でも何でもありません。
「他人を喜ばせて、人に好かれていたい」などという、私利私欲に、私自身が囚われている場合でもありません。
私にとって叱ることは、
相手の良くない言動の事実を冷静に伝えて、それが結果的に相手の評価を下げたり、信頼を損ねるものであることを「心配している」のだ、ということを「本気」で伝えるコミュニケーションであると思ってきました。
本気であるが故に、力が入ることもありましょう。
大事なお客様であると思えば思うほど、上っ面を撫でたような適当な言葉で、些末な対処方法だけを教えるなんてことはできません。
叱ると決めたら、事前に叱る内容を冷静に整理して、叱り方をシミュレーションすることも必要な訳で、私は、皆さんが思っている以上に真面目に叱っているつもりです。
新人研修で教えることの大半は、当たり前のことばかりです。
でも、理解した内容がすぐ実践できるとは限りません。
私自身も、その当たり前のことが、当たり前のようにできていないことを痛感し、いまだに多少なりとも失敗もするのです。
だからこそ、若手を心配するのです。
抜けきれない学生気分のまま、中途半端な気持ちで仕事に向かい合っていた時に、上司から「目の色、変えて出直してこい」って言われた私。
お客様からのクレームにまともな対応もできず、嫌な思いや情けない思いをしてきた私。
自分の価値で勝手な判断や勝手なルールをつくり、新しい組織の大切に考える価値をいつまでも理解しようとしなかった転職したての頃の私。
失敗を失敗と認められずに、誰かのせいにして始まる言い訳に「能書きたれんと、まずはあやまらんかい(関西弁)」と一喝された私。
私自身は、叱られた経験はそれほど多くありません。
でも、今思えば、叱ってくれた数少ない上司のインパクトのある言葉は今でも自分にとっての「ありがたい戒め」になっています。
自分の中に今もいる「ダメな自分」を、受講者の中に見いだした時、自分に向かって問うかのように語り掛けている自分がいます。
私は、感情的になることはありません。
相手に伝わるような温度の思いは、自分で意図的に生み出さなければなりません。
ミスはに誰だって起きるもの。
時に、ミスは意に反して起き、誤った行動は無意識で軽率です。
ミスの再発防止や挽回する未来思考はもちろん必要なことです。
ETC型の新人なら、当たり障りなく謝って、高い学習能力で、スマートに改善することもできるでしょう。
しかし、叱られた側にとって、忘れてはいけないのは素直に詫び、指摘してくれたことに感謝すること。
そんな真剣なやりとりで、通じ合うことができた時のなんだか「ヤバイ泣きそう」的な震え。
「何を正し、何をわかちあうか」
このことが大事であることを、私に教えてくれたもう2度と会えないかもしれない受講者のみなさん、本当にありがとうございます。
印象に残る研修がまた1つ増えました。
プチっとお願いします。
↓