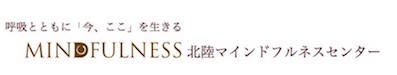マインドフルネス心理療法での拠点「北陸マインドフルネスセンター」開設。
マインドフルネス心理療法は、第3世代の認知行動療法で、日本ではまだ新しいものです。
「北陸マインドフルネスセンター」ではマインドフルネス心理療法のうちの「自己洞察瞑想療法(SIMT)」で
うつ・不安障害の方を中心としたサポートを行っていきます(福井・石川・富山)。
このまま何もしないでいるとメンタルヘルスが悪化し、仕事や家事に支障を来しそうな予感のある方や、
通院しながら急性期は乗り越えたかなと思われている方、お薬を減らして行く過程にある方で、
なるべく自分の力で乗り越えて行きたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。⇒こちら
(病状によっては効果が確認されていないケースがございます。診断を受けていらっしゃる方は必ず事前に
お知らせください)
マインドフルネスについて記事更新中。 こちらのブログもぜひお立ち寄りください!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
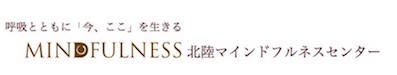
「北陸マインドフルネスセンター」ではマインドフルネス心理療法のうちの「自己洞察瞑想療法(SIMT)」で
うつ・不安障害の方を中心としたサポートを行っていきます(福井・石川・富山)。
このまま何もしないでいるとメンタルヘルスが悪化し、仕事や家事に支障を来しそうな予感のある方や、
通院しながら急性期は乗り越えたかなと思われている方、お薬を減らして行く過程にある方で、
なるべく自分の力で乗り越えて行きたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。⇒こちら
(病状によっては効果が確認されていないケースがございます。診断を受けていらっしゃる方は必ず事前に
お知らせください)
マインドフルネスについて記事更新中。 こちらのブログもぜひお立ち寄りください!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓