
この絵は、中山忠彦画伯の「サッフォー」と題する絵を模写したものです。
やはりパステル画ですが、20号(72.7 x 50.0cm)くらいの大きな絵です。
(実際はもっと明るい色彩の絵なのですが、暗いところでフラッシュを焚かず
に撮ったので、こんな色合いになってしまいました。)
模写に使用した図録、それは月刊の美術雑誌に掲載されていたのですが、
ハガキの半分くらいの大きさで、それを拡大して仕上げたのですが、
昨年、日本橋の高島屋で開催された「中山忠彦 永遠の女神展」に展示
されてあった実物(油彩)は、もっと大きくて80号(145.5×97.0cm)もありました。
それにしても、30代前半は根気もあったし、目も良かった。今ではとても
無理です。
中山画伯は、白日会の伊藤清永に師事しましたので、この頃(S47)の作品には
(伊藤清永はルノワールに師事していたので)その影響が多分に現れています。
絵のモデルは、作品の大半がそうであるように、画伯の夫人の良江さんです。
画伯も若い頃(このとき37歳)には未だ貧しくて、純白の薄着の衣裳は夫人の
手作りに依るものですし、右手が軽く握るハープは鏡の縁を利用したそうです。
僕は、その純白のドレスにピンクの帯、それと緑の背景といった色彩のコント
ラストに惹かれたのですが、顔だけは意識するしないに関わらず、僕好みの
ものになってしまいました。(画伯の絵では、奥様の凛とした佇まいがその
表情によく現れているのですが、僕の方は少し妖艶です。 )
)
中山画伯が何故「サッフォー」と題したのか全くもって存じませんが、サッフォー
は紀元前6世紀頃に活躍した古代ギリシアの女流詩人です。
恋愛を扱った作品(その中には女友達を讃美したものもありました)が多かった
こともあって、後になってのことですが、キリスト教の隆盛とともに異教的頽廃的
とされ、有り難くない代名詞を戴くことになります。
「サフィスト」といっても分からないかも知れませんが、彼女の出身地である
レスボス島からとった「レスビアン」なら分かりますよね。
僕が中山画伯を知る切っ掛けとなったのは、赤坂にあった本社ビルのロビーに画伯の
絵が飾られてあったからです。「サッフォー」より少し前(S41)に制作された「椅子
に倚(よ)る」という絵で、夫人と結婚した翌年の、そして夫人をモデルにした三作目
の、そして第9回新日展に見事入選した、作品です。(この絵、珍しくルノワール風
ではなくて、小磯良平風です。)
同じ題名の作品がもう一点ありますが、本社にあったのは、椅子に座った夫人の衣裳
が薄地の純白の半袖ブラウスに、胸のところに黒い結び紐の付いた袖無しの赤い服
(何と呼ぶのか分からないのですが、「THE SOUND OF MUSiC」のレコードジャケット
のマリアの服装に似た物です。前年に映画が公開されていますので、触発された可能
性はありますね)、そして刺繍の入ったイエロー系のエプロンを着けたもので、背景
がグレーで、正面ではなくて斜め45°に向いた構図の作品です。
この衣裳も知人から借りたそうですし、エプロンは鏡掛けを代用したそうです。
この絵、社友から寄贈されたものとばかり思っていたのですが、そのうちに姿を消した
ところを見ると、借り受けていただけだったのですね。現在は、ウッドワン美術館蔵と
なっています。
借り物尽くしのお話でした。
ブログトップへ戻る












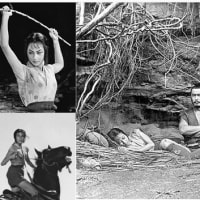
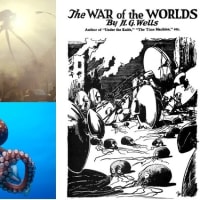






水彩は、手軽ですが、塗り重ねに不向きであったり、
発色の面でも物足らなさを感じます。
油彩は、発色も良いし、重ね塗りも出来て、僕のように
アレコレ手直ししたがる往生際の悪い者にとっては有難
いものですが、不注意で服などに付いた絵の具を落すの
が大変であったり、使用した絵筆やパレットなどの後片
付けが面倒であったりして、僕のようなウッカリ者の面
倒臭がり屋は、つい敬遠し勝ちです。
それにどちらも下の色が乾かないと色を重ねることが
出来ないので、僕のようなセッカチな者にとっては途中
で戦意喪失となり兼ねません。
その点、パステルは子供のときから使い慣れているクレ
ヨンやクレパスのように(それらに比べて多様な表現が
可能ですが)簡単に扱えて、油彩よりも発色が良く、重ね
塗り(も可能ですが)などせずに済むほどに色数が多く、
その上、あちこち汚しても水で洗い落せるのですから、
まさに僕のために天が与え賜うたような絵の具だったわけ
です。
大丈夫というところが、パステル画の魅力でもあります。
僕がパステル画に惹かれる直接の切っ掛けとなったのは、
パステル画の巨匠でもあったドガの「舞台の踊り子」と
いう有名な絵でした。
それから実際にパステルを手にするまで時間がかかりまし
たが、30代に入ってから意を決して、道具を一式揃え
ました。
まずは用紙です。
パステルは、水で溶いた顔料をアラビアゴムなどの薄い
溶液で煉って棒状に固めて乾燥させたものですので、定着
力が弱いのが特徴です。
ですから、紙にゴシゴシ擦り付けて着色させる必要があり
ます。そのためには、ケント紙のように表面がツルツル
したものではなくて、表面の凸凹が目立つ、目の粗い紙を
使用します。
パステル用紙には、沢山の色数のものがあります。
ルノワールは、肌を描くときの下地に赤を引いて温かみの
ある色調を作り出していますが、パステルでは基本的には
このようなことは出来ませんので、下地として赤い紙を用
いたりします。
同じ色を使って絵を描いても、下地となる紙の色によって
まったく趣の異なる絵に仕上がりますので、テーマに応じた
色の紙(目の粗さも風合いに関係しますが、ここではカット)
を選ぶことが肝心です。
僕は、ソフトパステル、ハードパステル、パステル鉛筆を
使用しています。今は150色もあるソフトパステルを使用
していますが、未だに色に迷うほどで、初めて学ぶひとは
36色のもので良いと思います。
ソフトパステルだけでも構わないのですが、エッジの効いた
強い線を描いたりする場合にハードパステルを用いたりします。
パステル鉛筆は、繊細な線など細密な表現を必要とするとき
に使用します。(普通の色鉛筆だと、そこだけがツルツルと
光ってしまいます。
さて筆ですが、まず10本の指が筆代わりになります。紙に
描いたパステルの粉末を、ゴシゴシと紙に擦り込むのが指の
役目です。汗腺から滲み出る油まじりの水分が役立つのか
どうかまでは存じませんが、ボカシなどの色調を上手く出す
ことができます。塗る箇所の広さなどに応じて親指を使ったり
小指を使ったり、また色が混じらないようにあれやこれやの
指を使用したりします。
指だけでも良いのですが、擦筆(さっぴつ)という用具も
使ったりします。
擦筆は、紙を何重にも巻いたもので、先が尖っています。
硬い材質のものと、軟らかいものとがあって、前者は強い線
を描くときなどに用いて、後者は広い面をボカスように塗る
場合などに使用します。どちらも細いものから太いものまで
何種類もあって、塗り込む線・面の違いに応じて使い分けます。
パステル画の便利なところは、描き損じても、消しゴムで簡単
に消すことができる点です。
それだけでなく、ハイライトなどの効果を出す場合にも消しゴム
を使ったりします。(僕の場合には、殆どが前者で使用していま
すが。)
フィクサチーフというスプレータイプの定着液を使用するひとも
います。
指や擦筆などでゴシゴシ擦り込んでも、それでも定着力は弱く、
何かに触れただけで、その箇所は擦れてしまって、描き直さねば
ならなくなったりします。そういったことを防ぐために定着液を
用いるのですが、発色が悪くなったりして、折角のパステルカラー
が台無しになったりすることがあるので、僕は使っていません。
(厚塗りなど、色を塗り重ねる場合に使用することもあるようです。)
ひとつは、大きな作品を制作する場合など、沢山のパステル粉末が
飛び交いますので、咽喉を痛めたりします。特に冬場は部屋を閉め
切っての制作になりますので、息苦しくともマスクは必需品になり
ます。
いまひとつは、作品の保存方法です。制作中は、画板にそのまま画鋲
で留めて、何処かに立て掛けて置けばよいのですが、完成した作品は
硝子の嵌め込まれた額縁に入れて飾ることが出来れば、それに越した
ことは無いのですが、全てそうすることは出来ません。そのような
場合には、パラフィン紙で表面を覆って、カルトンなどに挟んで、
擦れないように保存しなければなりません。
このページに臆面も無く載せた「サッフォー」ですが、額縁に入れて
あるので、硝子に外光や室内の明かりが映ったりするので暗いところで、
しかもフラッシュの光も映ってしまいますので、それも使用せずに
撮りました。それでも薄明かりが差していますので、僕のカメラを
持って差し出した手がちらっと写ってしまいました。額縁から絵を
取り出して撮れば良いのですが、そのときに擦れたりするのが怖いの
です。育てるのは比較的に楽なのですが、成人してからが大変なんです、
ぱすてるくんは。
誤りがあったので訂正します。
もうじきNHK「龍馬伝」が始まりますし、加尾の
出番も早そうなので、「あれっ違うじゃん」なんて
思われるのも癪に障りますし・・・。
加尾が山内容堂の妹友姫に付き添って郷里を後にする
ときに、龍馬とその友人が寄せ書きして加尾に贈った
袱紗。その中の和歌「あらし山 花にこころの とまる
とも 馴れしみ国の 春なわすれそ」を加尾本人のもの
としましたが、「春なわすれそ」は、「な」(副詞)と
「そ」(終助詞)とが呼応して禁止の意味を表しますので、
「(生まれ育った土佐の)春を忘れないでください」と
なり、加尾への送辞としか考えようがありません。
第一、送別品に、贈られた本人が書き込む筈は無いです
ものね。
では誰が、となりますが、署名に「八本こ(やほこ)」と
ありますので、「八矛」の号を持つ、宮崎十右衛門と
考えられています。
しっかり「胴掛」と書いていますしね。
寸法が縦36cm×横32cmもありますし、それを二つ折り
(36×16)にして使用するように折癖もついているそう
です。
胴掛は三味線を弾くときに、三味線の胴の下に敷いて、
撥を持つ手のすべりを止めるためのものですが、加尾は
一絃琴(いちげんきん。長さ三尺六寸、つまり1m余り
の、桐や杉で作った胴に一本の絃を張った琴)を習って
いたので、そちらでも使用するものなのかも知れません。
吉村三太、そして宮崎十右衛門の四人(と思えます)。
清平の生年は不詳なのですが、弟の望月亀弥太が天保9年
生まれですし、龍馬の手紙には清平のことを「大兄」と
してありますので、龍馬(天保6年生まれ)よりも年長
だけども、それほど歳は離れていないと思います。
内蔵太(くらた)は天保12年生まれ、三太は天保7年
生まれ、そして十右衛門は生年不詳ですが皆とはそんな
に歳が離れていないように思います。
裏面の右半分には三太、龍馬の順で、そして十右衛門の
和歌は裏面の左半分に後で縫い付けてあります。
年齢の順でないことは明らかで、皆軽格の家柄ですが、
清平は上士(山内侍)と下士(長曾我部侍。坂本家の
ような新規取立て郷士も含まれる。郷士以下の家格)との
間に位置する白札であって、他の四人よりも家格は高い
のですが、内蔵太は、三太や十右衛門の家格である用人
よりも低い徒歩(かち)ですので、そういった基準でも
なさそうです。
の兄権平や姉乙女、そして平井加尾も就いていた)ので、
その関係なのかも知れませんね。
そして、その門人仲間が芸歴に応じて順番に書き込んだ
のかも。
姉を訪ねて遣って来る加尾に恋慕の念を寄せた龍馬が、
頻繁に会えるようにと入門したのかも知れません。
そういったアグレッシブさが龍馬の持ち味ですし。
さて、この胴掛を渡すシーン、「龍馬伝」では用意されて
いるのかしらん。