動物の愛と感謝2

(lion-man.gif)

(elephant-man.gif)

(chick-boy.gif)

(parrot-womn.gif)
すべての動画を表示するまで
時間がかかります。
表示されない動画があったらブラウザの
リフレッシュボタンを
クリックしてください。

(betty01.jpg)
デンマンさん。。。、今日も動物たちの愛情と感謝の映像を取り上げるのですかァ〜?

(kato3.gif)
そうです。。。ベティさんが見ても おもわず心温まったり、笑ってしまったり、ビックリしたりするような動物が出てきます。。。じゃあ、まず次の動画を見てください。。。

(dog-woman.gif)

あらっ。。。ワンワンちゃんが、この女性に ずいぶん、うれしそうに懐(なつ)いていますわねぇ〜。。。どうして、こんなに嬉しそうにしているのですか?

この女性は兵士なんですよ。。。軍務期間が終わって休暇で家に帰ったところをこのワンちゃんと一緒に迎えに来た人と再会したというわけです。。。1年以上会ってなかったので、このワンちゃんは飼い主の女性に再会して、嬉しさを隠せないのです。。。

(parrot-womn.gif)

これはオウムですか?

そうです。。。オウムの仲間はオーストラレーシアに分布して、フィリピン、ワラセアのインドネシア諸島東部からニューギニア島、ソロモン諸島、オーストラリアに及ぶ地域に生息しているのですよ。。。。英語名は「Cockatoo」。。。マレー語名の「kaka(k)ktua」に由来しているそうです。。。(kaka「インコ」+ tuwah、または kaka「姉妹」+ tua「年上」)。
どうして、この鳥はこの女性に会って喜んでいるのですか?
あのねぇ〜、この女性はペットショップを経営してたんだけれど、倒産してしまったのです。。。可愛がっていた このオウムを友人に頼んで、暫くの間面倒を見てもらっていたのですよ。。。やっとお金の目処(めど)がついて、またペットショップを始めたのです。。。それで このオウムを久しぶりに引き取ったというわけです。
このオウムも売り物ですか?
いや。。。これだけ二人のキヅナができてしまったら、この女性は、このオウムを手放すことができないでしょう。。。
オウム目

(taihaku-oumu.jpg)
インコ目もしくはオウム目(Psittaciformes)は、鳥綱に分類される目。
日本産鳥類目録 改訂第7版などでは本目をインコ目としている。
一方で世界中の鳥類に和名をあてた世界鳥類和名辞典では本目をオウム目としている。
オウム目に固有の特徴として、強靭な湾曲した嘴、直立した姿勢、強力な脚、そして鉤爪をもった対趾足の趾(あしゆび)などがあげられる。
ほとんどのインコ科の鳥は全身が主に緑色で、部分的にほかの明るい色をしているが、中には多彩な色をした種類もある。
オウム科の鳥ではその色彩はほとんど白からおおむね黒の範囲に及び、可動する羽根の冠(冠羽)をその頭頂部にもつ。
ほとんどのオウム目の鳥は性的単型であるか最小限の性的二形である。
インコはカラス、カケス、カササギと並んで最も知能の高い鳥の一つであり、またその人の言葉をまねする能力からペットとして高い人気を博している。
ほとんどのインコの食餌のなかで最も重要な構成要素は、種子、ナッツ、果実、花粉とその他の植物性の素材で、いくつかの種は昆虫や小動物も食べる。
またヒインコは花や柔らかい果実から蜜や果汁を採食することに特化している。
ほとんどすべてのインコが木の洞(飼育下では巣箱)に巣をかけ、白い卵をうみ、晩成の雛を孵す。
現存する種類では、その大きさはアオボウシケラインコ(Buff-faced Pygmy-parrot)の10g以下、8cmからスミレコンゴウインコ(Hyacinth Macaw)の体長1m、フクロウオウム(Kakapo)の体重4kgにまで及ぶ。
かれらは体長という項目に関して最も変化に富んだ分類目の鳥である。
並外れたインコとしては性的二型性のオオハナインコ(Eclectus、雄は緑色で雌は赤色である)、飛行せずレック型繁殖行動を行うフクロウオウムなどがあげられる。
カカ、ミヤマオウム、テンジクバタンはとりわけ湾曲の強い上嘴をもつ。
生息範囲と分布
インコはオーストラリアや太平洋の島嶼、インド、東南アジア、北アメリカの南部地域、南アメリカおよびアフリカを含むすべての熱帯および亜熱帯の大陸で見ることができる。
一部のカリブ海と太平洋の島々には固有種が存在する。
圧倒的多数のインコの種がオーストラレーシアと南アメリカに由来する。
複数の種類のインコが南アメリカとニュージーランドの冷涼な温帯地方に進出している。
一種類、カロライナインコが北アメリカの温帯に生息していたが20世紀の初期に狩り尽くされて絶滅した。
数多くの種が温暖な気候の地域に移入されて安定個体群を確立している。
オキナインコ(Monk Parakeet)は現在では合衆国の15の州で繁殖している。
いくつかのインコの種はまったくの定着性であったり、また完全な渡り鳥であったりするが、大多数はその二つの間のどこかに落ち着いて、十分には解明されていない地域間の移動を行ったり、また種類によっては完全に非定着な生活様式を採用したりしている。
繁殖
いくつかの例外はあるが、インコは一雄一雌で繁殖を行い、なんらかの空洞に営巣し、その営巣地以外にはなわばりを設定しない 。
オキナインコと Agapornis属(ラブバード)のうちの5種のみが樹上に巣を編み、3種のオーストラリアとニュージーランドのキジインコ(Pezoporus wallicus、Ground Parrot)が地上に巣を作る。
これ以外のすべてのインコは、木の洞か、そうでなければ崖や河岸に掘られた巣穴や、シロアリの巣ないし地上に掘られた穴といった空洞に巣を作る。
集団で営巣する種もあり、イワインコのばあい、優に70,000羽を超えるコロニーを形成する。
インコの卵は白である。
ほとんどの種で雌が抱卵をすべて受け持つが、いくつかの種では雌雄で分担して抱卵が行われる。
雌は抱卵期のほとんどすべてを巣にとどまって過ごし、雄によって給餌される。
コンゴウインコやその他の大型のインコはK選択を採用する種の典型で、低い繁殖率を示す。
彼らは成熟するまでに数年を要し、年間に1羽ないし非常に少ない数の子を育てるが、必ずしも毎年繁殖を行うとは限らない場合もある。
知能
飼育されている個体による研究から、どの種類の鳥がもっとも知能が高いかについての知見がもたらされている。
ヨウム(African Grey Parrot)による研究から、インコにはヒトの言葉を物まねすることができるという特徴があるだけではなく、中には単語をその意味にしたがって結びつけて簡単なセンテンスを作ることができるものもあることが明らかになった。
カラス・ワタリガラス・カケスなどのカラス科鳥類と並んでインコはもっとも知能の高い鳥であると考えられている。
事実、インコやカラス科の鳥の頭脳と体の大きさの比率は高等霊長類のそれに匹敵する。
鳥類の想定された知的能力に対する反論の一つは、鳥類が相対的に小さな大脳皮質しか持っていないということである。
大脳皮質は、ほかの動物においては知能をつかさどると考えられている脳の一部分である。
しかしながら、鳥類は脳の異なった部分、すなわち吻側部内側新線条体/上位線条体をその知性の中枢として使っていると見られている。
研究によりそれらの種がもっとも大きな上位線条体をもっている傾向があるということが明らかになったが、これは意外なことではない。
また、カリフォルニア州立大学サンディエゴ分校の神経科学者である Dr. Harvey と J. Karten は鳥類の生理学の研究により、鳥類の脳の下位部分がわれわれのそれに似通っていることを明らかにした。
インコはその知能を言語を使う能力に関する科学的テストによって示したのみならず、たとえばミヤマオウムなどの一部の種類のインコでは道具を使うことに長けており、これでパズルを解くことができるということを示した。
物まねと会話をする能力
多くの種類のインコがヒトの言葉やその他の音のものまねをすることができる。
そしてアイリーン・ペッパーバーグの研究結果によってアレックスという名のヨウムが高い学習能力を持っていたことが示されている。
アレックスは言葉を使って対象を識別し、それらを説明し、その数を数えるように訓練された。
さらには「赤い四角はいくつありますか?」といった複雑な質問に80%以上の正確さで答えることすらできた。
第二の例はN'kisiという名の別のヨウムである。
N'kisiは1,000語近い語彙をもち、それを正しい文脈で使うだけではなく、正しい時制で作文できる能力を持っていることを示した。
インコには声帯がなく、このため音は分岐した気管の口全体に空気を噴出させることによって作り出される。
異なった音は気管の深さと形状を変化させることによって作り出される。
したがって話すインコは、実際にはさまざまなバリエーションでさえずっているということになる。
ヨウム(Congo African Grey Parrots、CAG)は、その"話す"能力でよく知られているが、これはおそらく強靭な気管かあるいはその精密なコントロールに依っているのであろう。
しかしこのことはオカメインコ(オカメインコの話す能力は一般にあまり知られていない)がヨウムよりもたくさんの語彙をもつことができるということを意味するわけではない。
この能力によって古代から現在に至るまで、インコはペットとして珍重されてきた。
ペルシャのルーミーによって1250年に書かれた"精神的マスナウィー"の中で、筆者はインコを話すように訓練する古代の方法について述べている。

(okame-inko2.jpg)
ペットのオカメインコ
インコは単語の意味を理解することなく話すことを教えられます。
その方法はインコとトレーナーの間に鏡を置くことです。
鏡の背後に隠れたトレーナーは単語を口にします。
そしてインコは鏡に映った彼自身の姿を見て、もう一羽のインコが話していると思い鏡の背後のトレーナーが口にした全ての言葉を模倣します。
ペットとしてのインコ
そのヒトと親しくまじわる愛らしい性質、高い知能、鮮やかな色彩と言葉をまねする能力からインコはペットとして高い人気を得ており、歴史的にもさまざまな文化において飼育されてきた。
1世紀の初めの大プリニウス(ガイウス・プリニウス・セクンドゥス)の記録によれば、ヨーロッパ人はホンセイインコ(Rose-ringed Parakeet 、ring-necked parrot とも)と記述の一致する鳥を飼っていた。
何千年ものあいだ、かれらはその美しさと話す能力から珍重されてきたが、飼育することの困難さもまた証明されてきた。
たとえば筆者 Wolfgang de Grahl は1987年の彼の著作"The Grey Parrot" の中で、真水が有害であると考えて、船積みされたインコにコーヒー以外を飲むことを許さなかった輸入業者がいたこと、そしてその行為が輸送中の生存率を向上させると信じていたことを取り上げている(今日ではコーヒーに含まれるカフェインが鳥に有害であるということが一般にみとめられている)。
ペットのインコは鳥かごや鳥小屋で飼われるだろう。
しかし一般にヒトに慣れたインコは、日常的に外に出てスタンドやジムにとまることが許されなければならない。
地域によってインコは捕獲された野生種かもしれないし、飼育下の人工繁殖による個体かもしれないが、野生インコの存在しない大部分の地域では人工繁殖による個体である。
ペットとして一般的に飼育されているインコの種類には、コニュア、コンゴウインコ、ボウシインコ、白色オウム、ヨウム、ラブバード、オカメインコ、セキセイインコ、オオハナインコ、シロハラインコ、パラキート、アケボノインコ やハネナガインコなどがある。
その気質、騒音の大きさ、物まねの能力、ヒトに触れられることへの好悪、そして世話の方法などは種類によって異なるが、しかしそのインコがどのように育てられたかということが、一般にその個性に大きな影響を与える。
インコはその美しさと高い知能、そしてヒトと親しくまじわる性質のためペットとしての人気が高い。
1992年に、新聞USAトゥデイ紙は、アメリカ合衆国だけで1100万羽の鳥がペットとして飼われており、その多くがインコであると発表した。
あらゆる種類のペットバードのなかでも家畜化されているセキセイインコや一般的なパラキート、小型のインコなどがもっともポピュラーである。
インコは優れたコンパニオンアニマルになることができ、その飼い主と近しい愛情深い絆を形作ることができる。
しかしながら彼らは決して飼うことの容易なペットではない。
その健康的な生活のためには給餌やグルーミング、獣医の診察、訓練、おもちゃを与えることによる環境強化、運動、そしてほかのインコやヒトとの社会的インタラクションなどが必要である。
大型の白色オウムやボウシインコ、コンゴウインコといった一部の大型種のインコは80年におよぶ非常に長い寿命をもつことが報告されており、100年を超える年齢の記録もある。
ラブバードやサトウチョウ、セキセイインコといった小型のインコは15年から20年程度の短い寿命をもつ。
インコの中には非常にやかましい種類もある。
ほとんどの大型のインコは破壊的なことがあり、このため常に新しいおもちゃか、木の枝や噛んで遊ぶためのものを供給することが必要である。
大型のペットのインコの中でもその多くが高い人気と長命、そして知能のために、長い生涯のコースの途上で新しい飼い主に引き取られるということが起こる。
一般的な問題とはこうである。
つまり可愛らしい穏やかな幼鳥として購入された大型種のインコが、複雑で、多くの場合手数のかかる、飼い主よりも長生きする成鳥へと成熟する。
これらの問題のために、そしてこういったホームレスのインコを犬やネコのように安楽死させられないという事実から、パロットレスキューやサンクチュアリといった施設がより一般的になってきている。
出典: 「オウム目」
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

では、次の動画を見てください。。。

(hippo-man.gif)

カバってぇ〜、ノロマのように見えますけれど、時には凶暴になって人間にアタックするのですわねぇ〜。。。

そうです。。。油断できない動物です。。。
でも、そういう危険なカバが人間に懐(なつ)く場合もあるのですわぇ〜。。。
そうです。。。この男性は、生後一週間からこのカバを育ててきたのですよ。。。親代わりになって このカバを親切に世話してきたのです。。。
カバ

(kaba10.jpg)
カバ(河馬、Hippopotamus amphibius)は、哺乳綱偶蹄目(鯨偶蹄目とする説もあり)カバ科カバ属に分類される偶蹄類。
猛獣でもある。
マダガスカルとサハラ砂漠以南のアフリカ大陸で生息、ただしアルジェリア、エジプト、エリトリア、モーリタニア、リベリアでは絶滅。
直線上に並んでいる眼・鼻孔・外耳を水中から出して周囲の様子をうかがう
形態
体長3.5 - 4メートル。体重はオス平均1500 kg(キログラム) 、メス平均1,300 kg。
非常に大型のオスだと2,000 kgを超えることもある。
陸上動物としてはゾウ、サイに次ぐ3番目の重さとされる。
分厚い脂肪と真皮・上皮で覆われるが、表皮は非常に薄い。
このため毛細管現象により水分は外側へ放出してしまう。
皮膚は乾燥すると裂けてしまい、水分消失量は5平方センチメートルあたり10分で12ミリグラムともされこれは人間の約3 - 5倍の水分消失量にあたる。
頭部は大型。顔の側面に鼻・眼・耳介が一直線に並んで位置する。
これにより水中から周囲の様子をうかがいながら、呼吸することができる。
鼻孔は内側の筋肉が発達して自由に開閉することができ、水中での浸水を防ぐことができる。
下顎の犬歯は50センチメートルに達することもあり、下顎2本の重量はオス2.1 kg、メス1.1 kgに達することもある。
一生伸び続けるが、上下の歯が噛みあい互いをすり減らすことで短く、鋭くなる。
闘争時にはこの犬歯が強力な武器となる。
第3・4指の間が膜で繋がり水かき状になる。
皮膚表面を保護する皮脂腺・体温調節のための汗腺を持たないが、「血の汗」などと呼ばれるピンク色の粘液を分泌する腺がある。
この粘液はアルカリ性で乾燥すると皮膚表面を保護し、赤い色素により紫外線が通過しにくくなる。
主成分も分離されており、ヒポスドール酸 (hipposudoric acid) 、ノルヒポスドール酸 (norhipposudoric acid) と命名されている。
この粘液に細菌の増殖を防ぐ働きもあり、傷を負って泥中に入っても化膿するのを防ぐことができる。
生態
水より比重が大きいため、水底を歩くことができる。
10 - 20頭のメスと幼獣からなる群れを形成して生活するが、乾季には100 - 150頭の群れを形成することもある。
オスは単独で生活するか、優位のオスは群れの周囲に縄張りを形成する。
口を大きく開ける・糞をまき散らす・後肢で蹴りあげる・鼻から水を出す・唸り声をあげるなどして威嚇し縄張りを主張するが、オス同士で犬歯で噛みつくなど激しく争うこともあり命を落とすこともある。

(kaba12.jpg)
縄張りは頭や体を低くする服従姿勢をとれば他のオスも侵入することはできるが、他のオスが縄張り内で交尾することは許容しない。
8年以上同じ縄張りを防衛することもあり、このうちの1頭が12年縄張りを防衛した例もある。
昼間は水中で生活し、夜間は陸上に上がり採食を行う。
陸上での行動範囲は水場から3 km(キロメートル)だが、水場と採食場の途中に泥浴びを行える場所があればさらに拡大し、水場から最大で10 km離れた場所で採食を行うこともある。
通常体内に多量の空気を溜めこむと浮力により潜ることが困難になるが、四肢の重さにより潜水が可能になっている。

(kaba14.jpg)
水中では水よりも比重が重い関係で水の底を蹴って泳ぐため「カバは泳ぐのが苦手」と表現されることも多いが、後ろ足を駆使し力強い泳ぎを行うことが可能。
潜水時間は1分で、最長で5分。
移動速度は陸上では短距離で時速30キロメートルに達すると報告されているが、確認されてはいない。
食性は植物食で、草本・根・木の葉などを食べる。
一晩のうち4 - 6時間ほどをかけて、30 - 40 kgの食物を食べる。
体重と食事量の比率は、他の植物食の動物よりも低い(乾燥重量にすると体重の1 - 1.5 %、有蹄類では約2.5 %)。
飼育下では体重4,000 kgのゾウ類は1日あたり約200 kgの食物を食べるが、体重1,500 kgの本種は約50 kgの食物を食べるとされる。
これは昼間に温度変化の少ない水中でほとんど動かずに、エネルギー消費を抑えているためと考えられている。
水中での睡眠時には呼吸のために無意識に浮上することがある。
成体の場合、通常5分おきに浮上し、呼吸をしてまた潜水する。
天敵はライオンである。ベナンではライオンの獲物のうちカバが17 %を占める。
コンゴではライオンの獲物のうちカバが20 %を占め、ザンビアではライオンの重要な獲物になっている。
その他ワニやヒョウに捕食されることもある。
野生の寿命は40 - 50年。飼育下では58年生きた記録がある。
発情周期は約30日、発情期間は2 - 3日。
飼育下では交尾時間は12 - 17分の例がある。妊娠期間は210 - 240日。
主に水中で1回に1頭の幼獣を産む。オスは生後5歳、メスは生後4歳程度で性成熟する。
平均寿命は約30年。
人間との関係
1864年に村上英俊によって編纂された仏和辞典『仏語明要』では、hippopotama の訳語を「川馬」としている。
1872年の石橋政方訳『改正増補英語箋』では hippopotamus の訳語を「河馬」としたうえで、読みを「かば」としている。
古くは hippopotamusが「海のウマ」と訳されることもあったようで、日本でも1862年の『英漢字典』・1872年の『英和字典』・1862年の『英漢字典』などでは hippopotamus の訳語を「海馬(うみうま)」としている。
ウガンダのエドワード湖・ジョージ湖では個体密度(クイーン・エリザベス国立公園で1平方キロメートルあたり31頭に達することもあった)が高く、採食活動により湖岸の森林が消失し土壌が侵食された。
そのためアフリカ大陸では初めて野生動物の人為的管理計画として1962年 - 1966年に生態的調査を行いつつ間引きが実施された。
これにより沿岸の植生が回復し他の動物の生息数も増加したが、間引きが停止すると状況は戻ってしまった。
ウガンダのクーデターによりこの試みは棚上げとなり密輸が横行するようになったが、本種の生態的知見はこうした計画による調査から得られたものも多い。
農地開発や湿地開発による生息地の破壊や水資源の競合、食用や牙用の乱獲などにより、1990年代から2000年代にかけて生息数は減少した。
2017年の時点では、以後は生息数は安定していると考えられている。
アフリカ東部や南部では地域によっては生息数が激減したものの、未だ生息数は多いと考えられている。
一方で2003年にコンゴ民主共和国では8年間で生息数が約95 %激減したという報告もある。
密猟・密輸されることもあり、特に政情が不安な地域では横行することもある。
1989年 - 1990年には15,000 kg、1991年 - 1992年には27,000 kgの牙が密輸されたと推定されている。
1995年にワシントン条約附属書IIに掲載されている。
日本では2021年の時点でかば科(カバ科)単位で特定動物に指定され、2019年6月には愛玩目的での飼育が禁止された(2020年6月に施行)。
カバ牙の利用
ワシントン条約で国際取引が禁止されている象牙の代替品として、カバの牙が印鑑や工芸品の高級素材として使われることがある。
アフリカ大陸北東部(要するにかつて生息していたナイル川周り)の民族には、水の精タウエレトとして崇められ、カバを象った面とカバの牙から作った呪い用の杖バース・タスクを持って占いの儀式を行った。
コロンビアにおいては、かつてパブロ・エスコバルが自宅の動物園で飼育するために密輸した、通称“コカインカバ”の子孫たちが脱走・繁殖して問題となっている。
繁殖力が高いため、多くの動物園は繁殖制限を行っている。また飼育下では肥満になりやすいため、野生行動を引き出す環境エンリッチメントや、適切な健康チェックが出来、飼育員との信頼関係も深まるハズバンダリートレーニングに取り組む必要がある。
エピソード
かつて、移動動物園をしたカバヤ食品の「カバ子」は、後に「デカ」と改名されいしかわ動物園で飼育された。
東山動物園のカバの番(つがい)「重吉」(2代目)と「福子」(初代)は19頭の仔をもうけ、日本国内最多産記録を作った。
技術の向上から、1997年に大阪市天王寺動物園では日本で初めてガラス越しに水中を歩くカバを観察できるカバ舎を製作した。
この展示スタイルは富士サファリパークの「ワンダー・オブ・ピッポ」なども追随している。
また、神戸市立王子動物園はスロープの傾斜を緩くしたバリアフリーを配慮したカバ舎を2003年に造っている。
名古屋鉄道関連会社の名鉄整備のCIとしてカバをモチーフにした「ヒポポタマス」というキャラクターを使用している。
創業当時使用されていたボンネットバスの整備中の姿がカバに似ていたためこのキャラクターが生まれた。
また自社が名古屋発祥で中部圏に広まった事と名古屋の東山動物園で飼育されていたカバの重吉・福子の子孫が全国の動物園に広まっていたことにあやかって、ユーザーの事業が全国に広まるようにという願いもこめられている。
1981年の東武動物公園開園に当たり、上野動物園でカバの飼育で名を馳せ、漫画『ぼくの動物園日記』のモデルとなった西山登志雄が初代園長に就任し、「カバ園長」として親しまれた。
呼称
属名 Hippopotamus は、「カバ」を意味する hippopotamus (ヒッポポタムス)をそのまま用いたもので、大プリニウス『博物誌』等にも言及のある古い言葉である。
さらに遡れば ἱπποπόταμος (ヒッポポターモス; < ἵππος 「馬」 + ποταμός 「川」)であり、当時はナイル川下流でも見られたカバに対してギリシア人が命名したものであった。
なお、オランダ語では、nijlpaard(< Nijl 「ナイル川」 + paard 「馬」)という。
日本語の「河馬」は近代になってこれを直接訳したか、もしくは、ドイツ語で「カバ」を意味する Flusspferd (< Fluss 「川」 + Pferd 「馬」)を訳したもの。
<HR>
出典: 「カバ」
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

日本でも個人がペットとして飼っていた人がいるのですわねぇ〜。。。

そういうことです。。。でも、2019年6月に愛玩目的での飼育が禁止された(2020年6月に施行)のですよ。。。
餌代だけでも大変でしょうねぇ〜。。。街では、とても飼うことができないでしょう。。。
川がある農場でないと飼うのは無理ですよ。。。じゃあ、次の動画を見てください。。。この動画にもカバ出てきて、カバが人に懐いているのを説明しています。。。

次は、象の動画です。。。

(elephant-man.jpg)

(zou-man.jpg)

象がこの男性に嬉しそうによってきますわねぇ〜

この人が象が まだ小さな頃から世話をしたんですよ。。。そして、しばらくぶりに会ったわけです。。。

(chick-boy.gif)

ニワトリが 男の子に懐(なつ)いてますわねぇ〜。。。ニワトリでも可愛がって世話してもらった人物を覚えているのですわねぇ〜。。。こういう場面を初めて見ましたわァ〜。。。

ニワトリは身近な鳥で、料理されて食べることが多いから、頭が良い鳥だとは思わないけれど、意外に賢くて認知能力・感受性もあるのです。。。
ニワトリ

ニワトリ(鶏、庭鳥、学名:Gallus gallus domesticus)は、キジ科に属する鳥類の1種で、代表的な家禽として世界中で飼育されている。
ニワトリを飼育することを養鶏と呼ぶ。
祖先種のヤケイとしては単元説と多元説がある。
単元説は、東南アジアの密林や竹林に生息しているセキショクヤケイ(Gallus gallus)を祖先とする説である。
多元説(交雑説)はセキショクヤケイ、ハイイロヤケイ(G. sonneratii)、セイロンヤケイ(G. lafayetii)、アオエリヤケイ(G. varius)のいずれか複数の種が交雑してニワトリとなったとする説である。
現在では分子系統学的解析によってセキショクヤケイもしくはその亜種に由来する可能性が強く示唆されている。
一方で、現在のニワトリからハイイロヤケイ由来の遺伝子が見出されるなど、多元説を支持する報告もある。
ニワトリという和名は「庭に飼う鳥」、つまり家禽という意味から名づけられた。
ニワトリは普通「鶏」と書かれるが、「家鶏」で「にわとり」と充てることもある。
ニワトリは古くはカケ(鶏)と呼ばれた。
代表的な鳥であるため、単に「とり」ともよばれる。
雄のニワトリは「雄鶏(牡鶏)」(おんどり)、雌のニワトリは「雌鶏(牝鶏)」(めんどり)と呼ばれる。
漢字
「鶏(鷄、雞)」という漢字は、甲骨文字に見られるニワトリを象った象形文字に由来する。
これに音を表す「奚」を加えた後、ニワトリを象っていた部分が通常の「鳥」(または「隹」)と同じように書かれるようになり、「鶏」の字体となった。
なお、かつて「会意形声文字」と解釈する説があったが、根拠のない憶測に基づく誤った分析である。
「鶏」は万葉仮名の「け」(甲類)にも使われる。
漢字「鶏」は様々な複合語を作り、「軍鶏」(しゃも)、「闘鶏」(しゃも)、「鶤鶏」(とうまる)、「矮鶏」(ちゃぼ)、「小鶏」(ちゃぼ)、「水鶏/秧鶏」(くいな)、「黄鶏」(かしわ)、「花鶏」(あとり)、「珠鶏」(ほろほろちょう)、「吐綬鶏/白露鶏」(しちめんちょう)、「食火鶏」(ひくいどり)などと読む。
ちなみに、「酉」という漢字は酒壺をかたどった象形文字で、仮借して十二支の10番目を指す単語を表記する。
のち十二支それぞれに動物が割り当てられた際、「酉」にはニワトリがあてられた。
英語
英語では"Chicken"。
話者の地域、ニワトリの年齢や雌雄などによって様々に言い分けが存在し、"Chicken"も元々は「若いニワトリ」を指す用語であった。
この用法としての"Chicken"は、イギリスのパブや劇場の名、またはHen and Chicken Islandsなどの"Hen and Chickens"というフレーズで残っている。
本種全体を指す用語としてはdomestic fowl、barnyard fowlもしくは単にfowlが使われており、現在でも本種全体を指す語として使われる場合が有るが、「家禽」(主にキジ目の、あるいはカモ目も含んだ人に飼われる鳥)全体を指す広い言葉でもある。
さらに遡るとfowlは元々、全ての鳥を指していたが、この用法は今では"wild fowl"という複合語のみで用いる。
英語fowlは中英語のfowl, fowel, fugol、アングロサクソン語のfugel, fugol、オランダ語のvogel、そしてアイスランド語のfugl, foglと同根である。
イギリスとアイルランドでは1歳以上の雄鶏をcockと呼ぶのに対し、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアやニュージーランドでは普通同じものを指してroosterと呼ばれる。
アメリカ英語でroosterが用いられるのは、cockは陰茎という意味があり、この連想を避けるためである。
またcockは通例"cock cardinal"や"cock robin"のように複合語で、鳥の雄を表すこともある。
1歳未満の雄はcockerelと呼ばれる。
去勢された雄鶏はcaponと呼ばれる。
1歳以上の雌鶏はhen、それより若い雌鶏はpulletと呼ばれる。
ただし採卵養鶏場では、卵を産むようになった16-20週目の雌鶏はpulletではなくhenと呼ばれるようになる。
オーストラリアとニュージーランドでは、全ての年齢・性別のニワトリを表すchook [tʃʊk]という総称が用いられる。
また、雛はchickと呼ばれる。"Rooster"が雄鶏、"hen"が雌鶏を指す言葉として広く使われているのにも拘らず、"chicken"という用語はときおり誤って雌鶏のみを指して使われる。
アメリカ合衆国のディープサウスでは、ニワトリはyardbirdというスラングで呼ばれることもある。
認知能力・感受性
霊長類同様、複雑な認知能力を有する。意思決定の際は、自分の過去の経験や現在の状況を考慮に入れる。ほかの鶏に感情移入することもできる。
実験では、空気を吹きかけられて怯える雛を見た母鶏は、右往左往して不安様行動を示す。
そして、母鶏特有の「こっこっ」という声を発し、雛を落ち着かせようとする。
この研究は、鶏が他個体の視点に立ち感情を共有するという共感能力があることを示している。
また、騒音がストレスになる一方[32]、クラシック音楽を聴かされた鶏はストレスが軽減されるという。
孵化5日後のヒヨコは、足し算と引き算の能力を示し、雌鶏は、AがBより大きく、BがCより大きければ、AはCより大きい、という推理の能力を持つことが実証されている。
またヒヨコは、はしゃいだり羽ばたいたり、物を追いかけたりつついたり、他のヒヨコと物を交換したり、ヒヨコ同士でスパーリングしたりにらみあったりなど様々な遊びをする。
利用(食用)
ニワトリのもっとも重要な用途は食用であり、肉は鶏肉として、卵は鶏卵としてそれぞれ大量に生産される。
食肉としては、淡白な白身で、栄養素としてタンパク質に富む良質な肉質を持つ。
また、ウシやブタと並ぶ世界で最も一般的な食肉であり、さまざまな鶏料理が世界中に存在する。
ウシやブタと異なり、世界規模で信者が存在する宗教においてニワトリを食す事を禁忌とする宗教がない(ただしジャイナ教などのように動物の種類を問わず肉食自体を禁忌とする宗教は別)ため世界中で手に入り、食用の鳥としては最も一般的なものであるため、通常「鳥肉」と言えばそのままニワトリの肉(鶏肉)のことを指す。
卵としてはさらに重要な生産源であり、ウズラやアヒルやガチョウなどの特殊な卵を除き、世界で流通する卵のほとんどは鶏卵である。
このため、通常特に品種を指定せず「卵」と言えば鶏卵のことを指す。
また、ニワトリの骨を鶏ガラと言い、良質の出汁やスープの原料となる。
特に中華料理においては基本的な食材のひとつであり、ラーメンの最も基本的なスープは鶏がらを原料としたものである。
ニワトリの脂肪からは鶏油が取れ、これも良質の調味油となる。
鶏油は家庭において、脂肪の多く含まれるニワトリの皮から作ることもできる。
さらに、軟骨はそのまま炒めたり揚げたりして食べることができ、焼き鳥屋においては「やげん」や「なんこつ」の名で一般的なメニューとなっている。
また、ニワトリは消化管の一部である砂肝や、ハツ(心臓)、レバー(肝臓)などのもつ(内臓)も食用とされる。
英語における表現
アメリカ英語においては、chicken(チキン)は「臆病者(名詞)」「臆病で(形容詞)」という意味のスラングとして使われることがある。
例えば、"play chicken"「度胸試しをする」や、動詞として"chicken out"「尻込みする」という成句で使われる。
また、no chickenで子供、とくに小娘を表す口語として使われる。
雄鶏 cock(コック)は「陰茎」という意味のスラングである。
以下のような成句がある。
count one's chicken (before they are hatched)
捕らぬ狸の皮算用。卵が孵る前に雛を数えるなという意味から。
go to bed with the chickens
(アメリカ英語で)夜早寝する。
chicken-and-egg
鶏が先か、卵が先か。解決できない。
古代中国におけるニワトリ
古代中国では、ニワトリには頭に冠を戴く「文」、足に蹴爪を持つ「武」、敵と戦う「勇」、食を見て呼び合う「仁」そして夜を守り時を失わない「信」の五徳があるとされた。
中国における闘鶏は古く「春秋左氏伝」に見え、唐代に最も盛んであった。
ニワトリには霊力があるとされ、除夜に門戸に懸け、邪悪を祓うという風習があった。
また、ニワトリは吉祥のシンボルとされることもあるが、漢字「鶏」の音が「吉」に通じるためである。
またニワトリは時夜、燭夜、司晨(鳥)、金禽、窓禽、徳禽、兌禽、巽羽、翰音、羹本、赤幘、花冠、戴冠郎、長鳴都尉官、酉日将軍など、実に様々な別名で呼ばれた。
以下のように様々な故事成語や成句がある。
鶏群の一鶴(けいぐんのいっかく)
鶏群一鶴。鶏群孤鶴。多くの凡人の中に優れた人が一人交じっていること。多くのニワトリの群れの中にいる1羽のツルという意。
鶏口牛後(けいこうぎゅうご)
「鶏口となるも牛後となるなかれ」の略。大きな団体で人の後ろ(牛後)となるよりも、小さな団体でその長(鶏口)となった方がよいということ。『史記』に由り、戦国時代に蘇秦が韓の王に「小国とはいえ一国の王であれ。大国の秦に屈して臣下に成り下がってはならぬ」と説いて、六国の合従に導いた故事に基づく。
鶏黍(けいしょ)
手厚く客をもてなすこと。『論語』に由り、ニワトリを殺して吸い物を作り、キビを炊いてもてなした故事から。
鶏窓(けいそう)
書斎または書斎の窓。晋の宋処宗が書斎の窓に飼っていたニワトリは人語を解し、彼の学識を助けたという故事に基づく。
鶏鳴狗盗(けいめいくとう)
つまらない技芸、つまらないことしかできない人の喩え。一見つまらないことでも何かの役に立つこともあるという意で用いることもある。『史記』に由り、戦国時代のころ、斉の孟嘗君は秦の昭王に軟禁されたが、イヌ鳴き真似で盗みを働く食客とニワトリの鳴き真似をして夜明けだと思わせる食客のお蔭で脱出し帰ることができたという故事に基づく。
鶏肋(けいろく)
大した役には立たないが捨てるには惜しいもののことで、自分の労作を謙遜するときに用いる。『後漢書』の故事で、ニワトリの肋骨は食べるほどではないが、少し肉がついているため捨てるには惜しいことに由来する。また体がひ弱だという意もある。こちらは『晋書』に基づく。
鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん(にわとりをさくにいずくんぞぎゅうとうをもちいん)
取るに足りないことを大袈裟な方法で処理する必要はない。『論語』に基づき、ニワトリを捌くのにウシを切り裂く大きな牛刀を用いる必要はないということから。
陶犬瓦鶏(とうけんがけい)
瓦鶏陶犬。見かけだけ立派で、実際は役に立たないものの喩え。焼き物のイヌと素焼きのニワトリの意で、『金楼子』に由る。
その他の文化
風見鶏
雄鶏 (紋章学)
早朝に鳴いて人に朝を知らせることを報晨という。『古事記』にて、天岩戸に閉じこもった太陽神である天照大神を呼び出すため常世長鳴鳥の鳴き声を聞かせる故事があり、伊勢神宮では放し飼いとなっている。また、ペルシア王タフムーラスは、早朝を知らせる鳥として導入した。インドや中国、ヨーロッパでも太陽と関連付けされ、闇夜を払う神聖な鳥として、食用を禁じられたり、魔避けとされ、崇められた。
太陽が幾度も登ることから、再生力と関連付けされ、鶏が医神アスクレーピオスへの捧げものとされた。哲学者ソクラテスの刑死前の遺言として、アスクレピオスに雄鶏を捧げるよう友人に依頼している。
闘鶏として、ギリシアなどで定着したことから、軍神の聖鳥としても崇められた。こういった闘争心は、ブレーメンの音楽隊などでも見ることができる。また、闘鶏好きのイギリス王ヘンリー8世の時代に闘鶏の試合ルールが定められ、それがそのまま人間が行う闘鶏ボクシングのルールになったという逸話がある。
出典: 「ニワトリ」
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(tiger2.gif)

親と離れ離れになったこの虎を この女性が生後3ヶ月の頃から育てたのですよ。。。だから、まるで自分の本当の母親のように、この虎は再会を嬉しがっているのです。。。

(gorilla81.gif)

この男性は野生のゴリラの赤ちゃんをイギリスで育て、大きくなったのでアフリカの野生の森に放して、5年ぶりに会ったのです。。。

それにしても5年ぶりに会って、ゴリラがよく覚えていましたわねぇ〜。。。
上の動画には13年離れていた猫が再会した時に飼い主を覚えている場面が出てきますよ。。。猫だって13年離れていても優しく世話してくれた飼い主を覚えている。。。人間に近いゴリラならば、5年離れていても可愛がってくれた飼い主は覚えているのは当然ですよ。。。

(lion-man.gif)

このライオンは、赤ちゃんの頃からこの人物に育てられて、保護施設に預けららているのすよ。。。久しぶりに出会ったので、このように再会を喜んでいるのです。。。

ほんとうに心温まる情景ですわねぇ〜。。。私も家に残してきた愛犬のボビーに会いたくなりましたわァ〜。。。

(laugh16.gif)
【ジューンの独り言】

(bare02b.gif)
ですってぇ~。。。
あなたも上の動画を見たら、微笑ましく、心が暖まる思いがしたでしょう?
ええっ。。。「そんなことは どうでもいいから、他に何か面白いことを話せ!」
あなたは、そのように わたしにご命令なさるのですかァ~?
分かりましたわ。。。
じゃあ、ホログラムを使った面白い動画をお見せしますわァ〜。。。
「面白いけれど、それだけじゃつまらん。他に何か面白いことを話せ!」
貴方が 更に そう言うのでしたら、ワンワンちゃんの面白い動画をお目にかけますわ。。。
ワンワンちゃんが人間の言葉をしゃべります!

(dog810.jpg)
ええっ。。。? 「そんな馬鹿バカしい動画など、どうでもいいから、何か他に面白い話をしろ!」
あなたなは、また そのような命令口調で わたしに強要するのですか?
わかりましたわァ。。。
では、たまには日本の歴史の話も読んでみてくださいなァ。
日本の古代史にも、興味深い不思議な、面白いお話がありますわァ。
次の記事から興味があるものをお読みくださいねぇ~。。。
■天武天皇と天智天皇は
同腹の兄弟ではなかった。
■天智天皇は暗殺された
■定慧出生の秘密
■藤原鎌足と長男・定慧
■渡来人とアイヌ人の連合王国
■なぜ、蝦夷という名前なの?
■平和を愛したアイヌ人
■藤原鎌足と六韜
■古事記より古い書物が
どうして残っていないの?
■今、日本に住んでいる人は
日本人でないの?
■マキアベリもビックリ、
藤原氏のバイブルとは?
ところで、他にも面白い記事がたくさんあります。
興味のある方は次の記事も読んでみてくださいね。
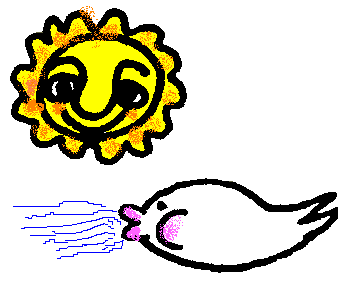
(sunwind2.gif)

(sylvie500.jpg)
■『おもろい動物たち』
■『動物の愛と感謝』
とにかく、今日も一日楽しく愉快に
ネットサーフィンしましょう。
じゃあね。バーィ。

(hand.gif)




(spacer.gif+betty5de.gif)
(hiroy2.png+betty5d.gif)
『スパマー HIRO 中野 悪徳業者』

(surfin2.gif)
ィ~ハァ~♪~!
メチャ面白い、
ためになる関連記事

(himiko92.jpg)
■『卑弥子の源氏物語』
■『平成の紫式部』
■ めれんげさんの『即興の詩』
■ めれんげさんの『極私的詩集』

(bagel702.jpg)
■ "JAGEL - Soft Japanese Bagel"

(linger65.gif)
■ 『センスあるランジェリー』
■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』
■ 『面白くて楽しいレンゲ物語』

(beach02.jpg)
■ 『軽井沢タリアセン夫人 - 小百合物語』
■ 『今すぐに役立つホットな情報』

(rengfire.jpg)

(byebye.gif)
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます