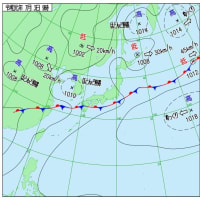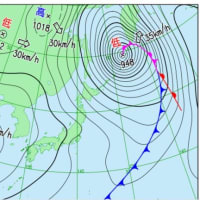随分昔の話で恐縮ですが、ふと思い出したので書き留めておこうと思いました。
島根県へ旅したのは昭和39年頃だったと思います。調べれば明確な年代が判りますが敢えてそうしないことにしました。京都で会合がありそのついでに島根県の小泉八雲記念館や宍道湖を見てみたいと思いました。同じ勤め先の仲間2人と京都駅から列車に乗りました。筆者は旅行で目的地へ着くまでは昼間列車に乗ることにしています。途中の駅に着くと必ず駅弁を買って食べるのが大きな楽しみでした。この旅でも鳥取駅の鳥めし駅弁を買い求めみんなで食べました。鶏そぼろがご飯の上に一面に広がり、一部に炒り卵とデンブが彩りを添えていました。僅かに甘くとても美味しかったのを思い出しました。あの駅弁は今もあるのでしょうか。
そうこうしているうちに列車は、松江駅に着きました。何しろ若かったので宿屋を予約することなんてしないで来てしまいました。それでも運良く眺めの良さそうなホテルに入ることが出来ました。ホテルの窓から宍道湖が見えるいい部屋を案内してもらいました。その日は小泉八雲の記念館を見てから松江城(跡)を散策してゆっくり過ごしました。夕暮れ時の宍道湖は夕焼けを写して幻想的な美しさを見せてくれました。宍道湖を二つに分ける橋もその美しさを際立たせるものでした。夜は電灯を消してテラスへ出ると星が降るように近くに見えました。宍道湖の方を見ると、漁り火でしょうか湖面に明かりを映していました。美しい夜景を見ながら、将来の夢を語り合いました。
翌日の朝は、宍道湖でとれたしじみ汁を添えた朝食を食べて出雲神社へ向かいました。バスに乗ってしばらく行きますと出雲大社駅に着きました。バスで駅に?と思いましたが、そこは一畑電鉄(イチバタデンテツ)という宍道湖の北岸を走る鉄道の駅でした。
出雲大社は荘厳なとはいえませんでしたが、しっとりとした社と境内の広い神社でした。ここは神無月に、日本中の八百万(ヤオヨロズ)の神様が集まって日本中の婚姻を取り仕切る神社だそうで、若い二人連れがたくさんいました。私たちの中には、一人だけ独身者がいたので神様によくお願いしなさいといいましたが、彼はお参りをしませんでした。そのためかもしれませんが、とうとう後期高齢者になるも結婚しませんでした。
その後、日御碕という所へ行きました。ここは玄武岩のような岩石が屹立した断崖でした。断崖の先端に立って周辺を見渡すと断崖の中に洞窟のようなものも見えました。のんびりと散策をして、その日は日御碕の国民宿舎へ止まることにしました。この国民宿舎は、大社作りの各部屋が広いすてきな宿舎でした。夜は周辺に明かりが無く、満天の星が見えました。
次の朝、私たちは出雲大社駅に行き、一畑電鉄で松江に向かうことにしました。小ぶりな車両は、東急車輌製であることが明記されていました。私は座ることはなかったのですが、特別席(今のグリーン席)の切符を買いました。これも想い出の一つですね。電車は宍道湖の北岸を一生懸命?走りました。どこかで乗り換えたように記憶しているのですが、今となっては不明です。かなり時間がかかって終点につきました。帰りは松江駅から京都へ向かい、京都から夜行列車で東京へ戻りました。
このときは未だ新幹線がありませんでしたので、旅はゆっくりしたものでした。