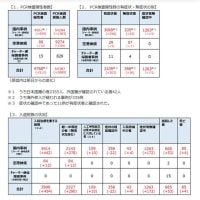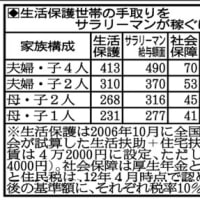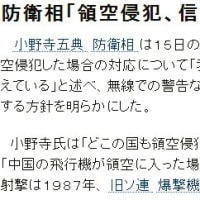自分が小学生の頃の話。確か小4くらいだったと記憶する。小学校の敷地内の端に体育用具を入れる倉庫があった。そこに、ちょうど時期的に不要になった机が山積みにされていた。本来は、倉庫に入れる予定だったらしいが、倉庫の整理に手惑い片付けられるのに時間が掛かっていた。自分と友人2人は、「立ち入り禁止」と書かれ張り巡らされていたロープを潜り、休み時間にそこで遊んでいた。休み時間も終わり、チャイムが鳴って教室に入ろうと、下駄箱に走っていった。すると、背のひょろっと高い老年の教師が自分達を呼び止めた。「お前ら、あの机のところで遊んでいただろう!危ないじゃないか!」とそんな風に怒鳴られ、一人ずつその教師の前に立たされて、3人とも左の頬を一発ずつ平手で叩かれた。無論、その時の自分達は文句を言いながら、教室に入っていった。それから時が流れ、あの時の情景を思い浮かべると、その叩かれた痛みよりも、遊んでいた机が崩れて、大怪我をせずに済んだことに感謝の念を抱くのである。
<産経関西より抜粋>
体罰を加えたことをわびる教諭に、教諭の熱意を正面から受け止めた児童と保護者。京都府京丹後市の市立小学校で、「クラスメートへのからかいをやめなかった」とクラス全員に体罰をした男性教諭(28)が辞表を提出した。しかし、保護者のほぼ全員が辞職の撤回を求める署名を提出。思いとどまった教諭は謹慎処分が解けた8日、児童らと互いに謝罪し、きずなを深めたという。市教委は「近年、学校に理不尽な要求をする保護者が増える中、教諭の熱意が通じたのでは」としている。
市教委などによると、教諭のクラスでは1人の男児の外見を一部児童がからかい、他の児童も黙認する状態だった。教諭は「(次にからかったら)みんなをたたいて教師を辞める」と注意したが、今月4日、再びからかいがあったため、「ここで放置すると、いじめに発展しかねない」と判断、からかわれた男児を除く全員のほおを平手打ちした。
報告を受けた校長は同日夜、保護者らを集め、教諭とともに謝罪。3日間の自宅謹慎を命じられた教諭は辞表を出した。ところが、寛大な処分を求める署名運動が保護者の間で始まり、全校の児童191人の保護者ほぼ全員分の署名が学校に提出された。
その後、教諭が二度と体罰をしない意思を示したため、校長は辞表を返却。謹慎処分が解けた8日、うつむいてわびる教諭に、児童たちも泣きながら「私たちが悪かった」と謝ったという。
教諭は採用4年目で、同小には今年度着任。校長によると、熱心でまじめな人柄で、子供のころに外見を理由にした嫌がらせを受けた経験があったという。
引野恒司・同市教育長は「学校に理不尽な要求をする保護者も少なくない風潮なのに、教諭の行為を熱意ととらえ、署名運動まで起きるとは驚いている」とした上で、「体罰の事実は事実なので、子供や保護者の心情を受け止めた上で適正に処分はする」としている。
河上亮一・日本教育大学院大学教授(教師論)の話 「教師として、職をかけてもやってはいけないことを示す覚悟も必要。児童や親にもその姿勢が伝わったのではないか。最近ではこういう先生はめずらしく、評価すべきだ」
森毅・京都大名誉教授の話 「熱心だから体罰が許されるという話ではない。教師が体罰をするなら辞めるしかないと思うし、保護者らはそれを非難するにしても支持するにしても、もう少し学校と冷静に付き合う手だてがあるのでは」
http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya060903.htm
心無き体罰は、暴力であり、心無き言葉は誹謗・中傷であり、心ある体罰は慈悲、すなわち愛なり。
ただ感情任せに、自分の思い通りにさせるために、人を叩く、殴る行為を暴力と呼ぶ。体罰とは、相手に反省を促す目的があり、かつ自分も痛みを伴う状況下で行われなければ、本当の心を通わすことはできない。相手を苛(いじ)めた人間のみならず、誹謗された人間を除くクラス全員に対して体罰を与えなければならなかった、この教師の胸の痛みは判る気がする。君子危うきに近寄らずとはいうけれども、助け合ってこその人間社会ではないか。それを判った上で嘆願署名した親もまた立派だ。
本来はこのような姿が、昔の日本の学校教育にはあった。もちろん、感情任せに暴力を振るう教師もいれば、自戒を促すために体罰を行った教師もいる。後者のような教師に叩かれたものは、時が経つにつれ、自戒し良い思い出に変わっていくものである。
近年は吼(ほ)え猿の如く、学校に物申すのが当たり前の風潮になってきている。人の迷惑を顧みないその行動は、子供にどんな影響を与えるか、判っていないのではないか。そして、子供を愛玩ペットと勘違いしてはいないのだろうか。親は木の上から子供を見下ろすのではなく、木のようにどっしりと構えて、慈悲を持って見守るのが親なのではないか。その方が子供達にも不安を払拭し、安心感を与えられる。また、時には子供の目線に合わせ、暖かな眼差しで慰(なぐさ)めるのも親だ。
こうした、昔当たり前のような光景が、目新しく、優しく思えるのは、今の学校に携わる大人達が歪んでいるからに他ならない。人権だの、男女平権だのが叫ばれて、日本人が持っていた美徳を破壊された気もする。今一歩、我々は引いた目線で物事を考える時期に来ているのかもしれない。
(補足:この記事の良いところは、河上教授と森教授の対比にある。2つの異なる意見を対比させる、これこそ中立の報道姿勢と言える。異なる意見は載せないどこぞの新聞社は見習うべきだろう。あとは読者が何れかの意見を採用すれば良いということだ。)