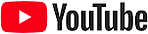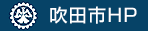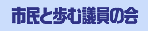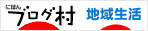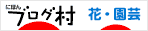未来にまっすぐ、市政にまっすぐ。まっすぐな人、池渕佐知子。無党派、市民派の前吹田市議会議員です。
未来にまっすぐ(池渕 佐知子のブログ)
21世紀の科学技術
阪大中之島センターで開催された環境リスクに関する研修会に出席しました。
講師は私の出身である阪大薬学部の平田教授で、「光合成生物の機能を利用した環境修復と食料増産」というテーマで講義と質疑で2時間ありました。
まずイントロダクションとして、21世紀の科学技術は環境保護と調和を保ちつつ、持続的な発展を保証するものでなければならない。だから、環境保全、環境管理、環境修復におけるバイオテクノロジーの活用が重要であるということです。
植物は動物と違い動けないので(だから動物とは言わないのだけれど)もし環境ストレスがかかっても、動いて逃げるわけにはいきません。だから、環境ストレスに耐える(耐性の獲得)、環境ストレスへの防御機能の発現、環境ストレスによる生物活性物質の生産がおこるという話でした。
そして、この植物の環境ストレスに対する反応を解析することによって、医療(医薬品原料、診断薬、予防薬)、環境(汚染物質浄化、汚染物質センサー、砂漠緑化)、食品・食料生産(高機能健康食品、安全な組み換え植物、環境調和型農薬)への応用、さらに実用化を考えていきたいという話でした。
これらの中で実際に実用化しているのは、ビスフェノールA(環境ホルモン)の浄化に有用とされている植物(ポーチュラカ)の販売ぐらいで、あとは、実用化に向けて試験プラントを海外で行っている緑藻を用いた余剰バイオマスを原料とする乳酸生産とのことでした。
講義の中身は化学式やDNA解析や濃度反応曲線グラフなど、まるで学生時代に戻ったような気分でした。(と言っても、私が学んだ頃よりもずっと高度な研究内容になっていますが)
平田教授が最後に、「研究者は実用化とか考えずに研究のための研究をしがちで、研究と実用化との間には大きなギャップがあるが、実用化を考えない研究ではなく、実用化を見据えた研究をしていきたい」と言われたと記憶しています。そういう繋ぐ役割が大事で、求められているのだろうなぁと思いました。
何事もそうですよね。理論と実践。理想と現実。その間は大きく深いけれど、それを繋ぐ人がいるから、前に進んでいくのだと思います。
講師は私の出身である阪大薬学部の平田教授で、「光合成生物の機能を利用した環境修復と食料増産」というテーマで講義と質疑で2時間ありました。
まずイントロダクションとして、21世紀の科学技術は環境保護と調和を保ちつつ、持続的な発展を保証するものでなければならない。だから、環境保全、環境管理、環境修復におけるバイオテクノロジーの活用が重要であるということです。
植物は動物と違い動けないので(だから動物とは言わないのだけれど)もし環境ストレスがかかっても、動いて逃げるわけにはいきません。だから、環境ストレスに耐える(耐性の獲得)、環境ストレスへの防御機能の発現、環境ストレスによる生物活性物質の生産がおこるという話でした。
そして、この植物の環境ストレスに対する反応を解析することによって、医療(医薬品原料、診断薬、予防薬)、環境(汚染物質浄化、汚染物質センサー、砂漠緑化)、食品・食料生産(高機能健康食品、安全な組み換え植物、環境調和型農薬)への応用、さらに実用化を考えていきたいという話でした。
これらの中で実際に実用化しているのは、ビスフェノールA(環境ホルモン)の浄化に有用とされている植物(ポーチュラカ)の販売ぐらいで、あとは、実用化に向けて試験プラントを海外で行っている緑藻を用いた余剰バイオマスを原料とする乳酸生産とのことでした。
講義の中身は化学式やDNA解析や濃度反応曲線グラフなど、まるで学生時代に戻ったような気分でした。(と言っても、私が学んだ頃よりもずっと高度な研究内容になっていますが)
平田教授が最後に、「研究者は実用化とか考えずに研究のための研究をしがちで、研究と実用化との間には大きなギャップがあるが、実用化を考えない研究ではなく、実用化を見据えた研究をしていきたい」と言われたと記憶しています。そういう繋ぐ役割が大事で、求められているのだろうなぁと思いました。
何事もそうですよね。理論と実践。理想と現実。その間は大きく深いけれど、それを繋ぐ人がいるから、前に進んでいくのだと思います。
コメント(0)|Trackback()
?