スポーツ大好き人間として、最近の柔道界、野球界の不祥事は、誠に残念だ。しかも、それぞれのトップは、何だかんだと言って辞める気配はない。全く見苦しいとしか言いようがない。
全日本柔道連盟(全柔連)では、暴力指導問題や助成金不正受給など不祥事が相次ぎ、4月下旬には、引責辞任を示唆していた上村春樹会長が「改革をやり切るのが使命」と述べ、一転して続投を表明した。如何に一般国民の感情とかけ離れていることか。

来年6月まで任期が残っているという上村会長は、「職にしがみついているわけではない。しっかり結果を出したい」と釈明しているが、長年にわたって責任者の立場にありながら、幾つもの不祥事に全く気がついていなかったのか、あるいは見てみぬふりをしていたのか、いずれにしても、組織を統率していく力がなかったということは明らかだ。何と弁明しようが、職にしがみついているとしか思えない。
上村氏は、オリンピックでの金メダル獲得をはじめ、長年にわたって輝かしい実績を持ち、柔道界においては、押しも押されもせぬトップリーダーである。しかし、事ここに至っては、責任を明確にすべき時に来ている。今の柔道界の常識は、世間の常識とは明らかにかけ離れている。新しく理事などの役員になった皆さんも、それを十分に弁えて改革に当ってほしい。
一方、日本野球機構(NPB)が統一球をひそかに飛ぶボールに変更していた問題。これまた、加藤良三コミッショナーが12日、各球団など関係者にお詫びをしたとのことだが、「私は知らなかった」「不祥事とは思っていない」と頑強に言い張る姿には唖然とした。下田邦夫事務局長の独断で行われたと示唆したが、事務局長は、相談しながら進めたと言っていたのに、すぐに撤回するなど混迷を深めている。

こんな大きな問題を、コミッショナーが知らずに事を進められるのか、極めて疑問だ。コミッショナーが知っていても、知らなかったとしても、紛れもなく不祥事そのものではないか。なのに、コミッショナーは、初めての記者会見では頭を下げていなかったし、昨日の会見でも、「ボールが変わったのは、ずれを修正する行為。そのことに着目すれば世間でいう不祥事ではない」と開き直る始末。
「失態」であると言いつつ、今のところ「私の進退問題について第三者(第三者機関を設置することになった)から意見が出れば当然ながら留意すべきことではある」とし、自ら辞任する意向はないようだ。テレビで、引退した小久保選手が言っていた。「ボールが飛ばせなくなったことも、引退の一要因ではある」と。
バッターにしろ、ピッチャーにしろ、選手生命に関わる問題を何と心得ているのか。駐米大使などを務めたエリートだが、トップとしての責任の取り方などは、知らないらしい。いや、知っていても、何だかんだ言っても選手やファンなどを言いくるめられるとでも思っているのだろうか。ここは、柔道界と同じように、球団の責任者や関係者が、勇気をもって改革に当らなければならい時だ。
リーダーの進退について記憶に残っている文章がある。
早稲田大学の教授だった宇野政雄氏が、昭和60年代に日本経済新聞社の「あのとき あの言葉」という連載の中で書いている。昭和40年代、大学紛争が激しかったころ、大浜信泉総長の後を引き受けて総長代行→総長→理事長となった阿部賢一氏についてである。当時、毎日新聞社の代表取締役であったが、総長代行として大荒れの学園紛争を半年で鎮静化させた。

総長の時、任期は4年だったが、2年ほどして、理事を務めていた宇野氏は、阿部氏から総長を辞めると告げられたという。その理由を聞くと、「最初から、火事の火消し役のつもりで総長になったのだから、鎮火したところで辞めるのが本当だと思う」と言い、「組織運営の責任者の進退にはタイミングが大切だと思う」とも語ったという。
あのころ、その潔さに賞賛の声が上がったのを覚えている。リーダーたるもの、その進退のタイミングを誤れば、今まで如何に立派な業績を残してきても、タイミングを失したら、それらを台無しにしてしまうということを肝に銘じなければならない。












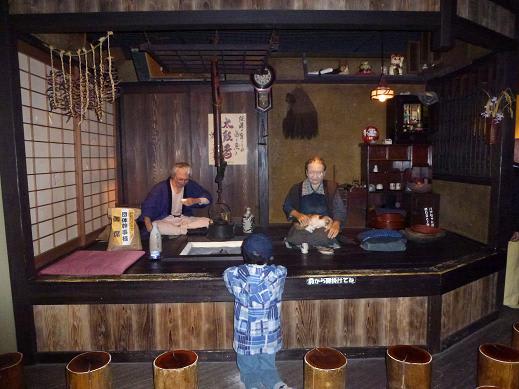
























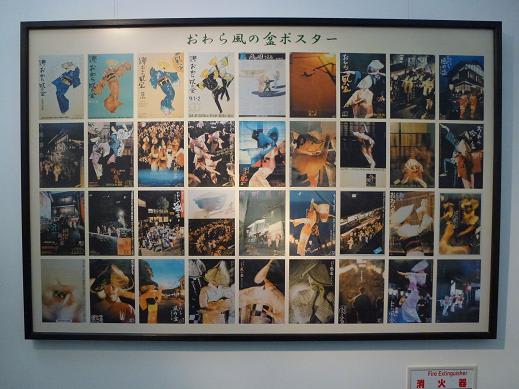












 い
い























































































