中学受験で疲弊しないために、親子で楽しむ受験になるヒントを綴っていきたいと思います。
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法
覚えるのが好きな子
例えば歴史は非常に詳しい子がいます。
あるいは生物の知識を恐ろしく持っている子がいる。
こういう子どもたちは覚えるのが苦にならない。というか、覚えようとして覚えてはいないのかもしれないと思います。
長い蝶の名前が、すらっと言えてしまう。どういう頭の構造になっているか、わからないがうらやましい限りです。
ところがこういう子がいざ、算数となると「パタっ」と思考を止めてしまう。
「どうした?」
「解き方を知りません。」
とこうくる。
「解き方は考えればいいんじゃないの?」
「でも習っていないから。」
これはやはり危険ですかね。
知識というのも使ってナンボのところがあるし、クイズ的に知識を持っていても入試では半分しか役には立たない。
やはり知識なり解き方なりは自分で使えるようになっていないと武器にはなりません。
良くパターンで算数を教える先生がいます。
例えばつるかめ算の基本問題を10も、20も数字を変えて出す。
こういう訓練は、確かに解き方を覚えればできるのかもしれない。しかし、それではその先に応用が利かなくなります。
良く月の満ち欠けの問題でこんな図を見ることがあるでしょう。
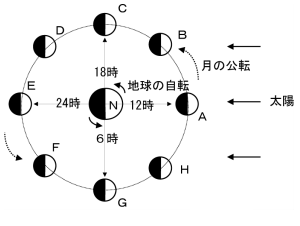
知識のある子は、まあだいたいわかっていると思うのですが、そんな子どもたちに
「どうしてどこでも正面が南なんだ?」
と聞くと、キョトンとすることがあります。
これは当然、北半球だから起きることなのですが、背中が北極を向いているのです。だから正面はどこでも南になる。南半球では背中が南極を向くから正面は全部北です。
知識を知っていて、実際は知らない。覚えているだけ、では次につながらない。
最近、地球から月を見るのではなく、月から地球を見るとどう見えるか、という問題が増えていますが、これなんかも、この図で解ける問題ではあるのです。その時の月の位置から地球を見たときの太陽の影の位置を見ればよいだけの話。
ところが、月の満ち欠けの問題ばかりを考えていると、足をすくわれてしまう。
だから、覚えるのももちろん大事だが、まずは考えることを優先してほしいと思うのです。
「どうして、こうなるの?」
そういうところから、考える力は伸びるのだと思います。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
立体を通る光線
==============================================================

「中学受験、成功する親、失敗する親」
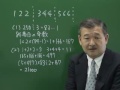
「映像教材、これでわかる数の問題」(田中貴)
 にほんブログ村
にほんブログ村
あるいは生物の知識を恐ろしく持っている子がいる。
こういう子どもたちは覚えるのが苦にならない。というか、覚えようとして覚えてはいないのかもしれないと思います。
長い蝶の名前が、すらっと言えてしまう。どういう頭の構造になっているか、わからないがうらやましい限りです。
ところがこういう子がいざ、算数となると「パタっ」と思考を止めてしまう。
「どうした?」
「解き方を知りません。」
とこうくる。
「解き方は考えればいいんじゃないの?」
「でも習っていないから。」
これはやはり危険ですかね。
知識というのも使ってナンボのところがあるし、クイズ的に知識を持っていても入試では半分しか役には立たない。
やはり知識なり解き方なりは自分で使えるようになっていないと武器にはなりません。
良くパターンで算数を教える先生がいます。
例えばつるかめ算の基本問題を10も、20も数字を変えて出す。
こういう訓練は、確かに解き方を覚えればできるのかもしれない。しかし、それではその先に応用が利かなくなります。
良く月の満ち欠けの問題でこんな図を見ることがあるでしょう。
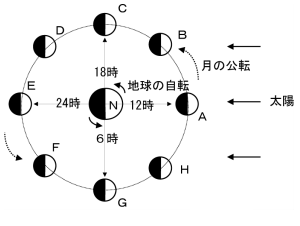
知識のある子は、まあだいたいわかっていると思うのですが、そんな子どもたちに
「どうしてどこでも正面が南なんだ?」
と聞くと、キョトンとすることがあります。
これは当然、北半球だから起きることなのですが、背中が北極を向いているのです。だから正面はどこでも南になる。南半球では背中が南極を向くから正面は全部北です。
知識を知っていて、実際は知らない。覚えているだけ、では次につながらない。
最近、地球から月を見るのではなく、月から地球を見るとどう見えるか、という問題が増えていますが、これなんかも、この図で解ける問題ではあるのです。その時の月の位置から地球を見たときの太陽の影の位置を見ればよいだけの話。
ところが、月の満ち欠けの問題ばかりを考えていると、足をすくわれてしまう。
だから、覚えるのももちろん大事だが、まずは考えることを優先してほしいと思うのです。
「どうして、こうなるの?」
そういうところから、考える力は伸びるのだと思います。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
立体を通る光線
==============================================================

「中学受験、成功する親、失敗する親」
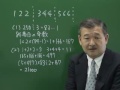
「映像教材、これでわかる数の問題」(田中貴)
コメント ( 0 )




