



今日はお寺の婦人部サークルでお念珠作りです。
簡単かと思ったら、ビーズ遊びのようにはいきません。途中まではスイスイでしたが、根元の親玉を通すのに手こずりました。
小さい穴がTの字になっていて、そこに左右から紐を通さねばならず、針やピンセットを使って悪戦苦闘です。
今日中に出来上がるかしら?と不安になるほどでした。
それだけに穴から紐が覗いた瞬間の嬉しさ!「出たぁ!」と思わず歓声をあげましたよ!
さあ、それからも又大変!
親玉の下のボサ玉に通した2本の紐(これも難しかった)を片ちょうちょ結びして4本の紐にし、房を編んでいくのです。
何という編み方か知らないけど、井桁のような形に6~7回編んで、やっと出来上がりました。
ご住職さんの話によると、今日の生徒(?)は優秀とのこと。
いえいえ、教え方がいいんですよ!
というわけで、1時間半ほど掛かりましたが、全員、Myお念珠の完成です。
来月のサークルは、お念珠入れを作る予定になっています。今から楽しみです。










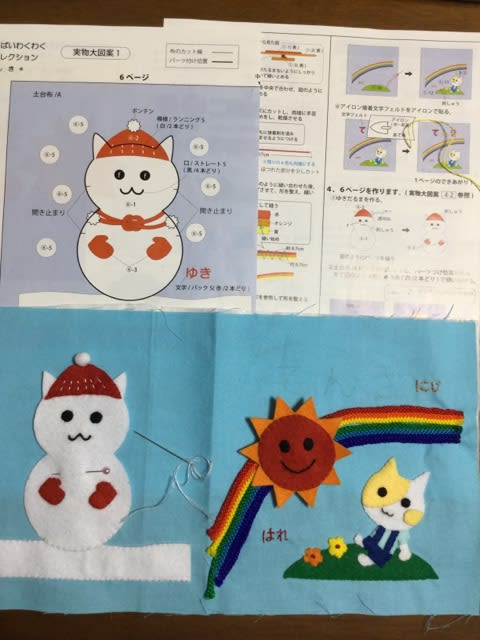
 )
)


























 これはブローディア
これはブローディア









