今週は、この2冊。
霜の降りる前に/死んでいない者/
■『霜の降りる前に(上・下)/ヘニング・マンケル』 2016.4.9
『霜の降りる前に』を読みました。
鍵をかけることと鍵を開けることは人が日々営む根本的な行為のひとつだからだよ。人間の歴史を通して、鍵束に揺れる鍵の音が聞こえる。鍵は一つひとつ異なる歴史を物語るものだ。そして、今回の鍵の話しもその中の一つなのだ。
こんなすてきな言葉を作品に残し、ぼくとほぼ同じ歳のヘニング・マンケルが逝ってしまった。
肺がんでした。
この作品のなかで、生きることへの彼の姿勢を思わせる言葉を見つけました。
父の目に涙が光っていた。ステン・ヴィデーンが死んだという知らせだった。知らせてきたのはヴィデーンのつきあっていた若い娘のひとりだった。たぶん最後に彼がいっしょに暮らしていた子だろう。クルト・ヴァランダーにヴィデーンの死を知らせて"すべてうまくいった"という言葉を伝えるように言われたという。
「それ、どういう意味?」
「若いころ、ステンとおれはそう決めていたんだ。死を決闘の相手として見なすということだ。勝負はすでに決まっていても、相手が力つきてなんとかこっちを倒すだけの力しか残っていないところまで、最後までねばるということ。死ぬときは、そのような死に方をしようと二人で決めていたんだ。"すべてうまくいった"というのはそういう意味だ」
ヘニング・マンケルの人となりについては、「訳者あとがき」に言い尽くされています。
ご一読下さい。
さて、この作品は、リンダとアンナの父と母と娘、祖父との家族の物語でもあります。
また、「信じる」ということについても考えさせられます。
地味なミステリーであり、かなり重たく感じられることもありましたが、がんばって読みとおしました。
それなりに面白く、味わい深いものがあります。
それにしても、リンダとヴァランダー父娘は、なぜあんなにもお互いに短気になるのでしょうか。
海に向かって、月に向かって、親に向かって大声で叫ぶ経験をしなければ、人は大人になれないもの。悲しみを経験したことのない王子や王女さまなんてなんてどうしょうもないから。そういう子たちは魂に麻酔薬を打たれたようなもの。わたしたち生きている人間は悲しみというものを知らなくちゃいけない
若いころは自分がしたいことがわからず悩んだ。自分の中に潜んでいるある種の苛立ち。
彼、あきらめたんだと思うの。いつか、何者かになるという夢は、夢でしかなかったんだと。
人には二種類ある、まっすぐで短い、もっとも早く目的地に到達する道を選ぶ人間と、回り道を選び、曲がりくねった道や険しい坂道があるほうを選ぶ人間と。
「駆け出しのころ、おれはリードベリからすべてを学んだ。彼もまた、ご多分に漏れず早く死んでしまった。だが、一言も愚痴らなかった。彼も人生のレースを何度か経験し、もう自分のレースのときは過ぎたということを受け入れた人間だった」
「おやじはそういう人間だった。おまえにとってはきっと別の人間だろうが」
「人はだれでも相手によってちがう自分を見せるんじゃない?」
「嘘つきが相手に嘘を信じ込ませるコツは、話の大部分が本当であること。その中に嘘を混ぜ込むの。そうすれば、嘘が真実のように聞こえるのよ。それで聞くほうはすべて本当だと思う。いつまでもってわけにはいかないけどね。話が嘘であることは早晩わかるから」
『 霜の降りる前に(上・下)/ヘニング・マンケル/柳沢由実子訳/創元推理文庫 』
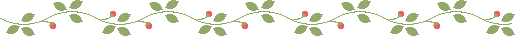
■『死んでいない者/滝口悠生』 2016.4.9
今回、初めて滝口悠生さんの作品を読みました。
『死んでいない者』は、ぼくには内容がよく理解できない作品でした。
それで、朝日新聞/2016.3.13/読書欄/大竹昭子さんの書評の助けを借りました。
第154回芥川賞受賞作。
まずタイトルで首をひねる。頭に「もう」をつけたらここに居ない死者に、「まだ」ならばこの世に留まっている生者になる。どちらともとれるが、この両義的なタイトルこそが作品のキモだ。
「お前さんは誰の息子?」
通夜の席ではおなじみの光景だ。故人とつながっているはずなのに、その結び目がわからない。
だが登場者の関係がつかみにくいのは意図的だ。全体に俯瞰する視点を著者はあえて避けている。
主語なしに成立する日本語の特性を活かした、画期的な「日本語文学」である。
では、冒頭ちかくのこの場面で作品の雰囲気をつかんで下さい。
人は誰でも死ぬのだから自分もいつかは死ぬし、次の葬式はあの人か、それともこちらの人かと、まさか口にはしないけれども、そう考えることをとめられない。むしろそうやってお互いにお互いの死をゆるやかに思い合っている連帯感が、今日この時の空気をわずかばかり穏やかなものにして、みんなちょっと気持ちが明るくなっているようにも思えるのだ。
『 死んでいない者/滝口悠生/文藝春秋 』
霜の降りる前に/死んでいない者/
■『霜の降りる前に(上・下)/ヘニング・マンケル』 2016.4.9
『霜の降りる前に』を読みました。
鍵をかけることと鍵を開けることは人が日々営む根本的な行為のひとつだからだよ。人間の歴史を通して、鍵束に揺れる鍵の音が聞こえる。鍵は一つひとつ異なる歴史を物語るものだ。そして、今回の鍵の話しもその中の一つなのだ。
こんなすてきな言葉を作品に残し、ぼくとほぼ同じ歳のヘニング・マンケルが逝ってしまった。
肺がんでした。
この作品のなかで、生きることへの彼の姿勢を思わせる言葉を見つけました。
父の目に涙が光っていた。ステン・ヴィデーンが死んだという知らせだった。知らせてきたのはヴィデーンのつきあっていた若い娘のひとりだった。たぶん最後に彼がいっしょに暮らしていた子だろう。クルト・ヴァランダーにヴィデーンの死を知らせて"すべてうまくいった"という言葉を伝えるように言われたという。
「それ、どういう意味?」
「若いころ、ステンとおれはそう決めていたんだ。死を決闘の相手として見なすということだ。勝負はすでに決まっていても、相手が力つきてなんとかこっちを倒すだけの力しか残っていないところまで、最後までねばるということ。死ぬときは、そのような死に方をしようと二人で決めていたんだ。"すべてうまくいった"というのはそういう意味だ」
ヘニング・マンケルの人となりについては、「訳者あとがき」に言い尽くされています。
ご一読下さい。
さて、この作品は、リンダとアンナの父と母と娘、祖父との家族の物語でもあります。
また、「信じる」ということについても考えさせられます。
地味なミステリーであり、かなり重たく感じられることもありましたが、がんばって読みとおしました。
それなりに面白く、味わい深いものがあります。
それにしても、リンダとヴァランダー父娘は、なぜあんなにもお互いに短気になるのでしょうか。
海に向かって、月に向かって、親に向かって大声で叫ぶ経験をしなければ、人は大人になれないもの。悲しみを経験したことのない王子や王女さまなんてなんてどうしょうもないから。そういう子たちは魂に麻酔薬を打たれたようなもの。わたしたち生きている人間は悲しみというものを知らなくちゃいけない
若いころは自分がしたいことがわからず悩んだ。自分の中に潜んでいるある種の苛立ち。
彼、あきらめたんだと思うの。いつか、何者かになるという夢は、夢でしかなかったんだと。
人には二種類ある、まっすぐで短い、もっとも早く目的地に到達する道を選ぶ人間と、回り道を選び、曲がりくねった道や険しい坂道があるほうを選ぶ人間と。
「駆け出しのころ、おれはリードベリからすべてを学んだ。彼もまた、ご多分に漏れず早く死んでしまった。だが、一言も愚痴らなかった。彼も人生のレースを何度か経験し、もう自分のレースのときは過ぎたということを受け入れた人間だった」
「おやじはそういう人間だった。おまえにとってはきっと別の人間だろうが」
「人はだれでも相手によってちがう自分を見せるんじゃない?」
「嘘つきが相手に嘘を信じ込ませるコツは、話の大部分が本当であること。その中に嘘を混ぜ込むの。そうすれば、嘘が真実のように聞こえるのよ。それで聞くほうはすべて本当だと思う。いつまでもってわけにはいかないけどね。話が嘘であることは早晩わかるから」
『 霜の降りる前に(上・下)/ヘニング・マンケル/柳沢由実子訳/創元推理文庫 』
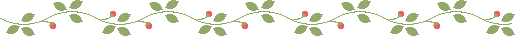
■『死んでいない者/滝口悠生』 2016.4.9
今回、初めて滝口悠生さんの作品を読みました。
『死んでいない者』は、ぼくには内容がよく理解できない作品でした。
それで、朝日新聞/2016.3.13/読書欄/大竹昭子さんの書評の助けを借りました。
第154回芥川賞受賞作。
まずタイトルで首をひねる。頭に「もう」をつけたらここに居ない死者に、「まだ」ならばこの世に留まっている生者になる。どちらともとれるが、この両義的なタイトルこそが作品のキモだ。
「お前さんは誰の息子?」
通夜の席ではおなじみの光景だ。故人とつながっているはずなのに、その結び目がわからない。
だが登場者の関係がつかみにくいのは意図的だ。全体に俯瞰する視点を著者はあえて避けている。
主語なしに成立する日本語の特性を活かした、画期的な「日本語文学」である。
では、冒頭ちかくのこの場面で作品の雰囲気をつかんで下さい。
人は誰でも死ぬのだから自分もいつかは死ぬし、次の葬式はあの人か、それともこちらの人かと、まさか口にはしないけれども、そう考えることをとめられない。むしろそうやってお互いにお互いの死をゆるやかに思い合っている連帯感が、今日この時の空気をわずかばかり穏やかなものにして、みんなちょっと気持ちが明るくなっているようにも思えるのだ。
『 死んでいない者/滝口悠生/文藝春秋 』














