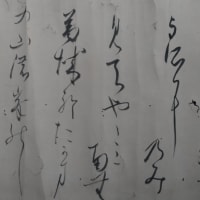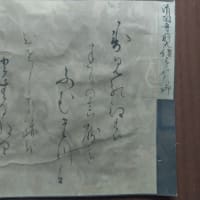※いんぶ門院の大輔
殷富門院大輔
※さぬき
二条院讃岐。源頼政女。正治二年後鳥羽院初度百首で久しぶりに出詠し、内裏百番歌合1216年(建保4年)が最後の出詠。
※みかはの内侍
二条院三河内侍。寂念女。七条院大納言の母。
※丹後
宜秋門院丹後。源頼行女。讃岐とは従姉妹。異浦の丹後。後鳥羽院御口伝では「故攝政は、かくよろしき由仰せ下さるゝ故に、老の後にかさ上がりたる由、たび/\申されき」。正治二年後鳥羽院初度百首に出詠し、住吉社歌合1208年(承元2年)まで出詠。
※少将
小侍従ではないかと言われる。正治二年後鳥羽院初度百首出詠。
コメント一覧

jikan314

kunorikunori
最新の画像もっと見る
最近の「新古今和歌集」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事