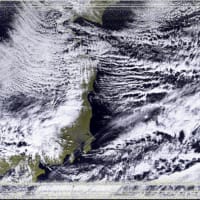岩手の宮古や瀬戸内海の因島に、和船を作れる職人が存在すると聞いていましたが、後継者がおらず、後何年かすると技術が伝承されず滅びてしまうようです。

画像提供Larusさん これは三浦半島で出土した縄文時代前期の丸木カヌー。縄文時代、海面は今よりず高く、三浦半島は入り江が深かった。その入り江の中を移動するために使われていたと考えられるカヌーだ。

伊豆半島の真鶴で見かけた櫓櫂舟。祭りに使う16櫓もある船だ。
瀬戸内海では昭和初期まで和船の帆掛け舟が大阪と地方を結んで行き来していたそうです。しかし、帆掛け舟の持ち主の半分以上は海で死んだと漁師さんが言ってました。最も怖いのは疾風(ハヤテ)という冬に吹く、北西風。長い時間は吹かないけど、あっと間に海上が地獄になるといいます。疾風で何人もの海の男が命を落としているそうです。
今や、船といえばFRP製。木船文化は滅びてしまうのであろうか。そうだとしたら残念でなりません。

朽ちた漁船が漁港に上げられていた。漁港ではまだ現役の木製漁船が係留されていた。瀬戸内海では小さな船の売り買いが盛んで、シーカヤックと同じくらいの値段で船(ここでは小伝馬船という)が手に入る。