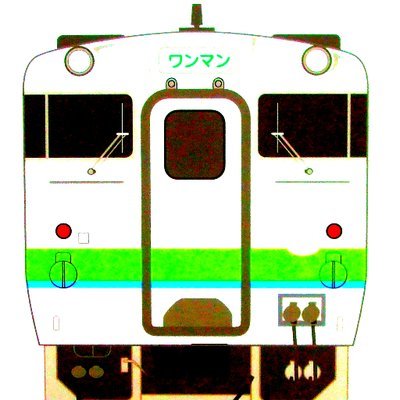私のツイッターの呟きへの反響が大きかったので、ブログで詳しくお話します。
「青函連絡船に乗ってみたかった」という方をタイムスリップして、冬型の気圧配置で低気圧が近づいた状況の下で乗せてあげたい。二度と乗りたいといわないだろうなw。女子は「キャー」、老婆は数珠を握って手を合わせる、まさに修羅場だよ・・・でも船員さんは平然としている。売店・食堂は当然閉鎖
以上がツイッターの内容です(●^o^●)。
まあ老婆が数珠を握って手を合わせたのは、小学生の頃に乗った夏場の連絡船でも見かけました。低気圧でも近づいていたのでしょうね。卑しくサラミを一本丸々食べてしまった私は、見事にそれをデッキから海に返還してしまい、母のそばで小さくなっていました。
86歳の母は、今でもその話を笑いながら話します。
冬、あまり時化るとデッキには出られないのですが、吹雪模様の中、デッキに出られたときの光景が忘れられません。左前方から北西の季節風が吹きつける中、船は風に流されるように右に船体を傾けながら進んでいました。
このまま流されて函館に着かないのではと心配したものです(笑)。
ですから冬は、風を背に受ける上り便は、あまり揺れなかったし、多少速かったような記憶があります。
陸奥湾を出て津軽海峡に入る頃には船の動揺は激しくなり、デッキは閉鎖されました。
食堂もレストランも閉鎖です。腹が減ると船酔いしやすくなるから困ったものです。
カレーライスが安くて旨かったですしね(●^o^●)。
吹雪で視界が悪いためか、頻繁に鳴る汽笛が恐怖感を煽ってくれます(+o+)。
やっと函館の桟橋に着いて地上に降りても、しばらくは揺れた感じが取れませんでした(´・ω・`)。
青函連絡船は津軽海峡で公海を通るわけですから、設備的にはしっかりしたものだったでしょうが、不安はいつも付いて回りました。
当時連絡船は500Khz辺りの周波数を使っていたのですが、AM変調された電信ですからAMラジオの選局ダイヤルの最も低いところでも聞けました。
電信の内容を聞くと、業務連絡と電報でした。
アマチュア無線が趣味の私の特権ですね。今では聞けませんが、いろいろと楽しめたものです。
上野を夕方に出る臨時の急行十和田が朝早く青森に着くと、連絡船がすぐにはありません。臨時列車には接続が悪かったようです。青森の広い待合室で2時間も待ってから乗船。臨時の連絡船で揺れて函館に着くと、またまた接続の列車がありません。そこで2時間くらい待って、学生時代に親の住んでいた小樽や登別に着くのは午後3時頃でした。下宿を出てから24時間と言った感じです。
ところが、それが楽しい思い出になっているのです。また乗りたいと思う・・・・不思議なものですね(笑)
「青函連絡船に乗ってみたかった」という方をタイムスリップして、冬型の気圧配置で低気圧が近づいた状況の下で乗せてあげたい。二度と乗りたいといわないだろうなw。女子は「キャー」、老婆は数珠を握って手を合わせる、まさに修羅場だよ・・・でも船員さんは平然としている。売店・食堂は当然閉鎖
以上がツイッターの内容です(●^o^●)。
まあ老婆が数珠を握って手を合わせたのは、小学生の頃に乗った夏場の連絡船でも見かけました。低気圧でも近づいていたのでしょうね。卑しくサラミを一本丸々食べてしまった私は、見事にそれをデッキから海に返還してしまい、母のそばで小さくなっていました。
86歳の母は、今でもその話を笑いながら話します。
冬、あまり時化るとデッキには出られないのですが、吹雪模様の中、デッキに出られたときの光景が忘れられません。左前方から北西の季節風が吹きつける中、船は風に流されるように右に船体を傾けながら進んでいました。
このまま流されて函館に着かないのではと心配したものです(笑)。
ですから冬は、風を背に受ける上り便は、あまり揺れなかったし、多少速かったような記憶があります。
陸奥湾を出て津軽海峡に入る頃には船の動揺は激しくなり、デッキは閉鎖されました。
食堂もレストランも閉鎖です。腹が減ると船酔いしやすくなるから困ったものです。
カレーライスが安くて旨かったですしね(●^o^●)。
吹雪で視界が悪いためか、頻繁に鳴る汽笛が恐怖感を煽ってくれます(+o+)。
やっと函館の桟橋に着いて地上に降りても、しばらくは揺れた感じが取れませんでした(´・ω・`)。
青函連絡船は津軽海峡で公海を通るわけですから、設備的にはしっかりしたものだったでしょうが、不安はいつも付いて回りました。
当時連絡船は500Khz辺りの周波数を使っていたのですが、AM変調された電信ですからAMラジオの選局ダイヤルの最も低いところでも聞けました。
電信の内容を聞くと、業務連絡と電報でした。
アマチュア無線が趣味の私の特権ですね。今では聞けませんが、いろいろと楽しめたものです。
上野を夕方に出る臨時の急行十和田が朝早く青森に着くと、連絡船がすぐにはありません。臨時列車には接続が悪かったようです。青森の広い待合室で2時間も待ってから乗船。臨時の連絡船で揺れて函館に着くと、またまた接続の列車がありません。そこで2時間くらい待って、学生時代に親の住んでいた小樽や登別に着くのは午後3時頃でした。下宿を出てから24時間と言った感じです。
ところが、それが楽しい思い出になっているのです。また乗りたいと思う・・・・不思議なものですね(笑)