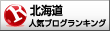道々あやは自分の生き方の頑さと、情のなさを噛みしめていた。
今までのことは置くとしても、この地に帰ると決めた時、何を置いても訪ねなければならない赤
間家のことを後に回していた。
あの家のことがそんなにも遠い過去のことになってしまっていたのか。
他ならぬあの家のことを、私が持たぬもの、私が失ったものの多くを捕ってくれたあの家のこと
を、ただの儀礼的にしか考えられなくなっていた。
やはり、未だに10歳で父と母を同時に失った日の記憶が疎ましいのだ。
振り返れば必ずあの日のことに回帰する。それがたまらなく厭なのだ。
それで気が付けばここで過ごした多くの時間を、記憶の底に押しこめてしまった。
ごまかしようがない。今日二人に会うことを願っていなかったのは、紛れもない事実だ。たまた
まの偶然が事態を強引に曳いていく。
あやの足どりは重かった。
みやげすら持っていない。やはり最初に感じた通り今日はまずい。何度も出直そうと思ったが、
千恵の涙がそんな言い訳を阻んだ。
この際自身の本当の姿が晒されるのは避けようもない。
「私は情の欠けたけちな人間なのだ」
みじめな暗い気分だった。
この期に及んでもなお表面を繕うことばかりを考えている。
改めて赤間の家の人達に罪を感じた。
未だ耕耘の始まらない剥き出しの畑地の中に、変わらない赤いトタン屋根の二階屋を見た時、
思わず胸が詰まった。