春に薬師寺を訪ねた。
実家から歩いて二十分くらいの道のり。
境内には豆粒ほどの小石が敷きつめられて
いて歩きづらい。
二歳の息子は一歩踏み出したとたん、ころ
がってしまった。
金堂をめぐり、東塔に向かう。
てっぺんの相輪(そうりん)まで三十四メ
ートルある。
建立は天平二年、西暦七百三十年と伝えら
れ、三軒三重の本瓦ぶき、各層に裳階(もこ
し)を付けているせいで、六重にみえる。
まるで持統天皇のお姿を象徴しているかの
よう。優美な趣を呈している。
白壁はきめ細やかな肌を、裳階は着物の裾
を、綾なす柱は装飾品を思わせる。
反面、暗い歴史を背負う。
「この時代、天皇が政治を執ったといいま
すが、寺の配置をみると天皇家を看板として
実質的には藤原氏が権力を握っていたと思う。
そうすると、この美しい塔の背後にも歴史の
ひとこまの人間の権力意志、あるいは呪詛(じゅ
そ)そういうものが含まれているんじゃなか
ろうかと思います」
梅原猛氏の言葉である。
境内は子どもの頃の遊び場だった。
拝観料をとらない時分、どこからでも入り
込むこめ、あちこちかけまわった。
にもかかわらず、寺のどなたかが出てきて、
子どもを叱らなかった。
やりたい放題だったが、だれも樹木を傷つ
けたり落書きしたりしなかった。
夕刻、親子連れが目立ちはじめた。
露店が軒をならべると、子どもが勇んで店
先に集まった。
最終日の唯識会(ゆいしきえ)である。
僧たちが、声をそろえ、経を読み始めると
境内に異様な雰囲気をかもし出した。
寄り集まった人々のざわめきがやんだ。
彼らは次に何が起きるかを知っている。
今か今かとそれを待ちのぞむ。
金堂の回廊の奥座敷からひとりの僧が速足
で出る。
彼がくくりつけられた松明(たいまつ)の
束のひとつひとつに火をつけ始めた。
青竹がボンボンと鈍い音をはなつ。
松のまきが燃え上がると、わっとばかりに
群衆が回廊の下に集まる。
鬼追い式の始まりである。
ドンドン、ドンドン。
廊下を、誰かが踏み鳴らしている足音が、
私の耳にも届いた。
だれかが暴れてるようだ。
気の小さな私は恐怖でふるえる。
正体のわからぬ者が、燃えさかる松明の一
部を抜き取ると、はやしたてる群衆に向かっ
てうおっと叫び、それらを振りまわした。
バシッ、バシッ。
松明が、回廊の手すりに、何度も打ち下ろ
される。
そのたびに、火の粉がはじけ飛ぶ。
私はただ怖くて怖くて、地面にうずくまっ
たままだ。
だれがそんな乱暴を働いているかなど、見
届けることもできずにいた。
「こっちだこっちだ。来い、来い。鬼めが、
夜叉めが」
わたしのまわりで、嬌声があがる。
鬼が怒りに怒って、燃え上がる青竹を、思
う存分に振りまわす。
「あのおっちゃん、きっと大酒でも食らっ
てるんや。ふらふらしてる」
私はぽつりとつぶやく。
鬼が回廊のかどをまわってしまうと。一瞬
静けさがあたりを支配する。
今度はだれだろう。
松明を右手でかかげた、妙な服装を身に着
けた者が、ゆっくりと走っていく。
「よっ、びしゃもんてん」
だれかが叫んだ。
火の粉を浴びると、その年ずっと、病気に
ならないと信じられている。
「万有は唯識である」
と説く法相宗の名物行事である。
実家から歩いて二十分くらいの道のり。
境内には豆粒ほどの小石が敷きつめられて
いて歩きづらい。
二歳の息子は一歩踏み出したとたん、ころ
がってしまった。
金堂をめぐり、東塔に向かう。
てっぺんの相輪(そうりん)まで三十四メ
ートルある。
建立は天平二年、西暦七百三十年と伝えら
れ、三軒三重の本瓦ぶき、各層に裳階(もこ
し)を付けているせいで、六重にみえる。
まるで持統天皇のお姿を象徴しているかの
よう。優美な趣を呈している。
白壁はきめ細やかな肌を、裳階は着物の裾
を、綾なす柱は装飾品を思わせる。
反面、暗い歴史を背負う。
「この時代、天皇が政治を執ったといいま
すが、寺の配置をみると天皇家を看板として
実質的には藤原氏が権力を握っていたと思う。
そうすると、この美しい塔の背後にも歴史の
ひとこまの人間の権力意志、あるいは呪詛(じゅ
そ)そういうものが含まれているんじゃなか
ろうかと思います」
梅原猛氏の言葉である。
境内は子どもの頃の遊び場だった。
拝観料をとらない時分、どこからでも入り
込むこめ、あちこちかけまわった。
にもかかわらず、寺のどなたかが出てきて、
子どもを叱らなかった。
やりたい放題だったが、だれも樹木を傷つ
けたり落書きしたりしなかった。
夕刻、親子連れが目立ちはじめた。
露店が軒をならべると、子どもが勇んで店
先に集まった。
最終日の唯識会(ゆいしきえ)である。
僧たちが、声をそろえ、経を読み始めると
境内に異様な雰囲気をかもし出した。
寄り集まった人々のざわめきがやんだ。
彼らは次に何が起きるかを知っている。
今か今かとそれを待ちのぞむ。
金堂の回廊の奥座敷からひとりの僧が速足
で出る。
彼がくくりつけられた松明(たいまつ)の
束のひとつひとつに火をつけ始めた。
青竹がボンボンと鈍い音をはなつ。
松のまきが燃え上がると、わっとばかりに
群衆が回廊の下に集まる。
鬼追い式の始まりである。
ドンドン、ドンドン。
廊下を、誰かが踏み鳴らしている足音が、
私の耳にも届いた。
だれかが暴れてるようだ。
気の小さな私は恐怖でふるえる。
正体のわからぬ者が、燃えさかる松明の一
部を抜き取ると、はやしたてる群衆に向かっ
てうおっと叫び、それらを振りまわした。
バシッ、バシッ。
松明が、回廊の手すりに、何度も打ち下ろ
される。
そのたびに、火の粉がはじけ飛ぶ。
私はただ怖くて怖くて、地面にうずくまっ
たままだ。
だれがそんな乱暴を働いているかなど、見
届けることもできずにいた。
「こっちだこっちだ。来い、来い。鬼めが、
夜叉めが」
わたしのまわりで、嬌声があがる。
鬼が怒りに怒って、燃え上がる青竹を、思
う存分に振りまわす。
「あのおっちゃん、きっと大酒でも食らっ
てるんや。ふらふらしてる」
私はぽつりとつぶやく。
鬼が回廊のかどをまわってしまうと。一瞬
静けさがあたりを支配する。
今度はだれだろう。
松明を右手でかかげた、妙な服装を身に着
けた者が、ゆっくりと走っていく。
「よっ、びしゃもんてん」
だれかが叫んだ。
火の粉を浴びると、その年ずっと、病気に
ならないと信じられている。
「万有は唯識である」
と説く法相宗の名物行事である。










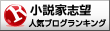






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます