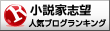第一波、第二波、そして第三波。
やれ、もうこれで終わりだろうとほっとしたのもつかの間、
またまた、波が押し寄せて来そうな勢い。
十年前の東日本大震災時のつなみの話ではない。
新型コロナウイルスの世界的大流行についてのものだ。
これは困った。もっと早く、流行が収まるんじゃなかった
のか。思わずそう嘆き、ため息をつく。
後ろ向きにばかり、人生をみつめるようになり、日々、体
力の衰えが気になる。目、耳、歯などの衰えぶりに頭をかか
え、かかりつけ医のお手をわずらわせてばかりいる。
そんなわたしどもは、一体、この事態にどう対処したもの
かと戸惑うばかりである。
従来のウイルスに加え、今度はあらてのものだという。
みなさん、よくご存じの変異株。
英国型とかなにやらと、いろんな種類があるようで、はて、
どこからそれらが国内に入ってきたものやらと、首を傾げて
しまう。
横浜港に着いた豪華客船のことは、よく知っている。
政府がすばやく、対策をこうじられ。ああさすが、我が国
の防疫体制はととのっているなと感心した。
水際対策とやらで、白い防御服を身に着けた人々が奮闘さ
れた。わたしは、その光景を、テレビをとおして、毎日、祈
るような気持ちで観ていた。
それは確か、去年の初めのこと。彼らの奮闘努力のおかげ
で、その後しばらくは、感染者も、ずいぶんとうちわで、あ
あ良かったと、胸をなでおろした。
それから数か月のうちに、大流行が始まった。
ホテルにとめおかれ、二週間、様子を観察されていた乗客
たちの方々の身の上を思いやった。
その後、欧州や他の国々で、感染が大流行となり、渡欧し
ていた我が国の人々が、飛行機で帰国されるようになった。
その際も、防疫体制が、きちんと働いたはずだったが、実
際はいかがなものだったろう。
若干の器具を抱かざるをえない。
先日テレビで、いずれかの医療関係の大学の先生のご意見
を拝聴する機会があった。
なにやら、それにやられると、従来のものより重症化する
リスクが高いとおっしゃる。ほかにも重要なことをいくつか
おっしゃったように思うが、忘れてしまった。
さて、新型コロナワクチンに対するワクチン接種のことだ
が、それは、初め、医療関係者に対して行われた。
ちょっとばかり、アレルギー体質のわたしは副反応が気が
かりで、そのことにおおいに注目していた。
アナフィラキー・ショックが、その最たるものである。
政府・厚労省が懸命に努力され、手に入れられたワクチン。
欧米の方にくらべ、ちよっと、副反応の割合が高いなと思
った。
どうしてだろう。わたしは考え込んでしまった。我が国に
おける流行をみていると、罹患された人々の重症率が低い。
小さいころから、BCGや麻疹など、きちんと接種を受けて
いるせいだろうか。
わたしなどが悩んだところで、どうなるものでもない。
ここで、今は亡き著名な批評家、小林秀雄さんに登場いた
だこう。
以下は「考えるヒント」からの抜粋。
「さて、そういう次第で、原稿の先きを続けるわけである
が、常識を守ることは難しいのである。文明が、やたらに専
門家を要求しているからだ。私達常識人は、専門的知識に、お
どかされ通しで、気が弱くなっている。私のように、常識の
健全性を、専門家に確かめてもらうというような面白くない
事にもなる。機械だってそうで、私達には、日に新たな機械
の生活上の利用で手一杯で、その原理や構造に通ずる暇なぞ
誰にもありはしない。科学の成果を、ただ実生活の上で利
用するに足るだけの生半可な科学的知識を、私達は持ってい
るに過ぎない。これは致し方のない事だとしても、そんな生
半可の知識でも、ともかく知識である事には変わりはないと
いう馬鹿な考えは捨てた方がよい。その点では、現代の知識
人の多くが、どうにもならぬ科学軽信家になり下がっている
ように思われる。少し常識を働かせて反省すれば、私達の置
かれている実情ははっきりするであろう。どうしてどんな具
合に利くのかは知らずに、ペニシリンの注射をして貰う私達
の精神の実情は、未開地の土人の頭脳状態とさしたる変わり
はない筈だ。一方、常識人をあなどり、何かと言えば、専門
家風を吹かしたがる専門家達にしてみても、専門外の学問に
ついては、無知蒙昧であるより他はあるまい。この不思議な
傾向は、日々深刻になるであろう」
きたるべきワクチン接種に、私達は、どのような態度での
ぞめばよいのだろう。
やれ、もうこれで終わりだろうとほっとしたのもつかの間、
またまた、波が押し寄せて来そうな勢い。
十年前の東日本大震災時のつなみの話ではない。
新型コロナウイルスの世界的大流行についてのものだ。
これは困った。もっと早く、流行が収まるんじゃなかった
のか。思わずそう嘆き、ため息をつく。
後ろ向きにばかり、人生をみつめるようになり、日々、体
力の衰えが気になる。目、耳、歯などの衰えぶりに頭をかか
え、かかりつけ医のお手をわずらわせてばかりいる。
そんなわたしどもは、一体、この事態にどう対処したもの
かと戸惑うばかりである。
従来のウイルスに加え、今度はあらてのものだという。
みなさん、よくご存じの変異株。
英国型とかなにやらと、いろんな種類があるようで、はて、
どこからそれらが国内に入ってきたものやらと、首を傾げて
しまう。
横浜港に着いた豪華客船のことは、よく知っている。
政府がすばやく、対策をこうじられ。ああさすが、我が国
の防疫体制はととのっているなと感心した。
水際対策とやらで、白い防御服を身に着けた人々が奮闘さ
れた。わたしは、その光景を、テレビをとおして、毎日、祈
るような気持ちで観ていた。
それは確か、去年の初めのこと。彼らの奮闘努力のおかげ
で、その後しばらくは、感染者も、ずいぶんとうちわで、あ
あ良かったと、胸をなでおろした。
それから数か月のうちに、大流行が始まった。
ホテルにとめおかれ、二週間、様子を観察されていた乗客
たちの方々の身の上を思いやった。
その後、欧州や他の国々で、感染が大流行となり、渡欧し
ていた我が国の人々が、飛行機で帰国されるようになった。
その際も、防疫体制が、きちんと働いたはずだったが、実
際はいかがなものだったろう。
若干の器具を抱かざるをえない。
先日テレビで、いずれかの医療関係の大学の先生のご意見
を拝聴する機会があった。
なにやら、それにやられると、従来のものより重症化する
リスクが高いとおっしゃる。ほかにも重要なことをいくつか
おっしゃったように思うが、忘れてしまった。
さて、新型コロナワクチンに対するワクチン接種のことだ
が、それは、初め、医療関係者に対して行われた。
ちょっとばかり、アレルギー体質のわたしは副反応が気が
かりで、そのことにおおいに注目していた。
アナフィラキー・ショックが、その最たるものである。
政府・厚労省が懸命に努力され、手に入れられたワクチン。
欧米の方にくらべ、ちよっと、副反応の割合が高いなと思
った。
どうしてだろう。わたしは考え込んでしまった。我が国に
おける流行をみていると、罹患された人々の重症率が低い。
小さいころから、BCGや麻疹など、きちんと接種を受けて
いるせいだろうか。
わたしなどが悩んだところで、どうなるものでもない。
ここで、今は亡き著名な批評家、小林秀雄さんに登場いた
だこう。
以下は「考えるヒント」からの抜粋。
「さて、そういう次第で、原稿の先きを続けるわけである
が、常識を守ることは難しいのである。文明が、やたらに専
門家を要求しているからだ。私達常識人は、専門的知識に、お
どかされ通しで、気が弱くなっている。私のように、常識の
健全性を、専門家に確かめてもらうというような面白くない
事にもなる。機械だってそうで、私達には、日に新たな機械
の生活上の利用で手一杯で、その原理や構造に通ずる暇なぞ
誰にもありはしない。科学の成果を、ただ実生活の上で利
用するに足るだけの生半可な科学的知識を、私達は持ってい
るに過ぎない。これは致し方のない事だとしても、そんな生
半可の知識でも、ともかく知識である事には変わりはないと
いう馬鹿な考えは捨てた方がよい。その点では、現代の知識
人の多くが、どうにもならぬ科学軽信家になり下がっている
ように思われる。少し常識を働かせて反省すれば、私達の置
かれている実情ははっきりするであろう。どうしてどんな具
合に利くのかは知らずに、ペニシリンの注射をして貰う私達
の精神の実情は、未開地の土人の頭脳状態とさしたる変わり
はない筈だ。一方、常識人をあなどり、何かと言えば、専門
家風を吹かしたがる専門家達にしてみても、専門外の学問に
ついては、無知蒙昧であるより他はあるまい。この不思議な
傾向は、日々深刻になるであろう」
きたるべきワクチン接種に、私達は、どのような態度での
ぞめばよいのだろう。