利休なき後、天下の茶匠は古田織部、後に小堀遠州へと移っていきました。
ともに利休茶をそのまま移すことなく、新しい時代を切り拓くべく独自の茶を創作した「作意」の人。
今回は、織部・遠州の人となりをしのぶ逸話を拾いました。
■古田織部
利休、各々昼の参会の席にて、
「勢多の橋の擬法師(ぎぼし)(擬宝珠)の中に、形(なり)のみごとなるが二つ有り。見分くる人なきにや」
とたかたる。
その座に古織居られたるが、俄(にわか)に見えず。何(いず)れもあやしむ所に、晩方かえりまいられたれば、休、
「何の御用候えつるぞ」
といえば、
「いや、別儀も候わず。彼のぎぼうし、試(ためし)に見分け申さんため、はや打ちにて勢多へ参り、只今かえり候也。さて、二つの擬法師は、東西のそこそこにてや候」
と問われたれば、休、
「いかにもそれにて候」
と答う。一座の人々、古織の執心、ことに感じ申されき。
〔ひとこと〕
美を追求せずにはいられない業。それは、師にも弟子にもついには悲劇を招いてしまいました。たかが、ぎほしひとつ。つかれたように瀬田へ馬を疾走させる、夕闇の織部の姿に"数奇の鬼"をありありと感じさせる逸話です。
■小堀遠州
雲山といえる肩衝、堺の人所持したるが、利休など招きて、はじめて茶の湯に出だしたれば、休、一向気に入らぬ躰(てい)也。亭主、客帰りて後、
「当世、休が気にいらぬ茶入、面白からず」
とて、五徳に擲(なげう)ち破(わ)りけるを、傍(かたわ)らに有りける知音の人もろうて帰り、手ずから継ぎて茶会を催し、ふたたび休にみせたれば、
「是でこそ茶入見事なれ」
とて、ことの外(ほか)称美(しょうび)す。よて此の趣き、もとの持ち主へいいやり、
「茶入秘蔵せられよ」
とて戻しぬ。その後、件の肩衝、丹後の太守※、値千金に御求め候て、むかしの継ぎ目、ところどころ合わざりけるを、
「継ぎなおし候わんや」
と小堀遠州へ相談候えば、遠州、
「此の肩衝破れ候て、つぎめも合わぬにてこそ利休おもしろがり、名高くも聞こえ侍れ。かようの物は、そのままにて置くがよく候」
と申されき。
古織、全き茶碗はぬるき物とて、わざと欠きて用いられしことあり。
※丹後の太守 京極高広(慶長4年1599年~延宝5年1677年) 丹後宮津藩の第ニ代藩主。
〔ひとこと〕
貴重な唐物名物を眉ひとつ動かすことなく、無慈悲に打ち割る、紹鴎、利休、織部。師から弟子へ、数奇の系譜がたどれる逸話です。しかし「当世、休が気にいらぬ茶入、面白からず」は、かの天正19年2月28日、美の終焉を予期させる不吉な予言ではなかったでしょうか。
■織部と遠州
桑山左近、宗易へ露地のしつらいよういかが、と尋ね申され候時、
樫の葉のもみぢぬからにちりつもる 奥山寺の道のさびしさ
この古歌一首にて御得心候えとなり。
附たり
遠州公も、去る人のもとへ庭の心入れ是にて御合点候えと御つかはし候発句、
夕月夜海すこしある木間かな
古織は、山のあらわなるをきらいて、木間よりみゆるを、山に天井張りてよし、といわれしなり。遠州、古織の意にかなうものならし。
〔ひとこと〕
桑山左近と織部は、利休門下において犬猿の仲といわれる険悪な間柄。しかし、茶の湯の場では、こんな心温まるエピソードがあります。
http://nobunsha.jp/blog/post_93.html
茶庭に露地をしつらえ、たんなる庭を一期一会の精神的な修行の場とした利休。
利休は露地石について「渡りを六分、景気を四分」とし、織部は「景気を六分、渡りを四分」としました。渡りは歩行、つまり機能性。景気は景色、美的風景。利休はあくまで機能に根ざす美を露地庭に追求した。織部は機能重視主義の「山のあらわなる」を嫌いました。てのひらにおさまり、点てやすく、また服のよい楽茶碗ではなく、茶の場を独特の存在感で支配する「へうげもの」の織部茶碗を創作したのです。そして、遠州は織部の美を受け継いだが、美のため腹を切ることは決してありませんでした。
ともに利休茶をそのまま移すことなく、新しい時代を切り拓くべく独自の茶を創作した「作意」の人。
今回は、織部・遠州の人となりをしのぶ逸話を拾いました。
■古田織部
利休、各々昼の参会の席にて、
「勢多の橋の擬法師(ぎぼし)(擬宝珠)の中に、形(なり)のみごとなるが二つ有り。見分くる人なきにや」
とたかたる。
その座に古織居られたるが、俄(にわか)に見えず。何(いず)れもあやしむ所に、晩方かえりまいられたれば、休、
「何の御用候えつるぞ」
といえば、
「いや、別儀も候わず。彼のぎぼうし、試(ためし)に見分け申さんため、はや打ちにて勢多へ参り、只今かえり候也。さて、二つの擬法師は、東西のそこそこにてや候」
と問われたれば、休、
「いかにもそれにて候」
と答う。一座の人々、古織の執心、ことに感じ申されき。
〔ひとこと〕
美を追求せずにはいられない業。それは、師にも弟子にもついには悲劇を招いてしまいました。たかが、ぎほしひとつ。つかれたように瀬田へ馬を疾走させる、夕闇の織部の姿に"数奇の鬼"をありありと感じさせる逸話です。
■小堀遠州
雲山といえる肩衝、堺の人所持したるが、利休など招きて、はじめて茶の湯に出だしたれば、休、一向気に入らぬ躰(てい)也。亭主、客帰りて後、
「当世、休が気にいらぬ茶入、面白からず」
とて、五徳に擲(なげう)ち破(わ)りけるを、傍(かたわ)らに有りける知音の人もろうて帰り、手ずから継ぎて茶会を催し、ふたたび休にみせたれば、
「是でこそ茶入見事なれ」
とて、ことの外(ほか)称美(しょうび)す。よて此の趣き、もとの持ち主へいいやり、
「茶入秘蔵せられよ」
とて戻しぬ。その後、件の肩衝、丹後の太守※、値千金に御求め候て、むかしの継ぎ目、ところどころ合わざりけるを、
「継ぎなおし候わんや」
と小堀遠州へ相談候えば、遠州、
「此の肩衝破れ候て、つぎめも合わぬにてこそ利休おもしろがり、名高くも聞こえ侍れ。かようの物は、そのままにて置くがよく候」
と申されき。
古織、全き茶碗はぬるき物とて、わざと欠きて用いられしことあり。
※丹後の太守 京極高広(慶長4年1599年~延宝5年1677年) 丹後宮津藩の第ニ代藩主。
〔ひとこと〕
貴重な唐物名物を眉ひとつ動かすことなく、無慈悲に打ち割る、紹鴎、利休、織部。師から弟子へ、数奇の系譜がたどれる逸話です。しかし「当世、休が気にいらぬ茶入、面白からず」は、かの天正19年2月28日、美の終焉を予期させる不吉な予言ではなかったでしょうか。
■織部と遠州
桑山左近、宗易へ露地のしつらいよういかが、と尋ね申され候時、
樫の葉のもみぢぬからにちりつもる 奥山寺の道のさびしさ
この古歌一首にて御得心候えとなり。
附たり
遠州公も、去る人のもとへ庭の心入れ是にて御合点候えと御つかはし候発句、
夕月夜海すこしある木間かな
古織は、山のあらわなるをきらいて、木間よりみゆるを、山に天井張りてよし、といわれしなり。遠州、古織の意にかなうものならし。
〔ひとこと〕
桑山左近と織部は、利休門下において犬猿の仲といわれる険悪な間柄。しかし、茶の湯の場では、こんな心温まるエピソードがあります。
http://nobunsha.jp/blog/post_93.html
茶庭に露地をしつらえ、たんなる庭を一期一会の精神的な修行の場とした利休。
利休は露地石について「渡りを六分、景気を四分」とし、織部は「景気を六分、渡りを四分」としました。渡りは歩行、つまり機能性。景気は景色、美的風景。利休はあくまで機能に根ざす美を露地庭に追求した。織部は機能重視主義の「山のあらわなる」を嫌いました。てのひらにおさまり、点てやすく、また服のよい楽茶碗ではなく、茶の場を独特の存在感で支配する「へうげもの」の織部茶碗を創作したのです。そして、遠州は織部の美を受け継いだが、美のため腹を切ることは決してありませんでした。















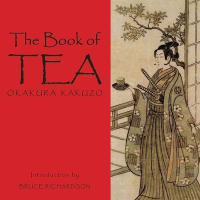

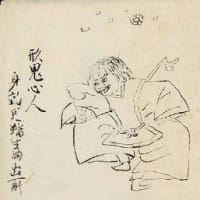


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます