
花見んと群れつつ人の来るのみぞ
あたら桜の咎にはありける
今回は西行を題材とした能の名作「西行桜」をご紹介しましょう。
古来より日本人にとって花といえば、ただ桜の一種のみをさしました。日本人の心の中に咲く花はいつの時代にも桜。秋は月見、春は花見です。
現在の”飲めや歌えや”ドンちゃん騒ぎの花見は、実は豊臣秀吉の醍醐の花見から始まったといわれています。慶長3年3月15日京都の醍醐寺において、約1300名の類縁者、家臣を集めて開催された秀吉生涯最後の一代イベントでした。むろん平安、鎌倉時代にも秀吉ほどではないにせよ、上つ方より下々に到るまで花見の宴は、日本人のもっとも楽しみとする春のイベントでした。
西行の隠棲する山奥の庵に毎年見事な花をつける桜樹があったことが、そもそも事件の始まり。一人静かに散る桜に、去り行く春の名残を愛でようとした庵主が、騒々しい花見客を揶揄したのが、冒頭の歌でした。
以下、能「西行桜」の概要をお伝えします。
■能 西行桜
曲名: 西行桜《さいぎょうざくら》
作者: 世阿弥 出典:『山家集』 季節: 春(旧暦3月)
場所: 京・西山西行庵 分類: 三番目物・一場 上演時間: 約1時間30分
登場人物:〔シテ〕桜木の精、〔ワキ〕西行法師、〔ワキツレ〕花見の人々、〔アイ〕西行庵の能力[寺の下働きの男]
〈解説〉
世阿弥『申楽談儀』に「西行・阿古屋の松、大かた似たる能也。後の世、かかる能書く者や有まじきと覚へて、此二番は書き置く也」と述べられています。また『五音』には「西行歌」として、現在の「西行桜」のワキの謡と同じ詞章がのせられているので、「西行の能」は「西行桜」のことであろうと考えられます。「西行桜」は、桜の老木のもとで眠る西行の夢の中に、桜の精が老翁の姿で現れて舞を舞う、老体の能として書かれています。老体の能は、世阿弥『風姿花伝』によれば「たゞ、老木に花の咲かんがごとし」といった、幽玄で趣の深い能。曲種としては三番目ですが、老体の神が舞う初番目にも近い、高雅な春の能といえましょう。
〈あらすじ〉
京都、西山に隠棲する西行の庵室。春ごとにここは見事な桜の花にひかれ貴賤群集が訪ねて来る。西行は思う所があって今年はここでの花見禁制を召使いに申しつける。しかし都の人々は例年通り春に浮かれ、この西山に花見のために押しかける。
西行は一人花を愛で、梢に咲き上がっていく春の花に悟りを求める向上心を見、秋の月が水に姿を映す様に悟りに遠い衆生を教え救う志を思い、そうした自然の啓示がそのまま仏を見、注文を聞く縁となるのだと観ずる。
花見人たちが案内を乞う。静かな観想の時を破られた西行は、しかし、遙々訪ね来た人々の志に感じ、庵の戸を開かせる。世を捨てたとはいえ、この世の他には棲家はない、どうして隠れたままでいられようかと内省し、「花見んと群れつつ人の来るのみぞあたら桜の咎にはありける」と詠ずる。西行は人々とともに夜すがら桜を眺め明かそうと木陰に休らう。
その夢に老桜の精が現れる。埋もれ木の人に知られぬ身となってはいるが、心には未だ花やかさが残るといい、先程の西行の歌を詠じ、厭わしいと思うのも人の心であり、非情無心の草木に咎はないと西行を諭す。老桜の精は桜の名所を数えあげ、春の夜のひとときを惜しみ、閑寂なる舞を寂び寂びと舞う。
やがて花影が仄かに白むうちにも西行の夢は覚め、老桜の姿は消え失せ、老木の桜が薄明かりのなかにひそやかに息づいているのであった。
あたら桜の咎にはありける
今回は西行を題材とした能の名作「西行桜」をご紹介しましょう。
古来より日本人にとって花といえば、ただ桜の一種のみをさしました。日本人の心の中に咲く花はいつの時代にも桜。秋は月見、春は花見です。
現在の”飲めや歌えや”ドンちゃん騒ぎの花見は、実は豊臣秀吉の醍醐の花見から始まったといわれています。慶長3年3月15日京都の醍醐寺において、約1300名の類縁者、家臣を集めて開催された秀吉生涯最後の一代イベントでした。むろん平安、鎌倉時代にも秀吉ほどではないにせよ、上つ方より下々に到るまで花見の宴は、日本人のもっとも楽しみとする春のイベントでした。
西行の隠棲する山奥の庵に毎年見事な花をつける桜樹があったことが、そもそも事件の始まり。一人静かに散る桜に、去り行く春の名残を愛でようとした庵主が、騒々しい花見客を揶揄したのが、冒頭の歌でした。
以下、能「西行桜」の概要をお伝えします。
■能 西行桜
曲名: 西行桜《さいぎょうざくら》
作者: 世阿弥 出典:『山家集』 季節: 春(旧暦3月)
場所: 京・西山西行庵 分類: 三番目物・一場 上演時間: 約1時間30分
登場人物:〔シテ〕桜木の精、〔ワキ〕西行法師、〔ワキツレ〕花見の人々、〔アイ〕西行庵の能力[寺の下働きの男]
〈解説〉
世阿弥『申楽談儀』に「西行・阿古屋の松、大かた似たる能也。後の世、かかる能書く者や有まじきと覚へて、此二番は書き置く也」と述べられています。また『五音』には「西行歌」として、現在の「西行桜」のワキの謡と同じ詞章がのせられているので、「西行の能」は「西行桜」のことであろうと考えられます。「西行桜」は、桜の老木のもとで眠る西行の夢の中に、桜の精が老翁の姿で現れて舞を舞う、老体の能として書かれています。老体の能は、世阿弥『風姿花伝』によれば「たゞ、老木に花の咲かんがごとし」といった、幽玄で趣の深い能。曲種としては三番目ですが、老体の神が舞う初番目にも近い、高雅な春の能といえましょう。
〈あらすじ〉
京都、西山に隠棲する西行の庵室。春ごとにここは見事な桜の花にひかれ貴賤群集が訪ねて来る。西行は思う所があって今年はここでの花見禁制を召使いに申しつける。しかし都の人々は例年通り春に浮かれ、この西山に花見のために押しかける。
西行は一人花を愛で、梢に咲き上がっていく春の花に悟りを求める向上心を見、秋の月が水に姿を映す様に悟りに遠い衆生を教え救う志を思い、そうした自然の啓示がそのまま仏を見、注文を聞く縁となるのだと観ずる。
花見人たちが案内を乞う。静かな観想の時を破られた西行は、しかし、遙々訪ね来た人々の志に感じ、庵の戸を開かせる。世を捨てたとはいえ、この世の他には棲家はない、どうして隠れたままでいられようかと内省し、「花見んと群れつつ人の来るのみぞあたら桜の咎にはありける」と詠ずる。西行は人々とともに夜すがら桜を眺め明かそうと木陰に休らう。
その夢に老桜の精が現れる。埋もれ木の人に知られぬ身となってはいるが、心には未だ花やかさが残るといい、先程の西行の歌を詠じ、厭わしいと思うのも人の心であり、非情無心の草木に咎はないと西行を諭す。老桜の精は桜の名所を数えあげ、春の夜のひとときを惜しみ、閑寂なる舞を寂び寂びと舞う。
やがて花影が仄かに白むうちにも西行の夢は覚め、老桜の姿は消え失せ、老木の桜が薄明かりのなかにひそやかに息づいているのであった。















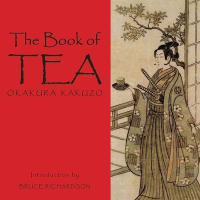

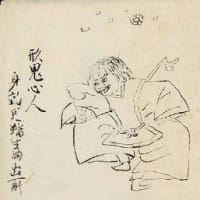


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます