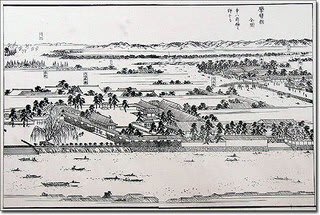八月以来のごぶさたでした。
来春公演の芝居の脚本に手こずっていました。
高齢者ばかりの船旅ツアーの物語です。
役者の数や場面転換など芝居には制約が多いので苦労です。
オリジナルなのに(先回はもう一つの林芙美子で資料あさりが大変でしたが)オリジナルだからこその悲壮さも相まって「書けません~!」と断ろうかと思った程でした。
同居人に訴えても「毎度のことじゃないか」と相手にもしてくれず、夜中に起きだしてはシコシコ紡いでおりました。
おまけに白内障の手術も決まって検査とかいろいろ。
コレが終わればもっとキーボードもうちやすくなるのでしょうか。
眼球にメス!!もう、怖くて怖くて…先輩方はたいしたことないと皆さん言われますがこわがりなんです。
さらにふと見たサイトで衝動的にiphone5のゴールドを申し込んでいましたら、忘れた頃に入荷のお知らせがあり。
こちらも奮闘努力中。なにしろ、auのお姉さんの不手際でアドレス帳の移行ができなかったのです(号泣)
それでもなんとか脚本は脱稿しまして、先方も気に入って下さり二度の打ち合わせでやっと晴れて手が離れました。
この爽やかな気分は苦労しないと手に入らないものです。
そこで、ようやく『小梅日記』をひらけました。
相変わらず遅々とした歩みですが、気が向かれましたら覗いてやってください。
ただいま、小梅さんは師走に突入していますので同じ頃に新年を迎えられればいいのですが。
来春公演の芝居の脚本に手こずっていました。
高齢者ばかりの船旅ツアーの物語です。
役者の数や場面転換など芝居には制約が多いので苦労です。
オリジナルなのに(先回はもう一つの林芙美子で資料あさりが大変でしたが)オリジナルだからこその悲壮さも相まって「書けません~!」と断ろうかと思った程でした。
同居人に訴えても「毎度のことじゃないか」と相手にもしてくれず、夜中に起きだしてはシコシコ紡いでおりました。
おまけに白内障の手術も決まって検査とかいろいろ。
コレが終わればもっとキーボードもうちやすくなるのでしょうか。
眼球にメス!!もう、怖くて怖くて…先輩方はたいしたことないと皆さん言われますがこわがりなんです。
さらにふと見たサイトで衝動的にiphone5のゴールドを申し込んでいましたら、忘れた頃に入荷のお知らせがあり。
こちらも奮闘努力中。なにしろ、auのお姉さんの不手際でアドレス帳の移行ができなかったのです(号泣)
それでもなんとか脚本は脱稿しまして、先方も気に入って下さり二度の打ち合わせでやっと晴れて手が離れました。
この爽やかな気分は苦労しないと手に入らないものです。
そこで、ようやく『小梅日記』をひらけました。
相変わらず遅々とした歩みですが、気が向かれましたら覗いてやってください。
ただいま、小梅さんは師走に突入していますので同じ頃に新年を迎えられればいいのですが。