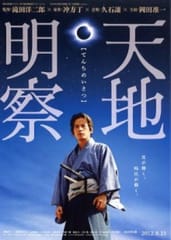看護学生の皆さんからいただいた質問ですが、
こんなプライベートなやつがまだ残っていました。
そして、この問いに対しては以前にお答えしたことがあるような気がして、
自分のブログ内をくまなく探し回っていたのですが、
どうやら一度も書いたことがなかったようです。
授業や飲み会の席ではたびたび話題にしているので、
学生たちも行きつけのお店の方々もみんなよーく知ってくださっていて、
気遣われたりネタにされたりいろいろなんですが、
それっぽいことを小出しにしたことはあっても、ブログではきちんと論じたことがありませんでした。
遅ればせながらここにしっかりと書き留めておこうと思います。
A.私はキュウリが大っ嫌いですっ!
いや 「嫌い」 という言葉ももったいないくらいです。
憎んでいます。
dislike ではなく hate です。
福島でこんなこと言うと多くの人を敵に回してしまうのですが、
(あ、だから今まで書かなかったのかな?)
味とか臭いとかがどうこうという問題ではなく、キュウリの存在自体が許せません。
天然痘やエイズウィルスとともにこの世から撲滅してもかまわないとまで思っています。
(この問題になると私のなかの自由主義は破綻します)
食わず嫌いではありません。
人生で一度だけ食べたことがあります。
子どもの頃キュウリばかりでなく、ホウレンソウ以外の野菜類がすべて食べられなかった私は、
小学校時代にある転機を迎えてしまいました。
給食の時間は担任の先生とのガマン比べで、昼休みの時間をすべて棒に振っても、
頑として野菜を食べずにすませていた私ですが、
どうしても野菜を食べないわけにはいかない局面に立たされてしまったのです。
家庭科の調理実習です。
自分たちで初めて作った料理ですから、さすがの私も手をつけないわけにはいきません。
その日はご飯を炊き、味噌汁を作り、トマトとキュウリのサラダを作ることになっていました。
トマトとキュウリ。
見るからにグロテスクです。
むろんそれまで一度も口にしたことはありません。
私の予想ではトマトは絶対にムリだろうなという気がしていました。
あの色といい、中のトロッとした部分といい、破壊力抜群です。
それに比べるとキュウリはまだおとなしい感じです。
外側のイボイボは強烈ですが、薄切りにしてしまえばなんとなく何とかなりそうな存在感の薄さです。
とにかく目をつぶって呑み込んでしまおうと決め当日を迎えました。
みんなはミョーなテンションで楽しげに料理をしていましたが、
私は料理がだんだん形をなしていくにつれどんどんブルーになっていきました。
そしてとうとうその時が来てしまいました。
覚悟を決めて先にヤバそうなやつを片づけてしまおうと思い、まずはトマトを口に放り込みました。
ものすごい衝撃が押し寄せることを覚悟していましたが、予想していたほどではありませんでした。
フニャフニャ、ドロドロした口当たりは最悪でしたが、味そのものは耐えられないほどではありません。
今から思うと、おそらくケチャップは大好きでその味に慣れていたからかもしれません。
ダメだと思っていたトマトがこれくらいですんだのですから、
今日はこの調子で何とか乗り切れるかもしれません。
そう思ってちょっと余裕をこきながら、おとなしげなキュウリも口に入れました。
その瞬間に予想もしなかった衝撃が舌と口と全身を襲ったのです。
なんじゃ、こりゃあ
思わずその日食べたものを全部リバースしそうになりました。
えづきながら何とかその衝動を抑え込み、
味と臭いと存在に涙しながら永遠とも思われる時間をかけて嚥下しました。
あの日、家庭科調理室でアレを吐き出してしまわず、
泣きながら呑み込むことのできた自分を誇りに思います。
その後、その昼食がどうなったのかはまったく覚えていません。
あの一口の強烈な思い出以外、一切の記憶は失われてしまいました。
ただひとつ、これは人間の食べ物ではない、
二度と口にはしないと堅く心に誓ったのでした。
P.S.
これはあくまでもまさおさまの主観的な感想であり、個人的な好き嫌いにすぎません。
自分の言ってることが穏当を欠いているということは重々承知しております。
キュウリ好きの方々やキュウリ農家の方々を貶める意図はまったくありません。
ただ誠に申しわけないけど私は嫌いですというだけのことなのです。
不快な思いをさせてしまったかもしれませんが、子どもの戯言だと思ってお聞き流しください。
こんなプライベートなやつがまだ残っていました。
そして、この問いに対しては以前にお答えしたことがあるような気がして、
自分のブログ内をくまなく探し回っていたのですが、
どうやら一度も書いたことがなかったようです。
授業や飲み会の席ではたびたび話題にしているので、
学生たちも行きつけのお店の方々もみんなよーく知ってくださっていて、
気遣われたりネタにされたりいろいろなんですが、
それっぽいことを小出しにしたことはあっても、ブログではきちんと論じたことがありませんでした。
遅ればせながらここにしっかりと書き留めておこうと思います。
A.私はキュウリが大っ嫌いですっ!
いや 「嫌い」 という言葉ももったいないくらいです。
憎んでいます。
dislike ではなく hate です。
福島でこんなこと言うと多くの人を敵に回してしまうのですが、
(あ、だから今まで書かなかったのかな?)
味とか臭いとかがどうこうという問題ではなく、キュウリの存在自体が許せません。
天然痘やエイズウィルスとともにこの世から撲滅してもかまわないとまで思っています。
(この問題になると私のなかの自由主義は破綻します)
食わず嫌いではありません。
人生で一度だけ食べたことがあります。
子どもの頃キュウリばかりでなく、ホウレンソウ以外の野菜類がすべて食べられなかった私は、
小学校時代にある転機を迎えてしまいました。
給食の時間は担任の先生とのガマン比べで、昼休みの時間をすべて棒に振っても、
頑として野菜を食べずにすませていた私ですが、
どうしても野菜を食べないわけにはいかない局面に立たされてしまったのです。
家庭科の調理実習です。
自分たちで初めて作った料理ですから、さすがの私も手をつけないわけにはいきません。
その日はご飯を炊き、味噌汁を作り、トマトとキュウリのサラダを作ることになっていました。
トマトとキュウリ。
見るからにグロテスクです。
むろんそれまで一度も口にしたことはありません。
私の予想ではトマトは絶対にムリだろうなという気がしていました。
あの色といい、中のトロッとした部分といい、破壊力抜群です。
それに比べるとキュウリはまだおとなしい感じです。
外側のイボイボは強烈ですが、薄切りにしてしまえばなんとなく何とかなりそうな存在感の薄さです。
とにかく目をつぶって呑み込んでしまおうと決め当日を迎えました。
みんなはミョーなテンションで楽しげに料理をしていましたが、
私は料理がだんだん形をなしていくにつれどんどんブルーになっていきました。
そしてとうとうその時が来てしまいました。
覚悟を決めて先にヤバそうなやつを片づけてしまおうと思い、まずはトマトを口に放り込みました。
ものすごい衝撃が押し寄せることを覚悟していましたが、予想していたほどではありませんでした。
フニャフニャ、ドロドロした口当たりは最悪でしたが、味そのものは耐えられないほどではありません。
今から思うと、おそらくケチャップは大好きでその味に慣れていたからかもしれません。
ダメだと思っていたトマトがこれくらいですんだのですから、
今日はこの調子で何とか乗り切れるかもしれません。
そう思ってちょっと余裕をこきながら、おとなしげなキュウリも口に入れました。
その瞬間に予想もしなかった衝撃が舌と口と全身を襲ったのです。
なんじゃ、こりゃあ

思わずその日食べたものを全部リバースしそうになりました。
えづきながら何とかその衝動を抑え込み、
味と臭いと存在に涙しながら永遠とも思われる時間をかけて嚥下しました。
あの日、家庭科調理室でアレを吐き出してしまわず、
泣きながら呑み込むことのできた自分を誇りに思います。
その後、その昼食がどうなったのかはまったく覚えていません。
あの一口の強烈な思い出以外、一切の記憶は失われてしまいました。
ただひとつ、これは人間の食べ物ではない、
二度と口にはしないと堅く心に誓ったのでした。
P.S.
これはあくまでもまさおさまの主観的な感想であり、個人的な好き嫌いにすぎません。
自分の言ってることが穏当を欠いているということは重々承知しております。
キュウリ好きの方々やキュウリ農家の方々を貶める意図はまったくありません。
ただ誠に申しわけないけど私は嫌いですというだけのことなのです。
不快な思いをさせてしまったかもしれませんが、子どもの戯言だと思ってお聞き流しください。