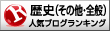昭和の終わりの深くなりつつある秋の日に、友人が若くしてこの世を去り、その訃報を聞いた日に、私は一日中、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を聴いていた。
その友人は下町生まれで、学校では近世文学を専攻していた。とくに『醒酔笑』など、江戸のお笑いについて研究していて、電車の中で謎かけをしたりしていた。当世流行の「なぞかけ」であるが、そのころは、何年かごとにやってくるお笑いブームの狭間のような時期で、世間にははばかられる、ちょっとシブイ遊びだった。
友人は地下鉄銀座線をこよなく愛していたが、その当時の車両が、次の駅に着く直前、電流のスイッチの切り替えか何かで、車両のランプが一瞬全部消えることをたいそう嫌がっていた。今、銀座線には、そんなタイプの車両はもう走っていない。
そんなわけで、メンデルスゾーンのヴァイオリン・コンチェルトを聴くたびに、私は街路樹の木の葉が風に渦巻いて飛んでいく、秋のあの日が思い浮かぶ。そして、ねづっちが「整いました!」と言うたびに、あの車中での謎かけ遊びと、瞬間的に点滅する電光に、シルエットになった友人の横顔を想い出す。
降る雨に打たれたように、心も体もしんなりと疲れた夜。家路を辿るときに聴きたいのがマーラーの交響曲第5番である。
あのメロディを、いかに明るく健康的な初夏の陽光の下で聴こうとも、目の前には、すぐさま、ベルベットのカーテンやソファ、レースの襟飾り、紫煙、琥珀色のブランデーグラスと氷が触れる音のする、薄暗い室内が広がる。
ヴィスコンティ「ヴェニスに死す」のせいばかりとはいえない。私の瞼の裏には、トーマス・マン『魔の山』が映画化されたときのBGMもこの音楽だったような気がするし、三島由紀夫『豊饒の海』も、夢野久作も江戸川乱歩も、あの、たゆとうようなメロディのうねりに、のみ込まれていく。
20世紀前半、世界中を暗雲で覆った二つの大戦の狭間の、明日なき者たちの、あだ花のような空虚な繁栄と絶望感。ドイツ第三帝国やら、栄耀栄華を極めたものたちが終焉する前夜の、貴族の館を彩るのが、マーラーの交響曲5番なのだ。
退廃的な、すべてを諦めたような、いいんだ、このまま崩れていこう…というような没落志向の、脱力状態、気力のなさを許してくれる、ありがたい曲だ。
誰しもヘタレ込むとき、激励の言葉を聞きたくないほど疲れきって、心神耗弱の瀬戸際にあるとき、そのまま崩壊していくことを容認してくれる、マーラーの第5番が必要なのである。
堕落と退廃をうっとりと官能的に肯定してくれる。…この管弦の甘やかなメロディの谷間に落ち込んで、崩折れて朽ち果てることをにっこりと、受け入れてくれる。いいじゃないの…とことん墜ち込んでそのまましばらくしていると、何となく、生まれ変わったようになって、明日に立ち向かっていこうという、勇気が湧いてくるから不思議だ。
先日、父君を亡くした友人の激励会で、堺正章「街の灯り」を歌った友人が、ぽつりと、やっぱりこの曲がダメだ、いちばん泣ける…と呟いた。
一番泣ける曲…。条件反射なのに、無条件でいちばん泣ける曲。
それは私にとっては「埴生の宿」である。もう、イントロの、三音目ぐらいで泣いている。あのメロディが流れてくると、「みずしまぁ…、いっしょに日本へ帰ろう…!」という内藤武敏だったか、三國連太郎だったかの兵隊さんたちのセリフがかぶさってきて、もはや私の平常心は修復不可能。これはすべて、『ビルマの竪琴』、そして故・市川崑監督のせいである。リメイクされるたび、CMが流れるたびに、それだけでもう、涙腺が決壊していた。
芸のためでも何でもなく、私を泣かすには玉ねぎもいらず、埴生の宿が三音あればよいのであった。
その友人は下町生まれで、学校では近世文学を専攻していた。とくに『醒酔笑』など、江戸のお笑いについて研究していて、電車の中で謎かけをしたりしていた。当世流行の「なぞかけ」であるが、そのころは、何年かごとにやってくるお笑いブームの狭間のような時期で、世間にははばかられる、ちょっとシブイ遊びだった。
友人は地下鉄銀座線をこよなく愛していたが、その当時の車両が、次の駅に着く直前、電流のスイッチの切り替えか何かで、車両のランプが一瞬全部消えることをたいそう嫌がっていた。今、銀座線には、そんなタイプの車両はもう走っていない。
そんなわけで、メンデルスゾーンのヴァイオリン・コンチェルトを聴くたびに、私は街路樹の木の葉が風に渦巻いて飛んでいく、秋のあの日が思い浮かぶ。そして、ねづっちが「整いました!」と言うたびに、あの車中での謎かけ遊びと、瞬間的に点滅する電光に、シルエットになった友人の横顔を想い出す。
降る雨に打たれたように、心も体もしんなりと疲れた夜。家路を辿るときに聴きたいのがマーラーの交響曲第5番である。
あのメロディを、いかに明るく健康的な初夏の陽光の下で聴こうとも、目の前には、すぐさま、ベルベットのカーテンやソファ、レースの襟飾り、紫煙、琥珀色のブランデーグラスと氷が触れる音のする、薄暗い室内が広がる。
ヴィスコンティ「ヴェニスに死す」のせいばかりとはいえない。私の瞼の裏には、トーマス・マン『魔の山』が映画化されたときのBGMもこの音楽だったような気がするし、三島由紀夫『豊饒の海』も、夢野久作も江戸川乱歩も、あの、たゆとうようなメロディのうねりに、のみ込まれていく。
20世紀前半、世界中を暗雲で覆った二つの大戦の狭間の、明日なき者たちの、あだ花のような空虚な繁栄と絶望感。ドイツ第三帝国やら、栄耀栄華を極めたものたちが終焉する前夜の、貴族の館を彩るのが、マーラーの交響曲5番なのだ。
退廃的な、すべてを諦めたような、いいんだ、このまま崩れていこう…というような没落志向の、脱力状態、気力のなさを許してくれる、ありがたい曲だ。
誰しもヘタレ込むとき、激励の言葉を聞きたくないほど疲れきって、心神耗弱の瀬戸際にあるとき、そのまま崩壊していくことを容認してくれる、マーラーの第5番が必要なのである。
堕落と退廃をうっとりと官能的に肯定してくれる。…この管弦の甘やかなメロディの谷間に落ち込んで、崩折れて朽ち果てることをにっこりと、受け入れてくれる。いいじゃないの…とことん墜ち込んでそのまましばらくしていると、何となく、生まれ変わったようになって、明日に立ち向かっていこうという、勇気が湧いてくるから不思議だ。
先日、父君を亡くした友人の激励会で、堺正章「街の灯り」を歌った友人が、ぽつりと、やっぱりこの曲がダメだ、いちばん泣ける…と呟いた。
一番泣ける曲…。条件反射なのに、無条件でいちばん泣ける曲。
それは私にとっては「埴生の宿」である。もう、イントロの、三音目ぐらいで泣いている。あのメロディが流れてくると、「みずしまぁ…、いっしょに日本へ帰ろう…!」という内藤武敏だったか、三國連太郎だったかの兵隊さんたちのセリフがかぶさってきて、もはや私の平常心は修復不可能。これはすべて、『ビルマの竪琴』、そして故・市川崑監督のせいである。リメイクされるたび、CMが流れるたびに、それだけでもう、涙腺が決壊していた。
芸のためでも何でもなく、私を泣かすには玉ねぎもいらず、埴生の宿が三音あればよいのであった。