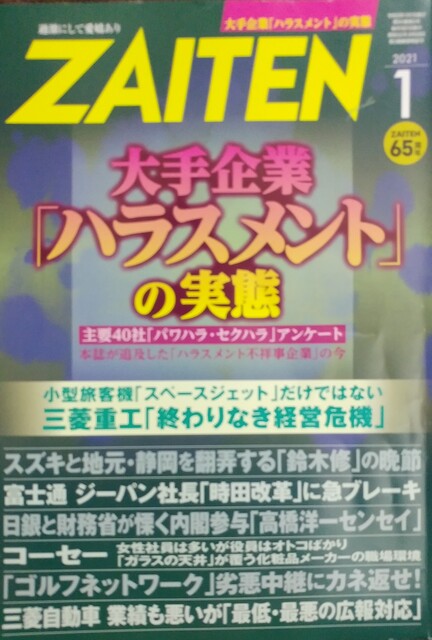トヨタ自動車が3月に立ち上げた自動運転ソフトウェア開発の新会社「Toyota Research Institute Advanced Development」(TRI-AD)はこのほど、即戦力となるエンジニアの新規採用を開始した。同社に出資するトヨタ、アイシン精機、デンソーからのエンジニアを含め、将来的に1000人規模の開発体制を目指す。
【画像】募集要項の例
TRI-ADは、乗用車の自動運転技術や自動運転用地図の自動生成技術の開発、およびhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180615-00000085-zdn_n-sci
【画像】募集要項の例
TRI-ADは、乗用車の自動運転技術や自動運転用地図の自動生成技術の開発、およびhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180615-00000085-zdn_n-sci